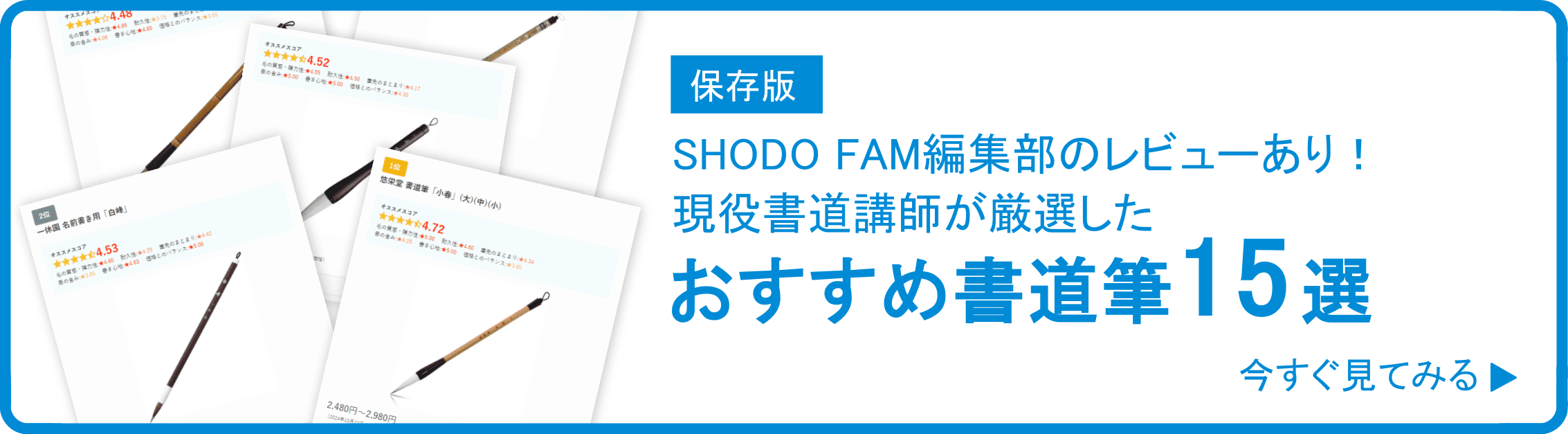筆はお店に行くとたくさんの種類やサイズがあってどれを選べばいいか難しいですよね。
また、筆の洗い方、乾かし方、保管方法によっては筆の持ちがずっとよくなります。
今回は筆の選び方、扱い方を紹介していきます。
書道をはじめるなら、オンラインという選択肢も!
SHODO FAMなら、あなたのペースで、いつでもどこでも書の学びを深められます。

書き方動画を見ながら練習して、書いた作品はスマホで撮って提出するだけ。
添削・サポートつきだから、ひとりでも安心して続けられます。
\6月30日まで!7日間無料キャンペーン/
筆の種類
書道で使われる筆は、先をカットしていない動物の毛をたばね、竹や木の筒の先に差し込んだ東洋独自の筆記用具です。やぎや馬、いたちなどいろいろな動物の毛が使われ、最近ではナイロンで作られたものもあります。
絵画で用いられる筆は、一定の圧力で絵の具が塗りやすいように、毛先をカットされており、かなりの弾力があります。
しかし、書道の筆は先がカットされていない毛で作られているため、扱いに慣れれば多彩な線を書くことができます。そして、線の太細やにじみ、かすれなど、線の変化が書道の重要な表現要素であるため、いろいろな動物の毛が使われてきました。動物の種類によってやわらかい毛やかための毛、毛が長いものや短いものなどがあります。
中国の筆と日本の筆
基本的に日本で作られた筆を「和筆」、中国で作られた筆を「唐筆」といいます。
しかし近代、現代では分業化がすすみ日本製と中国製の区別がつけにくくなっています。
- 原材料を日本国内で調達して、製造もすべて日本
- 原材料は中国のものを用い、製造は日本
- 下処理をした材料を輸入して、日本で製造
- 出来上がった毛の部分だけを輸入して、日本で製造
- 日本風の完成品を輸入して、筆の名前だけを日本で書く
- 日本風に作った完全な完成品を輸入
- 中国で日本人が指導した日本仕様の完成品を輸入
- 原材料から製造までを中国で行った中国風の筆
ただ、最も重要なのは毛の部分になるため、それをどこで作ったかが和筆と唐筆の違いのポイントと言えます。
これは私の一意見としてとどめていきますが、中国製は質とアフターケアが伴わないのが現実です。日本の筆製造技術はすばらしいものがあります。
電化製品や衣服などは、製造した国名が書かれているのは当たり前ですが、筆にはそういった文化がありません。
筆を買う際には店員さんに聞いてもわからない場合が多く、これを改善するには日本でそのすばらしい製造技術を受け継いだ職人さんを育成していく取り組みが必要だと思います。
筆の選び方
筆を選ぶときは、どんなサイズの字を書くのか、かたい毛がいいかやわらかい毛ががいいか、予算はどれくらいか、など、いろいろな要素を組み合わせて決めます。多くの書道専門店では専門知識を持つ店員さんがいると思うので、希望を言って選んでもらうのがいいと思います。
実際に私は入店してまずすることは筆コーナーを探すことではなく、店員さんを探すことです。
「半紙に4文字でひらがなを書きたいんですけど、安い筆でいいです。」
「半紙に6文字で楷書を書きたいんですけど、どの筆が人気ですか?」
書道教室の先生や書道団体によって基本的な筆が決まっていたり、また独自で筆を作り、それを指定にしている場合も多いので気を付けましょう。
筆のサイズ
筆のサイズは戦前は尺寸法で表記されていました。しかし、1966年(昭和41年)に、小中学校への普及を進めるために、書道用品の生産者団体によって、より簡単な「号」が決められました。
それ以降、販売業者もおおむねこれに従っていますが、「大」「中」「小」などという表記がされている場合もおおく、統一がとれているわけではありません。
「号」を表記しないメーカーもありますが、基準として表を作りました。
| 号数 | 直径(㎜) | 直径(寸) | 標準時数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.0 | 5分以上 | 半紙1字 |
| 2 | 14.5 | 4分8厘 | 半紙2字 |
| 3 | 13.0 | 4分2厘 | 半紙4字 |
| 4 | 11.0 | 3分6厘 | 半紙6~字 |
| 5 | 10.0 | 3分2厘 | 半紙8~12字 |
| 6 | 8.5 | 2分8厘 | 半紙20字 |
| 7 | 7.6 | 2分5厘 | 碑文用 |
| 8 | 6.7 | 2分2厘 | 辞令用 |
| 9 | 6.1 | 2分 | 書簡用 |
| 10 | 5.5 | 1分8厘 | 書簡用 |
筆のサイズは1号を最大として2号、3号と10号までしだいに小さくなります。
とはいえ、現在の号数表示はメーカーによって微妙に違うため、筆を購入さる際には号は参考程度に、具体的なサイズで決めましょう。
良い筆の条件
筆として最低限必要なことは3つあります。
- 筆の先が1つにまとまること
- 弾力があること
- 耐久性があること
1について、最初から筆の先にまとまりがなく、毛先がきかない場合は筆として不適切です。
2について、毛の種類や配合によって差がありますが、筆には弾力がなくてはなりません。筆を紙に軽く押し付けて、紙から離した時にまがったままで戻らないものは筆として失格です。
3について、物はなんでも長く使えるものがいいに決まっています。安くてすぐ傷んでしまう物を何回も買いなおすより、ある程度の値段で長く使えるものを選びましょう。
良い筆の選び方
筆は職人さんが手作業で作っているため、同じ種類の筆でもクオリティに差が出てしまいます。お店で筆を選ぶときはノリで固められていて見分けにくいですが、そのなかで一番良いものを選びたいですよね。
私自身、どれもそれほど変わりはないと思っていますが、一応見ておくべきポイントを紹介します。
- 穂先がとがっている
- 毛がバランスよく配合されていること
- 毛の部分がきれいな円錐形になっていること。ひねりがあるものは避けましょう。
- 毛が丈夫で弾力があること
同じ種類の筆どうしで差があるものはハズレを選ぶ可能性があるため、別の種類の筆に変えましょう。
筆の後始末、保管方法
筆は使った後、筆についた墨液を取り除きます。余分な墨が残ると筆の根元に「墨溜まり」ができ、毛が割れる、抜け毛、切れ毛の原因になります。また、濡れたまま密封(購入したときについていたキャップをはめて保存)すると、湿気がこもって腐敗や異臭につながるので注意しましょう。
使い終わったらそのまま水道で洗うか、バケツなどに水をためて両手を使ってていねいに洗いましょう。とくに、根元にたまった墨を指先でつまむようにして墨がほとんど出てこなくなるまでしっかりと洗うようにしましょう。
洗い終わったら水気を十分に取り、つり下げるなどして、筆の先が下になるようにして乾燥させます。下に向けることが無理なら、横に寝かせましょう。
筆が乾いていない状態で歯ブラシたてのように筆の先を上にして保管すると、根もとで墨が固まり「墨溜まり」ができてしまいます。
筆は書道用具店で買うようにしよう
筆は、スーパーや百円ショップなどで売っているところを見ますが、信頼できる専門店で購入することをお勧めします。
知識がないのではずかしいとか、高いものを買わされるのではないかなどという心配はしなくていいと思います。
どこの専門店も知識のある店員さんがいて、聞いてみれば親切に教えてくれます。
どうせ買うなら水準をクリアしたちゃんと使える用具を使って、作品制作を楽しんでください!