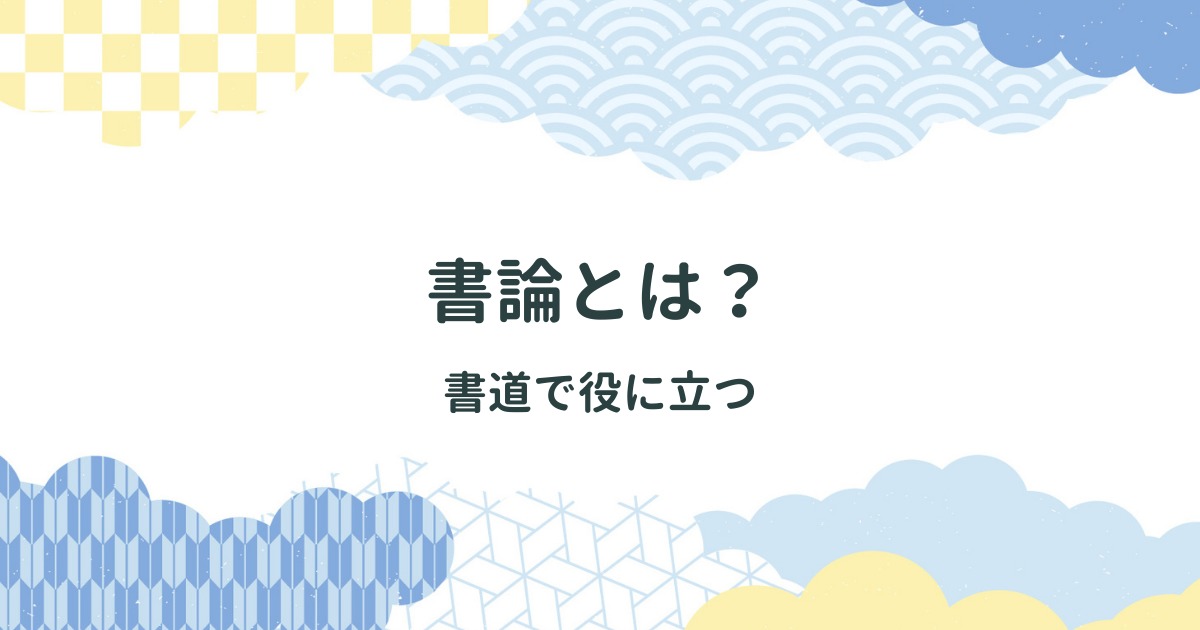書道をはじめるなら、オンラインという選択肢も!
SHODO FAMなら、あなたのペースで、いつでもどこでも書の学びを深められます。

書き方動画を見ながら練習して、書いた作品はスマホで撮って提出するだけ。
添削・サポートつきだから、ひとりでも安心して続けられます。
\6月30日まで!7日間無料キャンペーン/
書論とは
書論とは、「中国書学」の理論、または「中国美学」のなかの「書法」としての理論です。
簡単に言うと、書をめぐるさまざまな議論を指します。
もちろん、その議論は書き記されていないと残りませんから、基本的には書物や文献の形で伝わるものを対象とします。
書論の歴史は古く、古来の賢人たちは、数々の名言を今日に残しています。
そこには、現代でも色あせない新鮮な発想があったり、書に対する情熱が行間にあふれるようであったり、確かな経験に裏付けられた知恵があったりします。
これら賢人の言葉に触れることで、私たちは、書の見方を豊かにすることができます。
書のあり方や自身のかかわり方について、考えを深めることもできます。
みなさんがこれから進むべき方向のヒントも、ここに隠れているかもしれません。
書論の読み方
書論のタイプによるところもありますが、書論を読むことは、普段の読書と似ていて、2つのアプローチがあるように思います。
知識を得る読み方
1つは、何かを知るために読むアプローチです。
書論から自分が興味や関心を持っている問題について「情報を得ようとするもので、知識の伝達を中心とした書論が主な対象となります。
ただし、古来の書論を広くあさってみても、満足のゆく情報が得られるとはかぎりません。
例えば、技能を向上させようという思いから、種々の書論が説く技法を参考にしても、自身の現状にそぐわず、かえってマイナスに作用することもあります。
書論は常にベストアンサーの宝庫というわけではなく、即効性の万能薬が詰まっているわけでもないことを心にとどめておく必要があります。
考えさせられる読み方
そしてもう1つは、楽しみ、味わうために読むアプローチです。
書論は、小説や物語とは違いますが、単に知識や情報を提供するだけでなく、語り手の話が面白かったり、じっくり考えさせたりするものが、少なくありません。
当然、退屈に思えるときもあるでしょう。
そんな時には、「この語り手は、何にこだわっているのだろうか?」と考えてみてください。
ひとまず書論の語り手の立場に立って、語り手が抱える問題を自分の問題として共有しようとするものです。
語り手の話題を自分が論ずるなら・・・と考えると、退屈そうな話題が、実は自分にとって切実な問題だったりもします。
さらに、「この語り手が、こんなことを言うのはなぜか?そこにどんな背景があるのか?」とも考えてみてください。
言葉を発するには、それなりの理由があるものです。
それは、語り手の個人的な事情にとどまらず、語り手の置かれた環境や時代に深くかかわることもあります。
そうした背景に思いをめぐらすことは、私たちの書論の理解をさらに確かなものにしてくれます。
実際に読んでみる
言うまでもなく、古い書論は古文・漢文で書かれています。
そのことは、書論が敬遠される最も大きな理由の1つになっています。
古代語という言葉の壁は厚く、これを超えることは決して容易ではありません。
しかし、そんなことの理由で壁の向こうの豊かな世界を味わえないとしたら悔しいでしょう。
幸いにも、古来の代表的な書論には、優れた訳や注釈があります。
初心者に限らず普通の方は原文を読もうなんてしなくても有名な書論の現代語訳だけ読めば十分です。
原文を読むのはその分野の専門家くらいです。
最後に
「知識が邪魔をする」とは、よく聞く言葉です。
書論から得た知識や情報も、時としてマイナスの作用を及ぼすかもしれません。
しかし、「知識が邪魔をする」という豆知識が、みなさんの進歩を邪魔するとしたら、それはとても残念なことです。
書論との出会いはみなさんの可能性との出会いでもあります。今後の意義ある出会いを祈ってます!