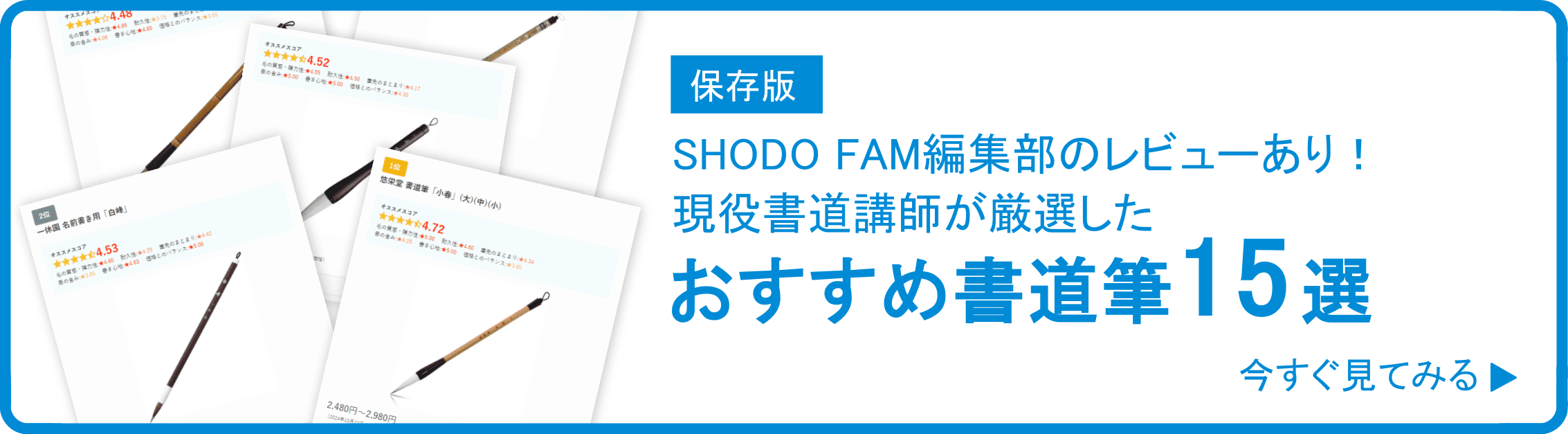書道をはじめるなら、オンラインという選択肢も!
SHODO FAMなら、あなたのペースで、いつでもどこでも書の学びを深められます。

書き方動画を見ながら練習して、書いた作品はスマホで撮って提出するだけ。
添削・サポートつきだから、ひとりでも安心して続けられます。
\6月30日まで!7日間無料キャンペーン/
才葉抄とは
才葉抄とは、平安時代末期に著された書論書です。
世尊寺家7代目の伊経に、藤原教長が書道の奥義を口伝した内容が書かれています。
書道の秘伝を語った藤原教長について
藤原教長は、難波権大納言忠教卿の6男として1108年(天仁元年)に生まれ、1180年(治承4年)に没したといわれます。
平安時代末期の能書家で、世尊寺流の書を学んだとされています。その書の技能、見識は一流のものです。
歌の道にも優れ、崇徳院・藤原頼長に特に重んじられました。
その教長が、1177年(安元3年)69歳のとき、高野山の庵室において書の道についてさまざまな抱負や見識を語った記録が、「才葉抄」です。
才葉抄が著された経緯
崇徳上皇と後白河上皇の対立によって、1156年(保元元年)保元の乱が起こりました。
後白河側には摂関家の藤原忠通、崇徳側には異母弟の頼長がつきます。
乱はあっけなく終了し、後白河側の勝利に終わります。
頼長側についた藤原教長は常陸に流罪、その後剃髪して、高野山に隠棲します。
教長は当時台頭してきた法性寺流にも注目しながら、世尊寺流の書法を熱心に体得していました。
そこで世尊寺家第7代目伊行はわざわざ高野山に赴いて世尊時流の書の奥義を求めに行きます。
この聞き書きをまとめたのが『才葉抄』です。
才葉抄の現代語訳
(才葉抄…一名筆躰抄)
才葉抄…またの名を筆躰抄という
(宰相の入道教長口伝)
宰相であった入道の藤原教長の語り伝えたものである
(安元三年七月二日。高野山庵室に於て密談す。諱は観蓮。難波権大納言忠教卿の第六男。参議正三位。)
安元3年(1177年)7月2日。高野山の庵室で密談した際の記録である。教長の法名は観蓮といい、難波権大納言忠教卿の第6男で、参議正三位の官位を得ていた。
(一、筆はいまだ墨を染めざる新筆にて文字を書くは、帯とけひろげてあしきなり。墨をぬりて乾かして、少し墨枕あるがよきなり。)
まだ墨をつけて使ったこのない新しい筆で文字を書くと、筆は帯がほどけて、着衣がだらしなく広がったような状態になってまとまらず、書きにくい。筆は墨を筆全体につけてから洗い乾かして、少し筆毛の根元が固くなってしっかりした状態になってからが書きよいのである。
(一、法性寺殿の御筆は、書く人の右へ平みたるなり。)
法性寺殿(藤原忠通)の御筆づかいは、書く人の右の方へと筆が倒れた状態(側筆)で書かれている。
(一、文字は、一字を取りはなしても、おのおのの文字なる体にうつくしく見ゆるやうに書くべきなり。すなはち、重なる文字は、高かるべきなり。並ぶ文字は、横へひろがるべきなり。)
文字は1字だけ取り離しても、その一字一字が、姿が整って美しく見えるように書かねばならない。つまり、上下に重なる文字は縦長にした形になるのがよいし、偏と旁からなる文字は、横に広い姿にすべきなのである。
(一、墨を筆にだぶだぶと染めて書くべきなり。)
墨を筆になみなみとたっぷりつけて書くのがよいのである。
(一、行の物の中に、真文字も相加ふるべきなり。道風は、さやうにかきたつを愛敬といふ。)
行書の中に真文字すなわち楷書も少し加えるとよい。小野道風は、そのように書いたものを愛敬があると言っている。
(一、文字不具なる事あるべからず。偏小にして旁大に、外囲大にして、内をば小さくかくことなり。あしきなり。道風。佐理。行成の手跡。不具なる字画なきなり。)
文字は調和を崩す不備な点があってはならない。例えば偏が小さいのに旁がやたら大きくなったり、かまえを大きくして、内の部分を小さく書いたりすることである。アンバランスで醜い。道風・佐理・行成の書ではそのような不具なる字画はない。
(一、長く引く点は斜す。また麗しきは弱きなり。少しゆるめて引くなり。)
長く引く点は側(偏鋒)を用いて斜めに書くが、平順にすぎると弱くなる。少し筆の運びをゆるがせながら引くとよい。
(一、頭の字は、皆ひらみたるなり。それがよきなり。)
行頭に置く字は、少し偏平になるのがよい。
(一、文字は、うるはしく書くが見通しあるなり。点をかたよせなどしたるは、一旦の愛にて、始終は見弱りするなり。)
文字は端正に書くのが、見た目がよい。点を一方に寄せて打ったりしたものは、一時の愛敬はみられるが、いつものことでは見た目にも魅力に欠けてしまうものだ。
(一、未練の間は、文字を高く書くべきなり。究竟になる時は、少し平らになる事なり。されば道風などの書きたる物は、若き手のときは、文字高きなり。老後に至りては、平みて見ゆるなり。)
まだ書が上手でない間は文字の姿を丈高く書くべきである。上手になった時は、少し偏平になるものである。だから、小野道風などの書いた物は、若いころは文字は丈高くなっているが、歳をとってからは平たく見えるのである。
(一、申状、諷誦、願文は真に書くべきなり。廻文は、行に書くべきなり。)
申文、諷誦文、願文は、楷書体で書くべきである。廻文は、行書体で書くべきである。
(一、法性寺殿の手跡は、若年の時摂政などの時はよきなり。後に筆平みて、打ち付け打ち付け書き給ふによりて、習ふ人の手跡損ずべきなり。いづれもこの心を得べきなり。)
法性寺殿(藤原忠通)の書きぶりは、若い時や摂政であったころはうまいものである。しかし、年老いてからは筆がかしいで、ペタペタと筆が紙にあたるように何度も墨つぎをしてお書きになられるので、習う人の書きぶりを害することであろう。いずれにしてもこのことは心にかけて注意すべきである。
(一、点の終りの筆をば必ず返すべきなり。「ゝ」これがよきなり。)
点の終筆は必ず引き返すべきである。「ゝ」の用筆が大切である。
(一、真の筆は立つべきなり。行の筆は平むべきなり。)
楷書を書くときは筆を立てるべきである。行書のときは傾けて書くのがよい。
(一、筆を打ち立てて後は、行くにまかせて書くべきなり。筆をすまひて書きつれば、筆こはくみえてわろし。ゆるゆるさしのべたる筆にて、みたみたとなさず書きたる物は、見立てあるなり。強さ筆にて書きたるは、見立てなきなり。)
筆の鋒尖をくじいて筆落として後は、筆の動きに自然にまかせて書くのがよい。それに逆らって書くと筆致がごつごつみえてよくない。柔らかい毛の長鋒で墨をたっぷりとべたつかせず書いたものは見栄えがするものだ。剛毛の筆で書いたものは見栄えがしないものである。
(一、手書きは、つねに物を書くべきなり。しからずんば筆あしし。)
文字を巧みに書く者(能書家)は、ふだん筆をもって何かを書いていなくてはならない。そうしないと書きぶりが悪くなってしまうものである。
(一、朝隆は能書なり。されども幼き物を書き出すなり。)
藤原朝隆は筆のたつ人である。しかしながら、未熟なものを書き表すことがある。
(一、眞行草ともに前の点の先をうちて、後の点のはじめをば返すべきなり。)
楷書・行書・草書ともに前の点画の穂先をはずみをつけて突き、後の点画のはじめを穂先をくじいて書くのがよいのである。
(一、文字は分けて一字も真に書き、合字にても見よかるべき様に書く事は、大旨の事なり。字によりてゆがめて偏を書きて吉き字もあるなり。よくよく心得べきなり。
文字は連綿のなかで一字を楷書に書いたり、合字で書いたりしても見やすいように書くことが大切なのである。また字によっては、斜めに偏を書いて姿の整う字もあるものだ。十分心得ておかなければならない。
(一、前点は後点を兼ねる約束なれば、真行草ともに前点の筆先を受けて、後点の初めを書くべきなり。)
筆脈を保つのが書法の基本であるので、真行草ともに前の点画の筆先の流れを受けて、後の点画の初めを書くべきなのである。
(一、文字をば、みるみると書くべきなり。ハッキたるは、見あしきなり。)
文字は、みずみずしくつやをもって書くべきである。きっぱりとしてつやに欠けるものは、見ためがよくないものである。
(一、行成の手跡は、筆に任せて書かれたるとみえたり。また法性寺殿の筆はしからず。よっておとらせ給ふなり。
藤原行成の書は、自然のままに筆が動いて書いていると思える。また、それに対して法性寺殿の書の筆づかいはそうではない。その点で劣っておられるのである。
(一、草は、游たる筆を以て、やはらかなる筆にて書きたる字のやうに書くべきなり。)
草書は、蜘蛛の糸のごとく、空中にあらぐような筆致で、柔らかい毛の長い筆で書いた字のように書くべきである。
(一、先ず物を書くには、静かなる所にて、心をしづめて書くべきなり。物をいそがしく書くことなかれ。いそがしく書きたるは、いたらぬ故という人あるべし。これは故実をしらぬ人なり。何事も思はですると、麁相にするとは替ることなり。ことさら手は、硯筆紙墨四つ物相叶ひて成るべきなり。このことは今の案にあらず。本文にあり。第一率爾の時は誤事多し。また文字落とすこと一定あることなり。)
まず物を書くには、静かな所で、気持ちを落ち着かせて書くべきある。心いそがしく物を書くことがあってはいけない。せかせかとせわしなく書いたのは、書の技能が未熟のためだどういう人がいる。これは故実を知らない人である。何事も、意図せずに行うのと、粗末に行うのとでは、違いがあるのである。特に書は、硯・筆・紙・墨の4つがお互いに結びついてできあがるものである。このことは今の時代の考えではない。昔からの本文にある。第一、軽率に行うときは間違いが多い。また文字を落とすことが必ずあるものなのである。
(一、手跡と形とは一つなり。また人の心も見ゆるべきなり。されば異様に書くべからず。皆本文にあり。)
筆跡と字形とはおおきなつながりをもっている。またそこに書く人の心もみることができる。だから、異なった俗体に書いてはいけない。このことについては皆、本文にある。
(一、我が好むやうならずとて、さうなく人の手を謗ることがあるべからず。手にむじんの様あり。また人の心万差なり。ただ筆づかひ、筆の品の善悪をわきまふべきなり。いかにも手書きの書きたる物を早く書くよしをして、筆をはやくつかふ こと、かへりておぞき様なり。相構へて筆を立つる所、折る所、引きはつる所に心をかくべきなり。とかく、能書には目を付けて見るべきなり。)
自分が好まないからといって、無造作に他の人の書をけなすことがあってはいけない。技法にはさまざまな趣があるし、また人の心もいろいろ違いがある。ただ、筆づかいをみたり、書の品格のよしあしを弁別できるようにすべきである。書けもしないのに、いかにも達筆家がかいたもののように早く書く格好をして、筆をはやく使うことは、かえって品がなくおろかである。しっかりと、筆を立てる所、折る所、引き切る所に心をかけるべきである。いずれにせよ、能書作品は注意して観察することである。
(一、物忩なればとて、散々に書くことあるべからず。真行草、ともにいづれもねばく書くべし。未練の手跡は、物を早く書きなして僻事あるものなり。いかに疎草に書くものなりとも、筆の捨て所に心を懸くべきなり。)
あわただしく落ち着かないからといって字をまとなりなくいい加減に書くことがあってはいけない。楷行草、いずれも粘っこく書きなさい。未熟な人の筆跡は速書きして書き違えがあるものである。いかに軽率に書く字であっても、筆の捨て所、終筆部分に注意すべきである。
(一、未練の時、左右なく物を書くと披露すべからず。よくよく習練して手の品を書き出してのち、手本をも書き、また人にも見ずべきなり。その人は能書なるなれども、少々しられて後は、少しわろきことありとも思免せらるるなり。物わるく見られ沙汰せられぬれば、後に能書となる時も、人の許すこと難きなり。手書きは分限を見るべし。世間に手書き少なし。非なる手書き多き故に、手書きに非ざるはわろしとののしるを、いつも定めて信ずるなり。されば、昔の手書きは、手習ひしたる反古をも焼き捨てけるなり。ただし、手の故実をも習ひ談義せん人には、はづべからず。相互ひに談ずべきなり。)
書の技能が未熟な時、無造作に字を書いて人に見せるべきではない。充分に習練をかさねて、書にその人柄や品格を書き表せるようになってから、手本なども書き、また人にも見せるのがよい。その人が能書家であって、少々世間に知られてからは、多少失敗作があっても許されるものである。逆に書く物が悪く見られ評判になってしまうと、あとで能書家となっても、人々が認めてくれることは難しいものである。だから書をする者は身のほどを知らねばならない。世間に本当の能書家は少ない。間違った考えの能書家が多いために、能書家でない人の書はよくないと、悪口をいうのを世間ではいつもきまって信じている。だから、昔の能書家は練習して使い古した紙さえも焼き捨てたという。ただし、昔の故実をも学び、意見してくれる人には恥ずかしがるな。お互いに話し合うべきである。
(一、額。色紙型。申文。願文。諷誦。叡山四番帳。戒牒。一品経等書くべき次第は、広く夜鶴庭訓といふ書にみえたり。これ先達の仕おきたることなれば、信ずべきなり。)
額。色紙型。申文。願文。諷誦。叡山四番帳。戒牒。一品経等の書き方は、広く夜鶴庭訓抄という書物に書いてある。これは先輩の方々が書き残したことなので、信じられることであろう。
(一、真の物は、第一の大事なり。唐人は、先ずこれを習ふなり。我が朝にもしかるか。近代は、皆行の者を先に習へり。されば真に達したる人稀なり。少々文字不具なれども、能書の様とて書き様あり。また、たださわさわとゆがめます、文字の座もはたらかず書きたる一の品なり。宋朝の欧陽が真がかくのごときなり。これは少し愛を取るなり。心より愛敬のある難なり。すべて上古の能書も、皆満足することは難なり。されば、法性寺殿は、むかしの手書きには、道風、佐理、行成、この三人を能書を宣へり。この三人に三徳三失あるなり。道風は強く書きて少し俗風なり。強さは徳、俗道は失なり。佐理は、やさしくてよわし。やさしきは徳、よわきは失なり。行成は打ち付けに愛敬ありて、手の少し正念なきなり。愛は徳、正念なきは失なり。故に太平御覧には、骨多く骨少なきは墨猪、力多くして筋ゆたかなるは聖なり。力なく筋なきは病なりと云々。)
楷書は、最も大切なものである。中国の人は、まず楷書を学ぶのである。我が国においてもそうであろうか。いやそうではあるまい。現在は皆行書を先に習っている。だから、楷書に深く通じた人は極めて少ない。少しぐらい文字が整っていなくとも、能書であるように書く書き方がある。やはり、ただうるさい様子で文字がゆがんだりせず、字と字の余白も生きているように書かれた作品は最高である。宋朝の欧陽脩の作品は少し意を取ったものである。心の底から愛敬のあるものは難しいものであり、すべて上古の能書も、皆が満足することは大変なことである。ところで、法性寺殿は、昔の書家では、道風、佐理、行成、この三人を能書家とおっしゃられた。しかし、この三人にも長所短所がある。道風は、強く書いて俗っぽい。強さは徳、俗っぽさは失である。佐理は優麗であるが弱い。やさしさは徳、弱さは失である。行成は、(落筆に)愛敬が表れて筆跡に少々しっかりしたところがない。愛は徳、正念のないのは失である。だから『太平御覧』には、骨多く、肉の少ないものは筋書、肉多く骨が少ないのは墨猪、力が多くて筋がゆたかなものは聖であり、力なく筋もないのは病の書であると述べている。
(一、物を書くには、 よくよく心を調じて思量すべし。荒く書くことなし。猶々、存ずべきこと、太平御覧には、軍陣に向かひて合戦なるべく思ふなり云々。またいふ。右軍(王羲之)衛夫人筆陣の図に題して曰く、「それ紙は陣なり。筆は刀矟なり。墨は鍪甲なり。水硯は城池なり。本師(心意)は将軍なり。心意(本領)は副将なり。結構は謀略なり。颺筆は吉凶なり。出入は号令なり。屈折は殺戮なり。それ書かんと欲して、まづ墨を研ぎ、神を凝らし思ひを静かにし、あらかじめ字形の大小偃仰平直振動を想い、筋骨をして相連ねしめ、筆意前に在りて、然るのち、字を作す云々」と。一番に知るべきなり。)
物を書くには、十分心を調えて考えることだ。乱暴に書くことはしないことだ。ゆったりと考えながらやるべきこと、『太平御覧』には、軍陣に向かって、合戦するように考えるべきである云々とある。またさらに、王羲之が衛夫人の作品筆陣図に題していうには、「そもそも紙は陣である。筆は刀や矛である。墨は甲骨である。水の入った硯は城を囲む堀である。師匠は将軍である。心は副将である。字の構えは策略である。筆をもつことは吉凶である。筆を紙につき放つ時は命令である。転折曲折は殺戮である。そこで書こうとして、まず墨をすり、気持ちを集中して心を静かにおちつかせ、前もって字形の大小、俯仰、平直、筆の振幅を考え、落筆の前に、作品の構想を練ってから字を書く云々」と。第一に理解すべきである。
(一、手本を習ふには、まず本の筆づかひを心得べきなり。本の意趣を心得ずして、筆にまかせて習ひつれば、本に向かふ時ばかりにて、我と書かれぬことなり。いづれの手本を習ふにもこの心を得べきなり。)
手本を臨書するには、何よりもまず、手本の筆づかいを理解しなければならない。手本の筆意の趣を理解せずに、自分勝手に筆にまかせて書いていると、手本に向かう時だけは書けたような気になるが、自分で筆をすすめてみると書けないものである。だから古法を心得ている人に習うのがよい。どんな手本を習うにもこのことを覚えておくべきである。
(一、手を習ふに本にも似たり、我もよく書くと思ひて本を捨て、雅意にまかせて書くは、自然に損ずるなり。いかにも初心の間は、よくよく用意すべきなり。さらば、ある先達の申すは、四、五十歳になりて、手は定まるともうし候ひしが、このことさることなり。不でもしたたまり、功が入りて後は、ともかうも書きたるは、苦しからざるなり。)
字を習うとき、手本にも似たし、自分でもよく書けたと思って手本をおろそかにして、勝手気ままに書くと、自然と失敗してしまうことになる。ほんとうに初めのうちは十分に心をくだいて字を習うべきである。だから、ある先輩の方が、四、五十歳になって初めて書は確かなものになると申しましたが、この事は、もっともなことである。筆づかいもしっかりし、習熟した後は、どのように書いても見苦しくないものである。
(一、手を習ふには、本の筆づかひ、意趣をこころえずして、ただ学びまた習ひたる文字ばかりをおぼえては、習はざる字は書かれざるなり。大旨だにも得つれば、自然に似ることなり。手本の意趣を心得ることは、未練の時は知り難し。先達に習ふべきなり。手跡にて人の心の程は知らるなり。されば相構へて異様に書くべからず。故に本文に曰く、「筆の用うるは心に在り、心正しければ則ち筆正し」」となり。」
字を臨書するには、手本の筆づかい、手本の筆意の趣を理解しないで、むやみに繰り返し学んだり、また習った文字ばかりを覚えたのでは、習っていない文字が書けなくなってしまう。だいたいの筆づかい、意趣だけでもつかめば、自然と似てくるものだ。手本の筆意をつかむことは、未熟の時はわかりにくいものである。先輩の指導を受けるべきである。書かれた字によってその人の心の様子は知れるものだ。そこで気をつけていい加減に書いてはいけない。だから、本文にも「用筆は人の心にもとづく。心が端正で真剣であれば、筆もしっかりと正しく運ばれる」とある。
(一、手本を多く見るべきなり。我が習はぬ手ならねばとて、必ず毀るべからざるなり。いかなる手跡も、皆おもしろきなり。捨て所知るべし。また、いかにも我と書かれざる文字をば、本を見て書かるるなり。縦ひまた習ふべきならねども、手書きの書きつる物を見れば、才覚付くなり。)
手本を多くみるべきである。自分の習ったことのない書だからといって、決して非難してはいけない。いかなる筆跡も、皆おもしろいものである。筆の運びをよく理解するべきである。また、どうしても自分では書けない文字でも、手本を多くみていれば、書けるようになる。たとえまた学ぶものがないとしても、能書家の書いたものを見ていると、書く上での工夫や知恵がつくものである。
(一、手本を数多持つべきなり。我が好むすぢならねばと思ふことなかれ。打見よく書きたれば、おもしろく能く候ふなり。能の中には、手が第一なり。身のため、人のため、よしあしに付けてありがたし。能書は大切なり。されば大国にもこの道をこそ重くせられ侍るなり。)
手本をたくさん持つのがよい。自分の好む書風ではないからどうもよくないなどと思ってはいけない。じっと見ると巧みに書いてあるので、心ひかれてなるほどと思うのです。技能に優れたものの中では、書が一番である。自分のため、他人のため、めでたい時も悪い時にも、尊いものであり、能書は大切な役目を持っている。だからこそ中国でも書の道を重んじているのです。
(一、手本には古歌古詩を書くべきなり。ただ、人の所望ならば、新歌新詩をも書くべきなり。消息も古き本にて書くべし。仮字消息は、すべて書くまじきなり。)
手本には古歌古詩を書くべきである。ただし人の望みであれば新歌や新詩でも書いてよい。手本も古い手本で書くべきである。しかし、仮名の手紙は、どんなものでも書くべきではない。
(一、屏風書写などは、仔細あることなり。道風の筆を見しが、綾の屏風に大きらかなる下絵をしたりしに、頭をさしつどへて、ただ行草に、筆に任せて書けりと見ゆ。大体この体有るなきなり。)
屏風書きなどは、その正しい書き方がある。道風の書いたものを見たが、綾の屏風に大柄な下絵をあしらったものに、行の頭をそろえてただ行草体で、筆のゆくに任せて書いたと思えた。大体、このような書き方があるとはいえない。
(嬾からん時、物書くことなかれ。文字あやしきのみならず、左様にしつければ、手あしくなるなり。吉き筆料紙にて、心のいさましからんをり書くべきなり。非能書は、この次第をしらずして、いつもたやすく書くとのみ知りて、費書するなり。されば、手を執せん人は、いか様に人言ふとも、とかくすべりて書くまじきなり。悪しく書きつれば、人に随ひて恥あるなり。人に随ひて書くは我が恥なり。我が損なり。かくのごときことは誰も知り易さことなれども故実の多きとは、かくのごときのことをこそ申し侍れ。手書きならざらん人も、この心を得べきなり。管弦なんどするには、あしき調子はかえてすべきなり。あしくとも構はず、卒爾にそのこととなくすることは僻事なり。諸道はただかくのごとくなり。)
大儀で気が進まない時は、物を書いてはいけない。文字がおかしくなるだけでなく、それが習慣になると、書き方も悪くなるものだ。よい筆をもって書きやすい紙で、心が気乗りしているときに書くべきである。書の下手な人は、このことを知らないで、いつも手軽に書くものだと思って、無駄書きをする。だから、書を大事に思う人は、どんなふうに人が言おうとも、上すべりして軽々しく書いてはいけない。悪く書いてしまえば、人の言いなりになって恥をかいたことであり、人に言いなりに書くのは自分の恥である。自分の損である。このようなことはだれでもわかることだけれども、意外と気づかない。古法をよく知っているものとはこのようなことをいうのです。書を習わぬ人でも、このことを覚えているべきである。管弦などをするにしても、悪い調子は、きちんとあわせてから演奏するべきである。悪くてもそんなことを気にもせず、いきなりあわてて準備なしにするのはよくないことである。どんな芸事でも、みなこのようなものである。
(一、物語、草子書くことは、能書のいとせざることなり。夜鶴に次第見えたり。)
物語の草子を書くことは、能書家はあまりしないものである。「夜鶴庭訓抄」にこのことについて述べられている。
(一、手習ひせんには、本に向かひてよく習ひて、物ぐさからぬ程、よき筆墨料紙にて書くべきなり。必ずその習ひつる文字ならねども、筆なるるなり。また本を持ちて習ひて、本をばかたかたに置きて見ずして書きて、本にあわせて見るべし。ただ本をもって習ひたるばかりにて、覚えざるは徒事なり。)
書を習うには、手本に向かってよく練習し、おっくうにならないように、よい筆、墨、料紙で練習するのがよい。そうすれば、必ず前に練習した文字でなくても、筆がきちんと運べるものだ。また、手本を用いて練習したあとは、手本をそばにおいて見ないで書いて、書いたあとに手本にあわせて見比べるとよい。ただ手本ばかりを用いて練習しているだけで、覚えないのは無駄なことである。
(一、手習ひするに、似ざる文字を相構へて似せんと、その字ばかりに心を尽くしぬれば、手習ひに退屈するなり。両三度も習ひて似ずば、しばらくその所を閣きて、別の所を習ひて、また帰りて習ふべきなり。かくのごとく度々重ねたれば、自然に似るなり。)
書を習うのに、どうしても似ない文字をなんとか似せようとして、その字だけに一所懸命になると、練習に飽きるものである。二、三度書いてみて似なければ、少しその所はおいて、別の所を練習して、また戻って書くとよい。そのように、何度かくり返していると、自然に似るものである。
(一、手習ひに貧福を思はず。また我も書き、人に物を書かせんにも、能々入木の道をば進むべきなり。されば、南史に曰く、「江夏王鋒。字は宣頴。高帝(注 斉)第十三子なり。年四歳にして、好んで書を学ぶに紙札なし。乃ち井欄に倚りて書を為す。書満つれば則ち之を洗ひ、已に復た書す。五歳にして高帝鳳尾諾を学ば使む。一たび学べば即ち工。皇帝大悦し、玉麒麟を以って之に賜ひて曰く、「麒麟鳳尾を賞す」と。異国例を以って、我朝にも、額・色紙形等書くには、必ず禄を賜ふことなり。みな之に准じて知るべし。くわしく夜鶴に見えたり。書く人も書かせん人も、かくのごとき故実をしるべきなり。顔魯公勅を奉じて額を書き、絹百疋を賜ふとなり。)
書を学ぶにあたって貧福を考えず、また自分も書き他人に物を書かせるような時にも十分に書の道を通すべきである。だから南史にいうには、「江夏王鋒、字は宣頴。斉の高帝の第十三子。年四歳で、好んで書を学んだが、書くべき紙や木札がない。それで井戸の囲いにもたれて書を書いた。書がいっぱいになると洗い流してまた書いた。五歳で高帝は鳳尾諾を学ばせたが、いったん学ぶとすぐに上手になった。高帝は大いによろこんで、玉の麒麟を賜って「麒麟が鳳凰の尾を賞めた」と。異国の例でもって、我が国でも、額や色紙型等を書く場合には、必ず報酬を受けることである。みなこれに合わせて知っておくがよい。くわしくは『夜鶴庭訓抄』に述べられている。書く人も書かせようとする人も、このような故実は知っておくべきである。顔魯公は、勅命によって額を書き、絹百疋を賜ったそうである。
(一、願文等の草案をば、清書の許に留めておくなり。清書する故實には、不審なることといへども、草案に任せて書くべきなり。これ清書の誤りにあらず。草案の僻事なり。)
願文等の草案を、清書した人の所に残しておくべきである。清書する故実からいくと、疑わしいものだと思えても草案の通りに書くべきである。これは清書の誤りでなく、草案の間違いなのである。
(一、物を人に誂へてあるのに、料紙のあまりたらんをば引き放ちて止めざるなり。料紙書き余りて、書かずして帰すは、手書きの恥辱なり。)
物を人に頼まれている時に、料紙が余ってしまったなら切り取って、そのままにしないことである。なぜなら、料紙を書き残して、何も書かないで返すのは能書家の恥辱であるからである。
(一、色紙形に物書くには、よくよく文字つづきを草案して書くべきなり。)
色紙形に物を書くときは、十分に文字の連綿を下書きしてから清書すべきである。
(一、必ず手本にさし当てて習はずといえども、つねづね心を懸けて見れば、自然に随分となるなり。わが書きたる物をも常々見て、善悪を思量すべきなり。)
必ず手本をそばに置いて学ばなくても、いつも心がけて手本を見れば、自然にずいぶんと上手になるものだ。自分の書いたものも常々見て、良いとこと悪いところを考えるとよい。
(一、近来弘誓院殿(注 教家)の御筆を学ぶ事。多くは以って損失するなり。その故は、地体に自在を得てあそばされたるに、筆勢を書きたる御筆どもも相交じりて、我が筆勢の程をも弁へず。御筆震えてあそばしたるを習ふ故、一定損ずるなり。地体くせもなく。筆もおさまりて後、少し筆勢をやつすは故実なり。且つは渥(涯)分を計りて、手も習ふべきことなり。いかやうにもまづなおく習ふべきなり。さてこの御筆は、一旦習ひ似するやうにはおぼゆれども、始終は難なり。故実多き人は、この様を捨て他筆を学ぶ事なり。能々得心なしにはいかで損ずべき哉。いづれの筆も、おそらくこゝろえては、損ずることなりとも、この御筆は大事に侍るなり。三月 日 伊経)
近頃、弘誓院殿(藤原教家1193~1255)の御筆跡を学ぶことが多いが、その多くは損をしている。その理由は、おもいのままによい結体を得て書かれてはいらっしゃるが、筆勢のある筆づかいにもまざって、自分の用筆の程度も考えないで、弘誓院殿の震えてお書きになったのさえもまねるから、必ず失敗してしまうものである。字体もよく整って、筆づかいもしっかりした後に、少々筆勢を崩すのは古法にもある。まずは、自分の力の程度を知って書を学ぶべきである。さて、この弘誓院殿の御筆跡は、一時は習って似たようには思われるけれども、結局はだめなのである。古法を多く学ぶ人は、この書風はやめて、他の書を学ぶことである。十分にこのことを心得ていないでどうして損わないですむのか。必ず損じてしまうだろう。いずれの書法も心得ていてもおそらく損うことがあるかもしれないが、この弘誓院殿の書風は難しいものであります。 三月 日 伊経