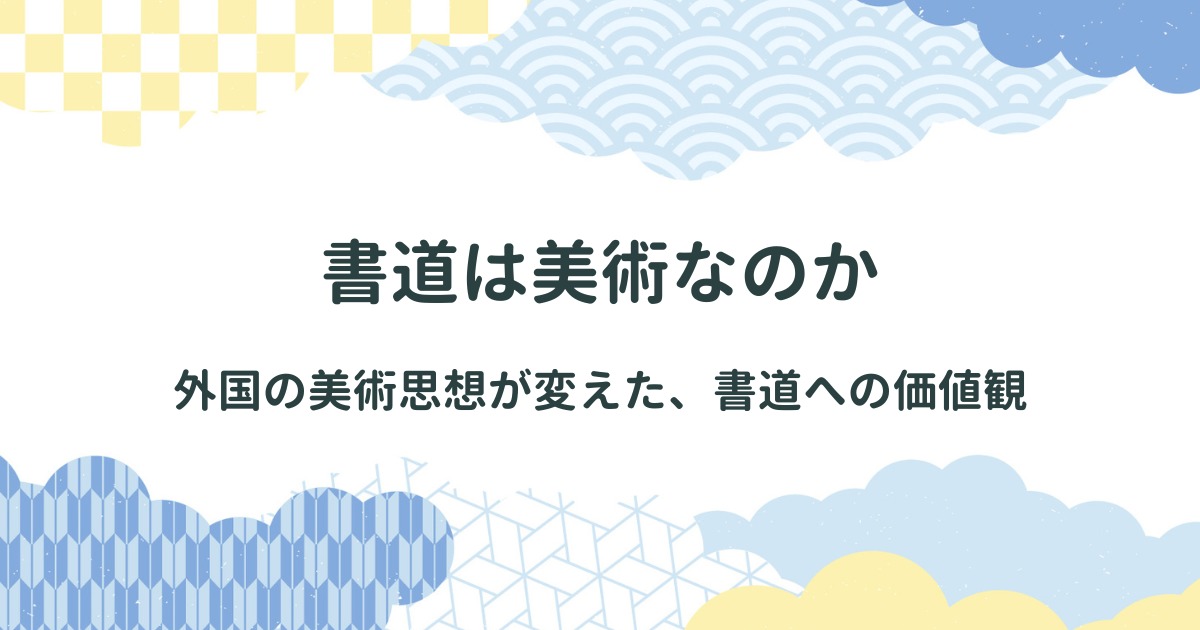書道の作品、なにがよくて、なにがよくないものなのか、よくわからないなと思ったことはありませんか?
公募展作品の審査の場面で、「こっちの方が元気があるよね」とか「こっちの方が行がそろってるよね」などといって、作品の優劣をつけています。
では、書道とは元気な雰囲気を出して、行をそろえて書くことをがんばる競技なのでしょうか?
そうではないはず…ですよね?
昔の評価されている有名な書道家方の作品に「元気がある」「行がそろっている」などという評価基準はありません。「元気がある」「行がそろっている」という評価基準で作品の優劣をつけられるのであれば、昔の書道家の作品はよくない作品ということになってしまいます。
現代の書道作品に対する価値観があいまいになってしまった原因には、近代以降、外国から入ってきた西欧思想、とくに美術思想の影響があると考えられます。
今回は、西欧思想、美術思想に影響された現代の書道観を紹介していきます。
そしてまた、本来書道とはどうあるべきなのかも考えます。

書道をはじめるなら、オンラインという選択肢も!
SHODO FAMなら、あなたのペースで、いつでもどこでも書の学びを深められます。

書き方動画を見ながら練習して、書いた作品はスマホで撮って提出するだけ。
添削・サポートつきだから、ひとりでも安心して続けられます。
\6月30日まで!7日間無料キャンペーン/
書道とはなにか、をはじめて考えることとなった「書道は美術なのか」論争を紹介
書道とはなにか、についてはじめて考えることとなった「書道は美術なのか」論争を紹介します。
明治時代は、日本がいままでにない西欧の近代文明を吸収していく若々しい時代でした。
明治15年、洋画家:小山正太郎と、東京美術学校、現在の東京芸術大学をつくった美術政策家:岡倉天心との間で、書道は美術なのか、そうでないのか、という議論が『東洋学芸雑誌』のなかで取り上げられました。
論争の仕掛人は、書道が美術として勧業博覧会に出品されるなんてとんでもないと考える小山正太郎です。書道とは基本的に言葉が書かれることによって生まれるものであって、言葉を書きつけたものにすぎないと割り切って考えました。
「書道作品に感動するというけれども、実は書かれた語句に感動しているだけのことではないか。東洋の文字も西洋の文字も文字に変わりはないので、東洋にだけ書道があるというのはおかしい。西洋の文字が美術でないのだから、東洋の文字も美術ではない」としたのです。
この意見に対して、岡倉天心は反論しました。
「東洋の書道は文字の大小、配列、形を工夫するのだから、美術として取り扱っても良いのではないか」
という意見でした。
当時、小山正太郎は26歳、岡倉天心は21歳でした。
当時の書道家は、この論争を知っていたのかどうかは分かりませんが、書道家にしてみれは、「書道は書道である」という以外に、美術であろうとそうでないとしても、そんなことはどちらでもよかったのでした。それよりも良い作品を書いて、良い作品を楽しめればそれでよかったのです。
しかし、この書道は美術なのか論争は、「書道とはなにか」がはじめて問われたという点で重大な意味を持つのです。それにもかかわらず、小山正太郎の「書道は文字」という意見も、岡倉天心の「書道は美術」という意見も、つい最近までは理論的に考察されることはありませんでした。
書道をする書道家が、「書道は書道である」という感覚にまったく疑問を持たずに固執して、そのなかで、書道作品に感動するとか、書道に愛着を感じるというのはどういうことなのかを明らかにすればよかったのですが、実際にはそのような取りくみは行われませんでした。
書道の美の理論をしっかりと打ち立てる余裕もないまま、外国からやってきた西欧思想、とくに美術思想に揺さぶりをかけられた結果、あいまいで本来の書道とは違った書道観、書道に関する意見が形成され、一般大衆にまで広まってしまったのでした。
つづいて、外国からやってきた西欧思想、美術思想に影響された現代の書道観を紹介していきます↓
書道はどのようなものと考えられてきたのか
近代以降、言葉を書いただけの紙がなぜ美しいと感じるのかを、いろいろな人が解明しようと試みてきました。それらを大きく分けると、
- 書道は文字の美的工夫
- 書道は文字の美術
- 書道は線の美
- 書道は人なり
の4つに整理されます。
それぞれ紹介していきます。
書道は文字の美的工夫
「文字の美的工夫」とは、1つ1つの画をどの方向にどれくらの力で引いて、どのような大きさのどのような形に仕上げ、字の並び、配列、配置を工夫することが書道だ、という意見です。
「は」の1画目を長く書くか短く書くか、3画目を長く書くか短く書くかといふのが芸術になるので、…
やはり同じ「お」の字を書いた。同じだといっても重ねてごらんなさい、1つの線の間隔はちがふ。「お」の字が2つ並んでも単調にならないやうにするというふのは芸術がするのです。
会津八一「東洋文芸雑考」
会津八一のこの言葉は、「美的工夫」論の代表例です。
また、「書道は美術なのか」論争で紹介した、岡倉天心が唱えた「造形的に工夫するところがあるから書道も芸術だ」という意見もおなじ「美的工夫」論です。
作品を制作する際に、「文字の美的工夫」が書道である、という考えは、多くの人に対して書道というのはそういうものだろうと納得させる主張であり、現在もっとも広く信じられているものではないでしょうか。
では、構成をいろいろ考えて書きあげた個性的な作品が「美」なのでしょうか。
個性的な字が「美」なのか
「大」という字の右上に点をつければ「犬」、下に点をつければ「太」というように、文字には、歴史的、社会的な約束である字形のきまりがあります。私たちは、このきまりにしたがって文字を書きます。
点がついていないのに「犬」とは読めません。きまりを無視して書いてしまえば、もはや文字、つまり言葉をかきとどめたとは言えません。
そのとき、ある人は「犬」の点を遠くに書き、またある人は「犬」の横画を長めに書くとします。このように、実際の書いた文字にある人それぞれの特徴に書道の美がある、という考えるのです。
しかし、この人それぞれの特徴がそのまま「美」である、と言えるのでしょうか。言えないと思います。もしそうだとしたら、癖の強い字ほど美しい字だということになってしまうからです。
書道家の個性的な作品は「美」なのでしょうか?
書道教室に通う人は、「手癖」という人それぞれの特徴を小さくしたい、または歴史的・社会的な基準に改善したいと考えて通います。
一方、書道展に出品するような書道家は、あるがままの自分だけの特徴を活かしてゆがんだ文字の作品を作ります。
つまり、悪筆に悩むひとは自分の特徴を小さくしたくて、書道家は特徴を大きくしたいのです。
戦後・現代の書道家は、この「書道は美的工夫」論をよりどころに、画の長さ、傾きなどを工夫し、数々のゆがんだ文字からなる作品を制作してきました。ゆがんだ文字は戦後書道の基本作法となっています。
書道展をひらく作家や詩人は、あるがままの自分だけの特徴を尊びます。
それぞれの特徴を、個性と呼べば、書道は個性の美ということになります。
現代の書道家は、意図的に癖のある字の作品を書きますが、それが「美」であるとは限らないのではないでしょうか。
書道は文字の美術
上の「美的工夫」論をさらにおしすすめていくと、「書道は文字の美術」論に行きつきます。
「書道は造形芸術、美術の1ジャンルである」という意見です。
書は造形芸術(美術)の1ジャンルである。文字を書くことを場所として成立した独特の芸術である。
文学が、文学とその意味内容との緊張関係に、重心を置く言語性の芸術であるに対して、書はむしろ文学とその視覚形象との緊張関係に重心を置く視覚性の芸術なのである。
井島勉『書の美学と書教育』
西洋美学者:井島勉によるこの明確な位置づけは、戦後の前衛書道家をはげまし、戦後前衛書道の思想となり、また、いわゆる伝統的な書道家も含めて、現在の書道界はこの理論の上に作品を制作しています。
これは書道を「文字の規範+人それぞれの特徴」と考える「文字の美的工夫」論に立っています。正確には、「美的工夫」論ではあいまいになっていた部分をきっぱり脱ぎ捨てたのが、「文字の美術」論です。
しかし、はたして書道は、「文字を書くことを場所として成立した美術」、言いかえれば、点画の長さを長くしたり短くしたりして文字の形を歪ませるものなのでしょうか。
絵画には抽象画というジャンルがありますが、そもそものルーツが違うため一緒にしてはいけません。書道はもともと実用的なものです。文字を記号として扱うのではなく、言葉として扱うべきなのです。
書道は線の美
書道は「文字の美的工夫」「文字の美術」論と並んで、もう1つ書道家たちが唱えるのがあります。それは、書道は「線の美」であるという論です。
現在の書道家の方々のほとんどが、書道とは「美的工夫」+「線の美」または、「文字の美術」+「線の美」であると考えています。
「線の美」とは、文字は点画を組み立てていくことで作られます。出来上がった字形よりも、文字を作りあげているその点画を「線」と呼んで、その点画のほうに焦点を向けたのが、「書道は線の美」論です。
この「書道は線の美」が歴史上いつごろから唱えられているのか、正確にはわかりませんが、明治45年に、書道家・諸井春畦が著した『書法三角論』のなかに、すでに次のような記述があります。
乃ち、形体の良否は、配線の美、即ち間架・均斉・疎密・円暢・俯仰・向背・陰陽・相応等美的観念を基礎とするものにして、一点一画の微に至るまで整然として形式美を発揮せしむるに足る。
書によりて、吾人に快感を与ふるものは、画そのものが配色にのみよりて、其の美を論ずるにあらざるが如く、又唯々形象のみを主とするにもあらざるが如く、其の妙一枝の筆、能く線の美を発揮するにあればなり。
諸井春畦『書法三角論』
明治45年にすでに「配線の美」「線の美」という記述がありますが、「線の美」論を決定的にしたのは昭和、つまり現代に入ってからです。
書道家・比田井天来の弟子・鮫島看山は、はっきりと次のように宣言しました。
一、凡そ書の内容は何であるか、書は何を表現せんとするのであるか、文字であるか、文字ではない。文字は単なる素材である。それなら文学的ボエジーや道徳的フモールであるか、両者でもない。此等の従属物であるならむしろ文学的制作や倫理的実践に譲った方が賢明である。古人が「書は散也懐抱を散ずる也」と云ったのは心理である。即ち懐抱即ち主観が書の内容をなすのである。詳しく言ふならば書は文学と云ふ素材を借りて作者の主張を表現するところの線の芸術である。
鮫島看山「作書理法覚書」
今の書道家に、「書道の美とは何ですか」と聞いてみたら、きっと「線の美」についての回答があるでしょう。
「書道は線の美」という意見は、西欧の絵画理論に幻惑されたことによって生まれた意見です。文字の点画を「線」とし、絵画の描写上の「線」とを同じように扱うことによって、書道を絵画のように華々しい舞台に立たせたいという願望によって「線の美」論が誕生しました。そのため、「書道は線の美」という意見は、「書道は文字の美術」論と車の両輪のような関係にあります。
前衛書道の営みを否定はしません。近代以降の書道の歩みからいって必然的な流れでしょう。
しかし、こういった西欧思想によって本来の書道から踏みはずしが行われたことだけは、見落とすべきではないと思うのです。
書道は人なり
「書道は人なり」、または「書道は人格を表す」とか「書道は人柄を表す」という言葉があります。
書道は、文字の上にそれを書いた人の精神・感情・肉体が現れている。文字からその人の人柄が伝わってくる。というものです。
書の本質は云ふまでもなく文字の上に人間の生命の躍動を率直簡潔に表現されたものであって、その筆者の精神・感情・肉体を合してその真面目を現はして居るものであります。
上田桑鳩『臨書研究 上』
書は単に文字であるのではなくて、いのちの世界の表れ出たかたちであります。いのちの世界、意識のかなたで自己決定した深い意味での生き方、その生き方が生み出したかたちが書であります。書は生き方のかたちである、…
森田子龍『書ー生き方のかたち』
書は人なりで、書でもって人柄がよくわかるが、私はさらに書は体格なりで、書でもって体格さえ察せられるようにおもっている。
福本和夫『書味真髄』
これに対して私は、ちょっと嫌味になりますが、とくに書道に限らず文学も絵画も、それよりなにより日常の行動そのものから性格は表れます。
「書道は人なり」という意見は、「人なり」が表現や美をもたらす源泉であるにしても、「文は人なり」「絵画は人なり」ともいろいろなものに言いかえられるように、書道に固有の美が成立する構造や特性について、なにも解明したことにはなりません。
とはいえ、書道については、とくにそう言ってみたい誘惑にかられる気持ちもわかります。
「書道は人なり」という以上、作品と作者との関係を解明しなければなりません。その作品のどういった点が作者のどんな性格とリンクしているのか、理論的に説明する必要があります。
まとめ:書道は本来「造形芸術」ではない
ここまで「美的工夫=美術論」「線の美」「書道は人格論」の4つの書道観を紹介してきました。
しかし、これら従来の書道観はすべて西欧思想に影響された、本来の書道観とは少しずれた価値観ではないかと考えられます。
その原因は、「文字」には言葉と造形の二側面があり、言葉の側面は文学、造形の側面が書道であると、単純に二分法で解明しようとした点にあります。書道を「文字を書く」ことだと考え、さらにその「文字」を線からなる図形と考えたのです。
現代の書道家が作品制作の際にいろいろと構成を考えるとき、文字は単なる図形と割り切っています。文字を図形と考えることによって、図形とそれを構成する線に注目するようになります。
書道家が、文字は単なる図形ととらえようとも、文字は言葉の筆跡であって、決して図形ではありません。
「書道は美術なのか」論争で小山正太郎が唱えたように、アルファベットも日本の漢字かな交じり文も、ペンで書くか、筆で書くかの違いはあるにしても、本質的なところではなんら変わりのない「筆跡」「書字跡」です。
文字というのは、決して「図形」ではありません。文字と呼ばれているものは、言葉の書かれた跡、また言葉そのものです。筆跡とはかかれた言葉の跡、言葉のかたまりです。ここが書道を理解する出発点です。
「言葉を書く」ことから出発するべきものを、「文字を書く」というありもしないところから出発してしまったところに、誤りの原因があるのです。
次回:書道とはなにかを解明する
今回は、明治15年の小山正太郎の「書道は文字」論、岡倉天心の「書道は美的工夫」論の立場からの「書道は美術なのか」論争を紹介し、現在、一般に書道の美とはどのようなものと理解されているのかを「書道は美的工夫」論、「書道は文字の美術」論、「書道は線の美」論、「書道は人なり」論の4つに整理し、紹介しました。
そのどれもが、書道の一断面をいい当ててはいるものの、決して書道の美が感じられるしくみに踏み込めきれていません。
それは、書道を「文字を書く」という実際にはありえない出発点から解明しようとしたからで、書道を解明するためには「言葉を書く」という出発点から考察し直す必要があります。
そこで、次の記事では、書道を言葉を書きとどめた筆跡、書字跡、肉筆であるという出発点から、書道とはなにかを解明しようと思います。

忙しい毎日に、心を整える書道の時間
まずは少しの「書にふれる時間」を。
通わなくていい教室・オンライン書道講座で、
おうちでゆっくり書く時間を楽しみませんか?
静かな集中と、美しい文字を手に入れるチャンス!

\6月30日まで!7日間無料キャンペーン/
参考文献:石川九楊『書とはどういう藝術か』