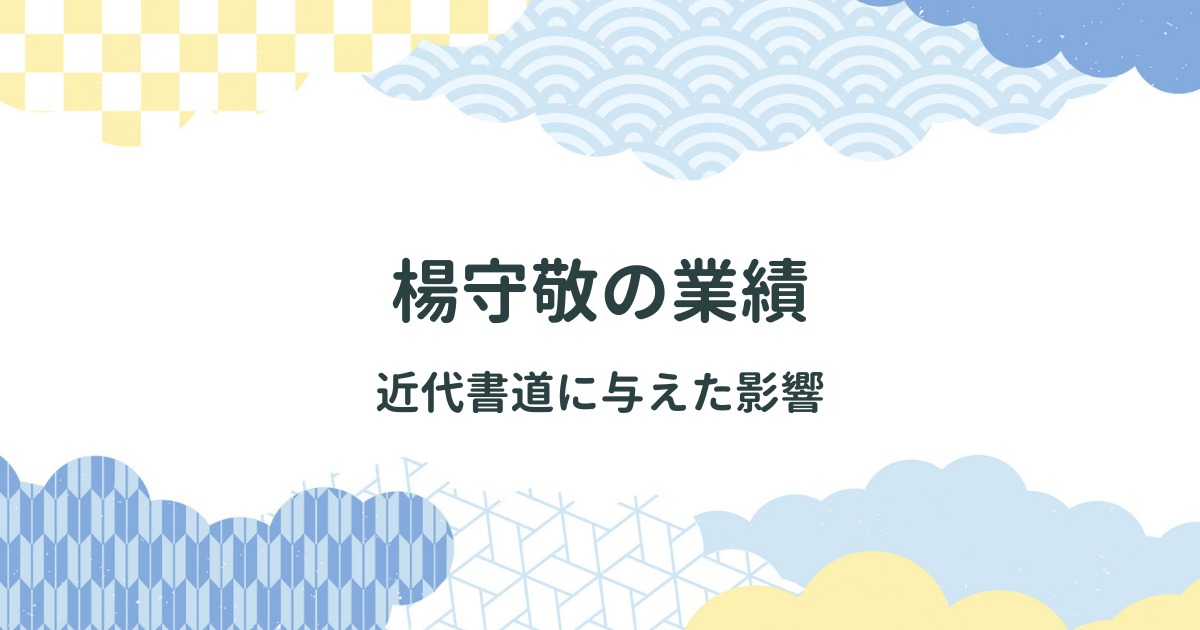楊守敬は、清国(中国)の人で、明治のはじめに日本へやってきます。
彼が持ってきた碑版法帖の影響によって、明治以前までは肉筆で書かれた文字を習うのが主流だった書道界に、碑に刻された北魏の書風を習うブームをもたらします。
今回は、楊守敬がどのような経緯で来日し、近代書道界にどのような影響を与えたのかについて書いていきます。
書道をはじめるなら、オンラインという選択肢も!
SHODO FAMなら、あなたのペースで、いつでもどこでも書の学びを深められます。

書き方動画を見ながら練習して、書いた作品はスマホで撮って提出するだけ。
添削・サポートつきだから、ひとりでも安心して続けられます。
\6月30日まで!7日間無料キャンペーン/
楊守敬の来日
明治4年(1871)、日本と清国との間に日清修好条規が締結されます。
そして、同10年(1877)11月30日欽差大臣何如璋をはじめとする清国公使の一行40名は、軍艦海安号に乗船して長崎に到着、神戸港などを経由して、12月16日、横浜港に入港しました。
さらに、同月24日、一行は外務省に外務卿寺島宗則を訪れ着任の挨拶をし、12月25日付の通達により何如璋は正式に日本政府より清国全権公使として認可されました。
明治13年(1880)4月、何如璋の招きということで、楊守敬(1839~1915)が来日しました。
楊守敬は著『水経注疏』に代表されるように水の流れを研究する地理学者でしたが、書法および金石学にも詳しく、当時は42歳の若さながら、『望堂金石』『楷法遡源』『平碑記』『平帖記』などの著述をすでに成し遂げていました。
日本書道における楊守敬の影響
楊守敬が来日すると、彼が中国一流の金石学者であり書家であることを聞き、いち早く交流を求めたのが、日下部鳴鶴(1838~1922)、巖谷一六(1834~1905)、松田雪柯(1823~81)の3人でした。彼らが公使館を訪れると、室内に楊守敬が携行していた拓本が、所狭しと広げられていました。
日本は長く鎖国をしていたため、中国の書物はわずかに長崎の出島から入るのみで、江戸時代では元の趙孟頫、明の文徴明、董其昌がもっぱら唐様として学ばれて、中国書法に対する理解には大きな停滞がありました。
楊守敬が漢魏六朝の拓本を示しながら、北朝書法の正統性を論じる実証てきな方法はとても斬新で、大きな関心を与えました。
松田雪柯は伊勢の宮司で、すぐにや命で亡くなってしまいますが、日下部鳴鶴は鶴門と呼ばれ、全国に1000人余りの弟子も持つ書道界の総師であり、巖谷一六はに携わる朝廷の要人だったので、二家は北魏書法を踏まえた新体の教本を競って出版し、世にいわゆる六朝ブームを巻き起こしました。そして、やがて日本の近代書法の始まりとして位置づけられるようになりました。
楊守敬を通じて鳴鶴たちが購入した拓本は、実に1万枚を超えたとされています。結果的にブームとなりましたが、これほど多くの拓本を購入させた楊守敬の商売の才能にうまく乗せられたという考え方もできます。
日本で古典籍を収集する楊守敬
明治時代の初期、仏教信仰の強制を廃止します。
やがて寺院、仏具、経文などの破壊運動がおこり、寺院が所蔵していた日本・中国の古い書物の価値が暴落します。
楊守敬はこれらを収集し、明治17年(1884)に帰国する際に、膨大な量の書物を搬送し、これによって彼は一気にすぐれた蔵書家となりました。