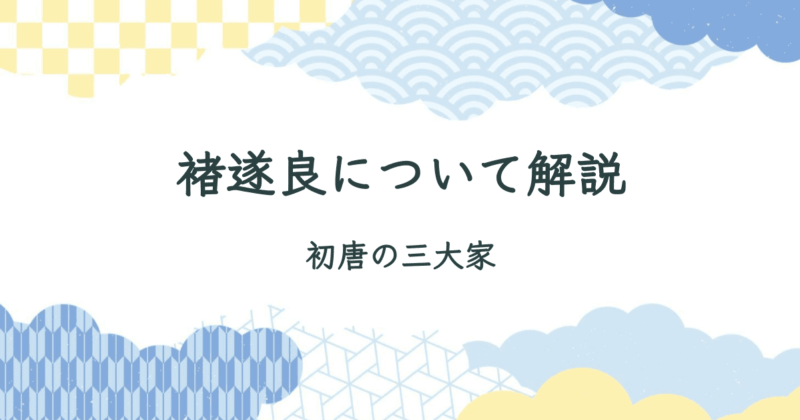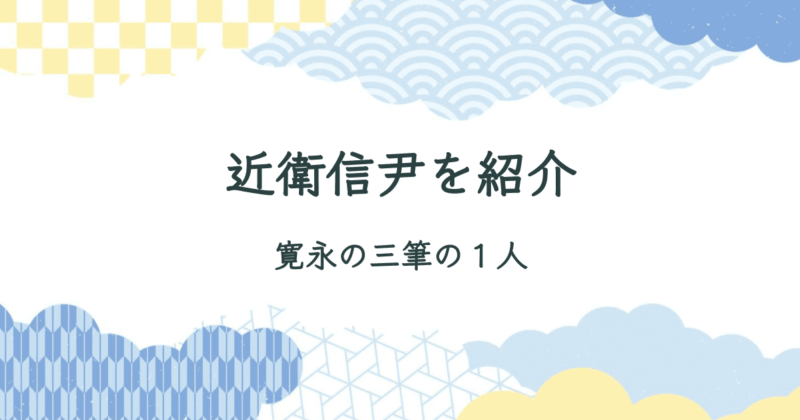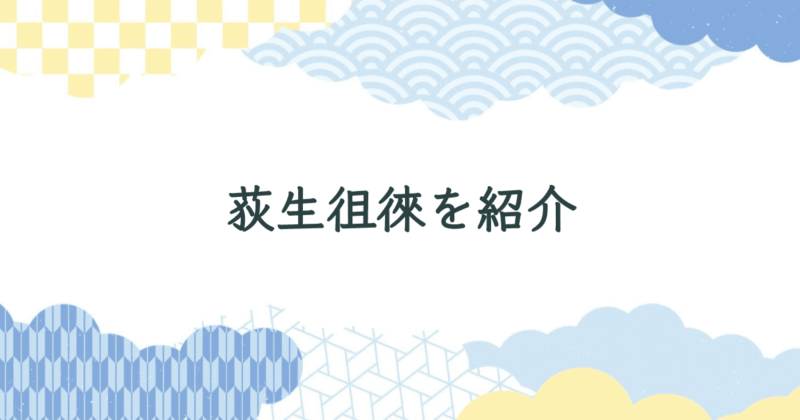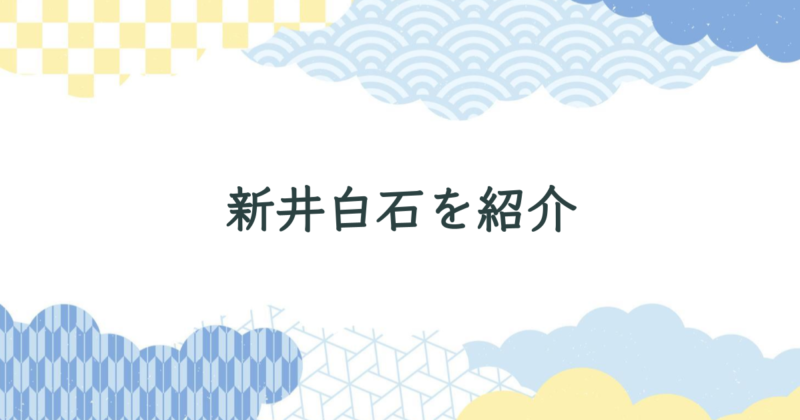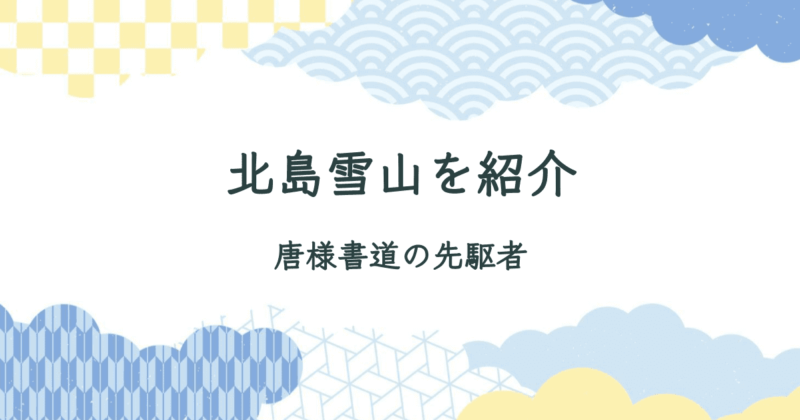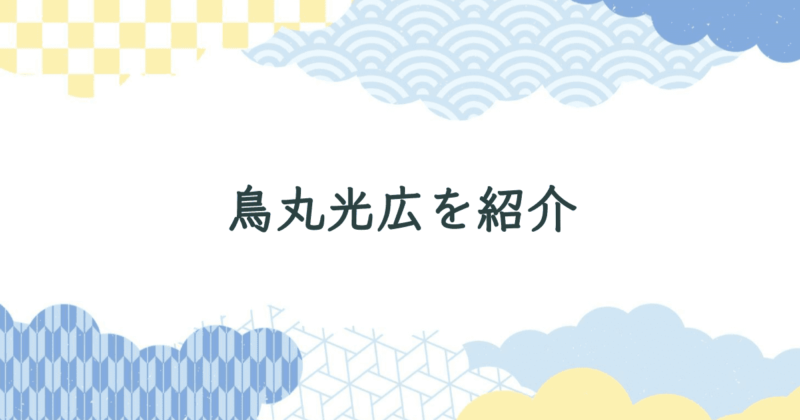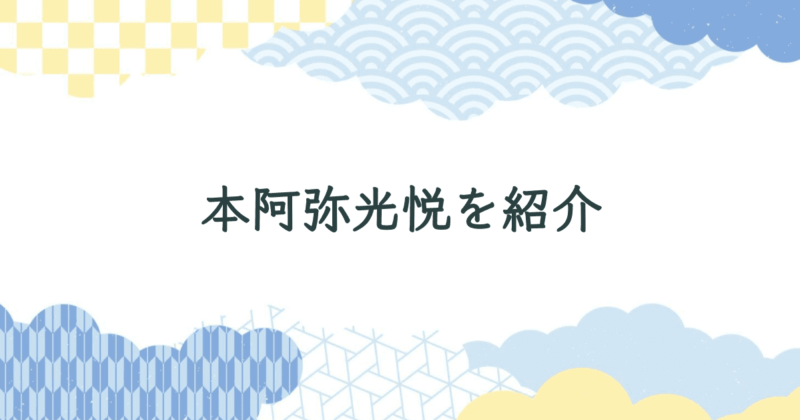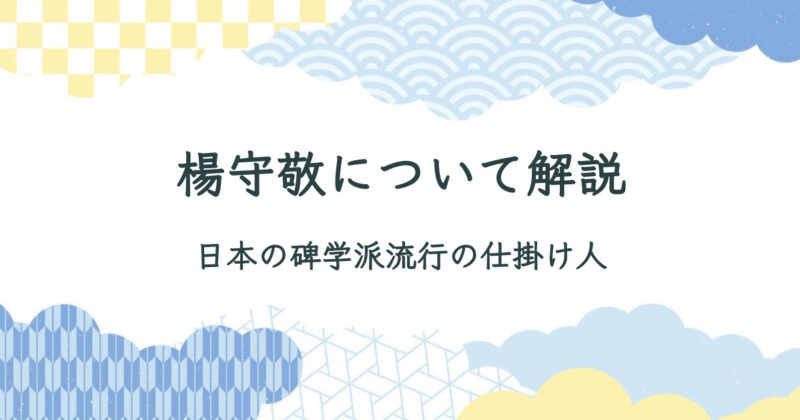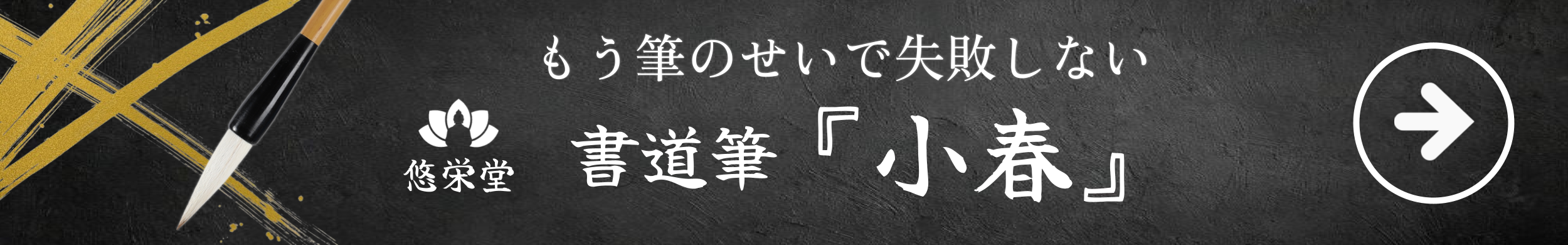書家– category –
-

褚遂良(ちょすいりょう)について解説/代表作品も紹介
【褚遂良について解説】 褚遂良像 雁塔聖教序という人物です。 褚遂良」と呼ばれています。 彼は唐)で生まれました。 中国における書道の名手は、同時にその時代を動かしてきた政治家や学者でもありますが、褚遂良も例外ではなく、唐の建国期を支えた重臣... -

近衛信尹(このえのぶただ)を紹介/能書としての活躍【寛永の三筆】
【近衛信尹(このえのぶただ)を紹介】 近衛信尹筆:三十六歌仙帖1 近衛信尹に変えました。 性格は血の気の多い性格だったようで、摂関」が起こると、自ら軍に入ることを希望しました。(しかし許可は下りなかった) 書道家としては、本阿弥光悦と呼ばれ... -

荻生徂徠(おぎゅうそらい)を紹介:書家としての活躍
【荻生徂徠(おぎゅうそらい)を紹介】 川原慶賀筆:荻生徂徠肖像 荻生徂徠は、江戸時代中期の儒学者、思想家、文献学者です。 生没は1666年~1728(寛文6年~享保13年)。徳川綱吉の侍医方庵の子。江戸の生まれ。名前は双松です。 1679年(延宝7年)14... -

新井白石(あらいはくせき)を紹介
【新井白石(あらいはくせき)を紹介】 新井白石肖像画 生没は1657年~1725(明暦です。 幼少のころから聡明で、若年のころから学問を修めました。 1686年(貞享の門に入り、やがて「木門の十哲」のひとりに数えられました。 1693年(元禄6年)順庵(将軍... -

北島雪山(きたじませつざん)を紹介
【北島雪山(きたじませつざん)を紹介】 細井広沢『紫薇字様』雪山肖像画 北島雪山(きたじませつざん)は江戸時代前期に活躍した書道家で、日本において唐様(中国風)の書風の基礎を築いたことで注目されます。 生没は江戸時代の1636~1697(寛永です。... -

松花堂昭乗(しょうかどうしょうじょう)を紹介
【松花堂昭乗(しょうかどうしょうじょう)を紹介】 松花堂昭乗作:三十六歌仙帖 松花堂昭乗(しょうかどうしょうじょう)は、江戸時代に活躍した書道家、画家で、特に書道においては「寛永」の1人として数えられ、江戸時代を代表する書道家です。 1584~... -

鳥丸光広(からすまるみつひろ)を紹介
【鳥丸光広(からすまるみつひろ)を紹介】 鳥丸光広作:聚楽第行幸和歌巻 晩年の烏丸光広が、和歌を揮毫(きごう)したもの。筆運びに彼独自のリズム感を発揮しており、奔放かつ自在な筆致が見どころの1つ。 鳥丸光広(からすまるみつひろ)天正7年~寛... -

本阿弥光悦(ほんあみこうえつ)を紹介
【本阿弥光悦(ほんあみこうえつ)を紹介】 本阿弥光悦 本阿弥光悦(ほんあみこうえつ)は、書・陶芸・漆芸・能楽・茶の湯などに携り、後世の日本文化に大きな影響を与えた人物として有名です。 永禄元年~寛永14年(1558~1637)光二の子。京都の生まれ。... -

池大雅(いけのたいが)を紹介
【池大雅(いけのたいが)について紹介】 福原五岳筆 池大雅像 ※Wikipediaより 池大雅(いけのだいが)、江戸時代に活躍した文人画家 、書道家です。享保8年~安永5年(1723~1776)、姓は池野、名は無名、大雅は雅号です。 幼少のころから聡明で... -

楊守敬(ようしゅけい)について解説/作品も紹介【中国清時代の書道家】
日本では明治の書道が流行し始め、篆書や隷書の作品が盛んに書かれるようになりました。 これは、中国からやってきた楊守敬という人物が日本にたくさんの碑版法帖を持ち込んだことがきっかけとされています。 今回は、日本に碑学派が流行する仕掛け人とな...