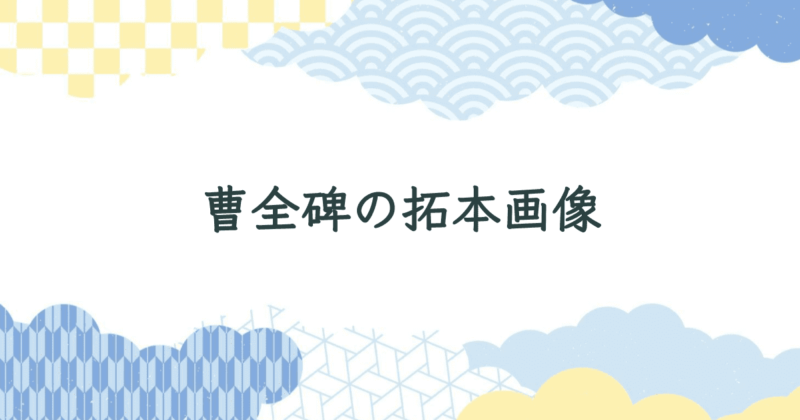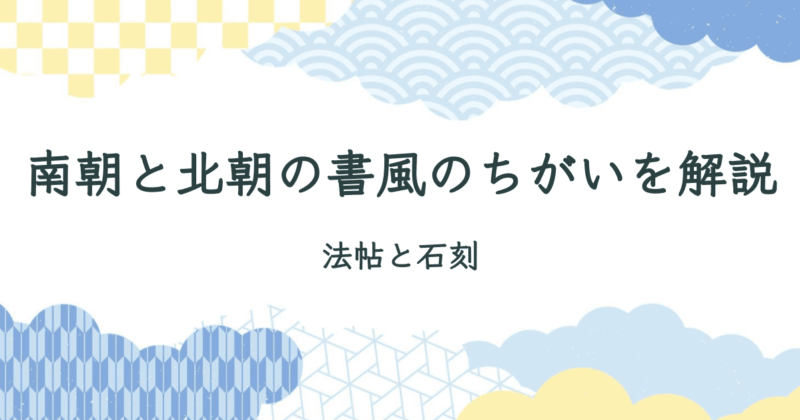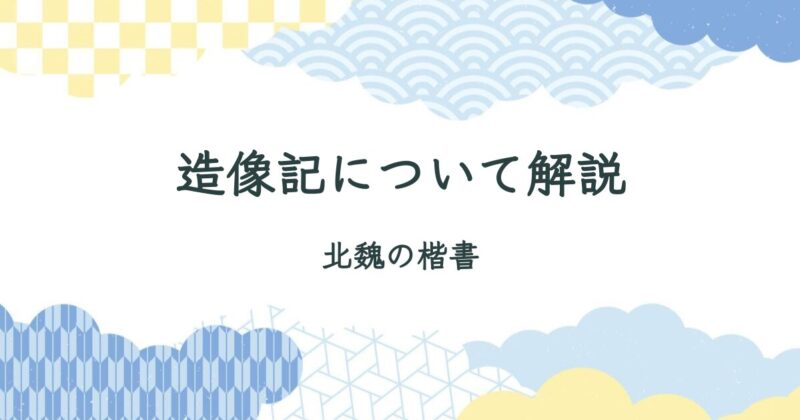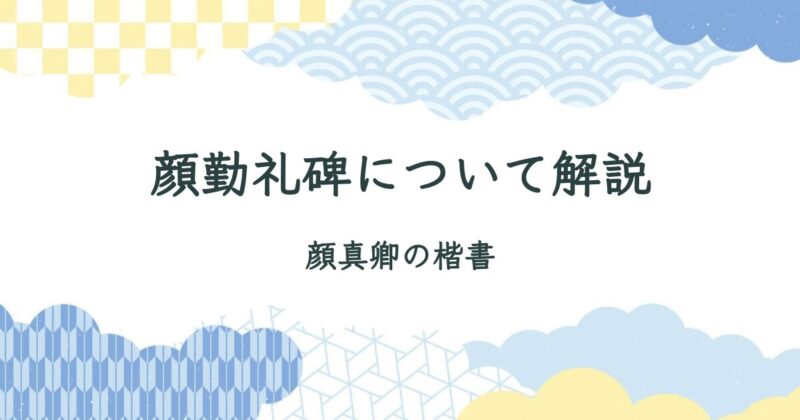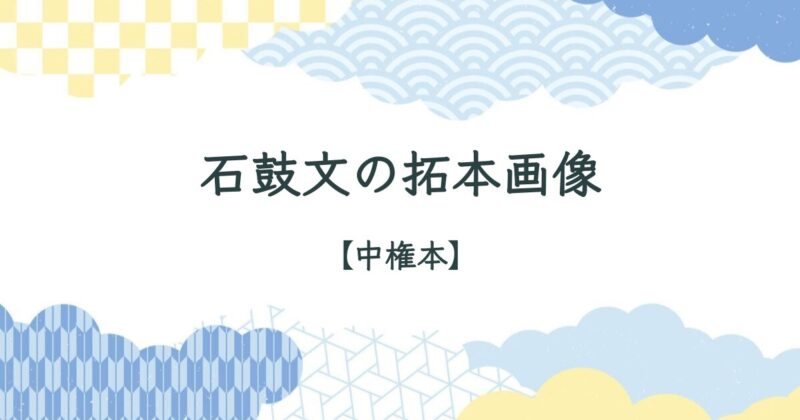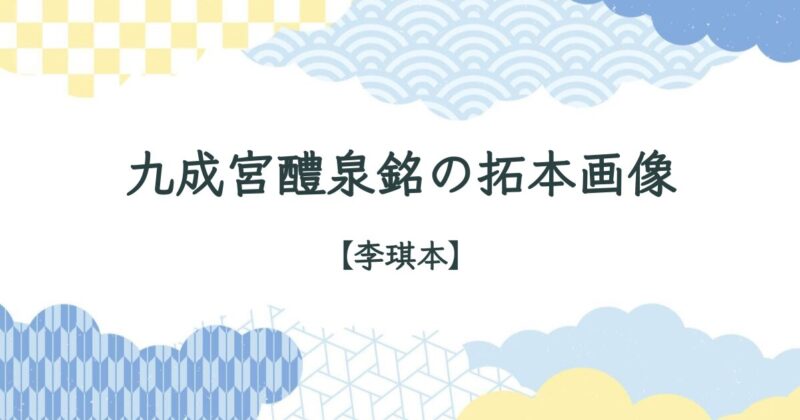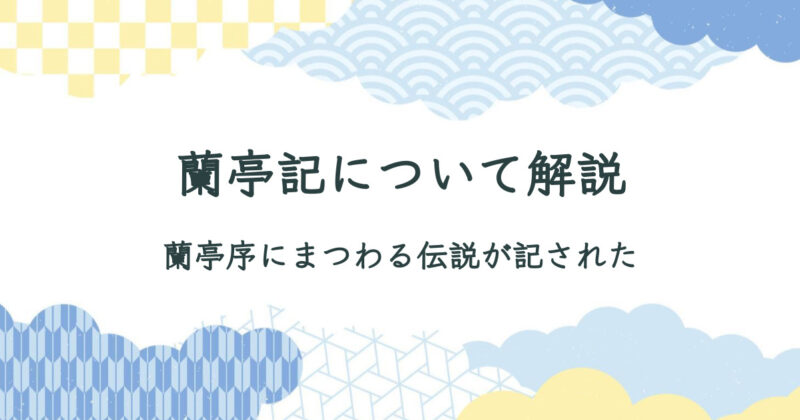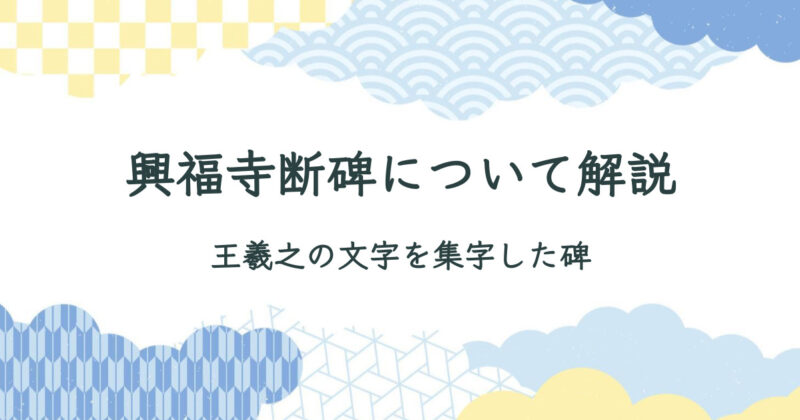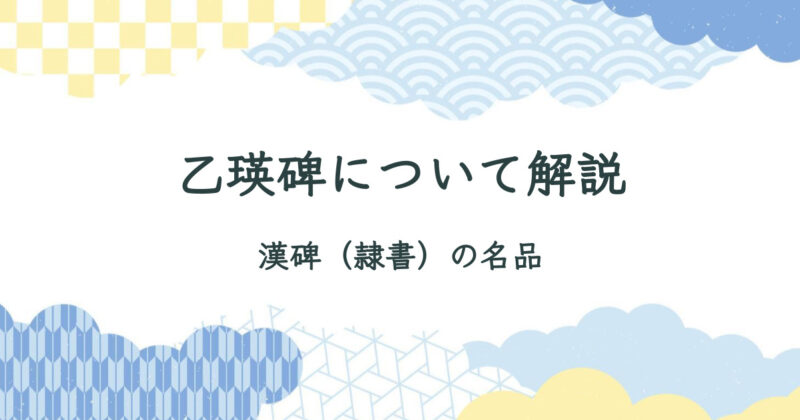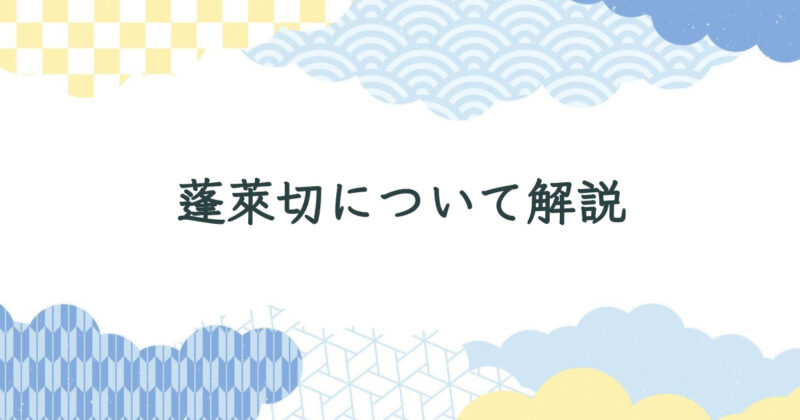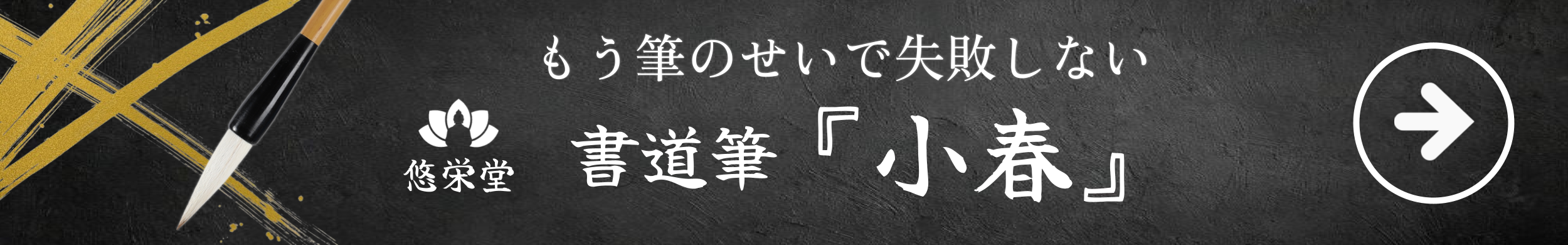法帖– category –
-

曹全碑(そうぜんひ)の臨書作品制作に使える全文拓本画像
この記事では、曹全碑の臨書作品制作に使える全文の拓本画像を紹介します。 曹全碑の内容や書風、書き方については、下の記事でくわしく解説しています。↓ 【曹全碑の拓本画像】 -

南朝・北朝では書風がちがう/南帖と北碑/中国南北朝時代は南と北とで書風が違った
書道において、よく「南朝風の書」といった表現がされることがあります。 この「南朝」と「北朝」の違いとは何でしょうか。解説します。 【南朝と北朝の書風 】 南北朝興亡年表 「南朝風の書」という表現は、中国大陸を南と北で分けたときに、南と北で書... -

【北魏の楷書】龍門造像記について詳しく解説/龍門石窟/龍門二十品
造像記を代表する書跡として慎重されてきました。一画一画をゆるがせにしない筆づかい、質朴古拙さとただよう緊張感に、それらが名品とされた理由も納得させられます。 今回は、造像記のなかでも特に名品として挙げられる「龍門二十品」を紹介します。 【... -

顔勤礼碑について解説【特徴・書き方】【顔真卿の楷書】
顔勤礼碑が書いた楷書の作品です。 本記事では、作者である顔真卿について、その作品顔勤礼碑について、特徴・書き方も紹介します。 【著者・顔真卿について】 伝顔真卿肖像 『歴代聖賢半身像』より 顔真卿に及第しました。 書道に優れた人物で、初唐の中... -

石鼓文(せっこぶん)の臨書に使える全文拓本画像【中権本】
こちらの記事では、石鼓文の拓本画像を紹介しています。 なお、石鼓文について詳しくは以下の記事で紹介しています。↓ 石鼓文#1 石鼓文#2 石鼓文#3 石鼓文#4 石鼓文#5 石鼓文#6 石鼓文#7 石鼓文#8 石鼓文#9 石鼓文#10 石鼓文#11 石鼓文#12 石鼓文#13 石鼓... -

九成宮醴泉銘(きゅうせいきゅうれいせんめい)の全文拓本画像【李琪本】
九成宮醴泉銘【李琪本】#1 ※クリック/タップで拡大 九成宮醴泉銘【李琪本】#2 九成宮醴泉銘【李琪本】#3 九成宮醴泉銘【李琪本】#4 九成宮醴泉銘【李琪本】#5 九成宮醴泉銘【李琪本】#6 九成宮醴泉銘【李琪本】#7 九成宮醴泉銘【李琪本】#8 九成宮醴泉銘... -

蘭亭記(らんていき)を紹介・現代語訳
中国唐(598~649)は、即位時にはまだまだ全国統一にはほど遠かった唐王朝を1代で世界帝国に築き上げていった名君主です。 そんな彼は書道にも関心が強く、特に王羲之がわからず、これを手中に収めることができませんでした。 今回紹介する『蘭亭記』に... -

興福寺断碑について解説【臨書に使える全文拓本画像】
興福寺断碑とともに、彼の書法を解明するうえでもっとも貴重なものの1つです。 興福寺断碑を臨書することで、王羲之の美しい行書に近づくことができるでしょう。 今回は、王羲之の興福寺断碑について解説し、臨書につかえる全文拓本画像も紹介します。 【... -

乙瑛碑(いつえいひ)について解説【書き方・特徴・書風・臨書作品に使える全文拓本画像】
【乙瑛碑(いつえいひ)について解説】 乙瑛碑 整本 東京国立博物館蔵 乙瑛碑時代、153年(元興元年)に建てられた碑です。 場所は、立碑のときからそのまま山東省にあります。現在は孔子廟内の東廡「漢魏碑刻陳列室」(通称「孔廟碑林)に置かれていま... -

蓬萊切(ほうらいぎれ)について解説【作者・読み方】
【蓬萊切(ほうらいぎれ)について解説】 蓬萊切 五島美術館蔵 蓬萊切(切とは断簡のこと)は、『拾遺抄』『拾遺和歌集』から4首、『後撰和歌集』から1首を書写した古筆断簡です。 もともとは巻子本でしたが、昭和9年(1934)1首ずつ5枚に分割されま...