草書– category –
-
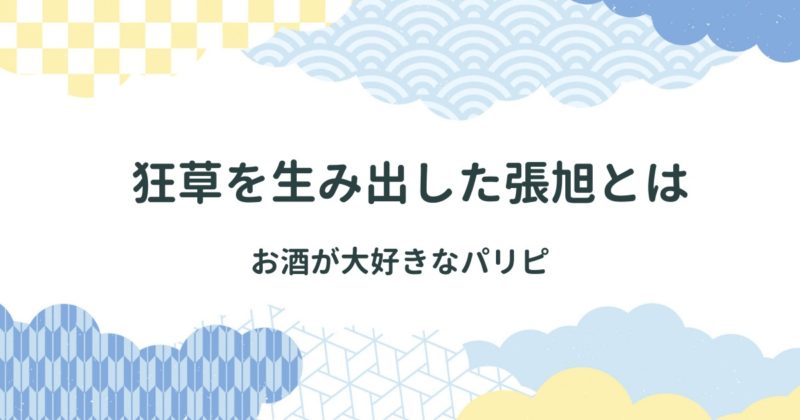
【狂草を作った書家】張旭(ちょうきょく)について詳しく解説・代表作品も紹介
張旭(ちょうきょく)は中国の唐時代(7世紀ごろ)に生きた書家です。 草書の名手として知られ、草書の中でも狂草というジャンルを生み出した人です。 狂草を受け継いだ懐素はそれぞれ、張旭と懐素に対する人物評語です。 今回は、狂草を生み出した張旭と... -
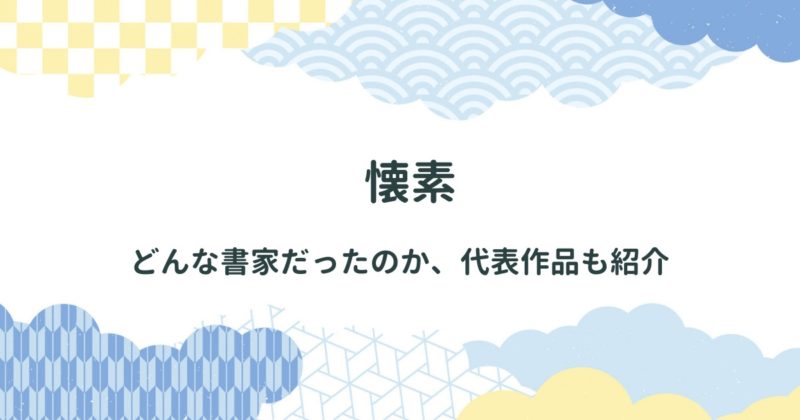
懐素(かいそ)が書いた狂草の書風の特徴、代表作品を紹介
懐素(かいそ)は、中国唐な性格で、酒を飲んでは心のおもむくまま、ところかまわず草書を書き散らしたといいます。 今回は、懐素とはどんな書家なのかを解説した後に、彼の書風の特徴である狂草について、代表作品も紹介していきます。 懐素について解説 ... -
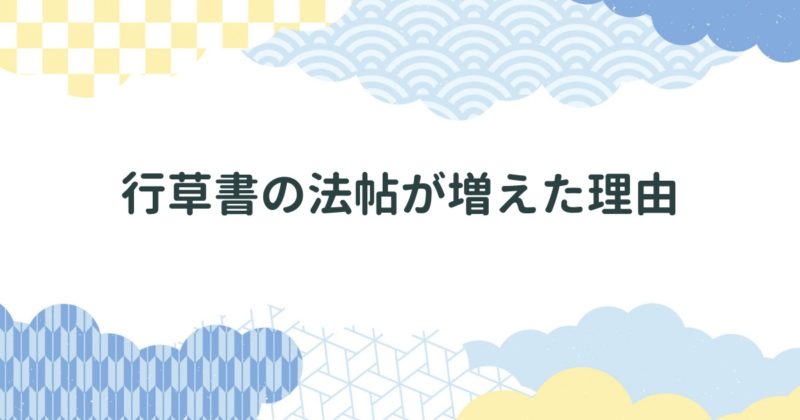
蘇軾・黄庭堅・米芾が代表される宋時代以後、行草書の法帖が増えた理由
欧陽詢が代表される宋時代以降、行草書の法帖が多くなります。 これには唐から宋にかけての文化の変革によるものがあると考えられます。 今回は宋時代以後、行草書が増えた理由について考えていきます。 宋の時代の書は意を取る 明を取り、唐の人の書は技... -
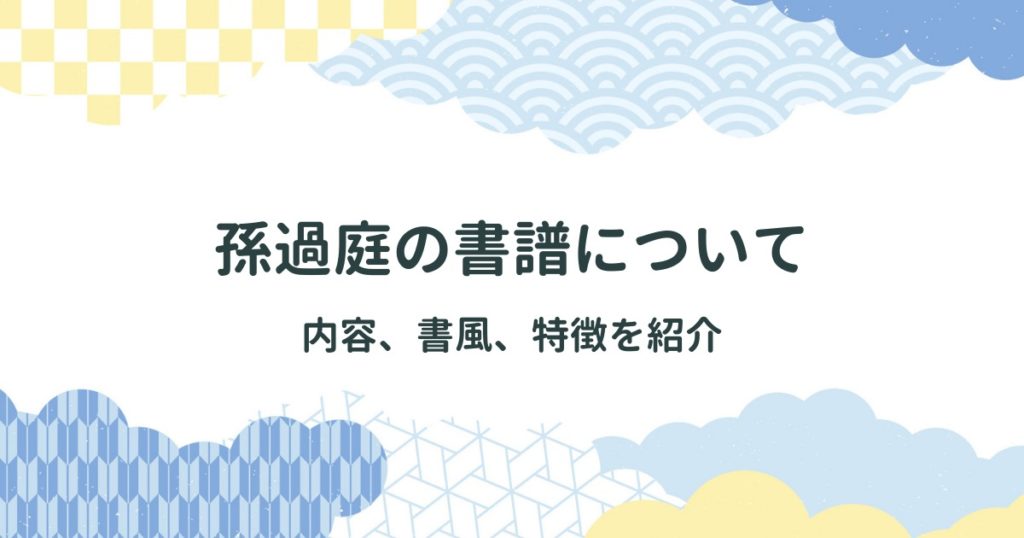
孫過庭の書譜について、内容、書風、特徴を紹介
孫過庭として、高く評価されてきました。 今回は、孫過庭について、書譜の内容、書風、特徴を紹介していきます。 孫過庭について 孫過庭像 孫過庭は、唐時代の書人です。孫過庭本人についての伝記には諸説があり、はっきりとしたことは分かっていません。 ... -
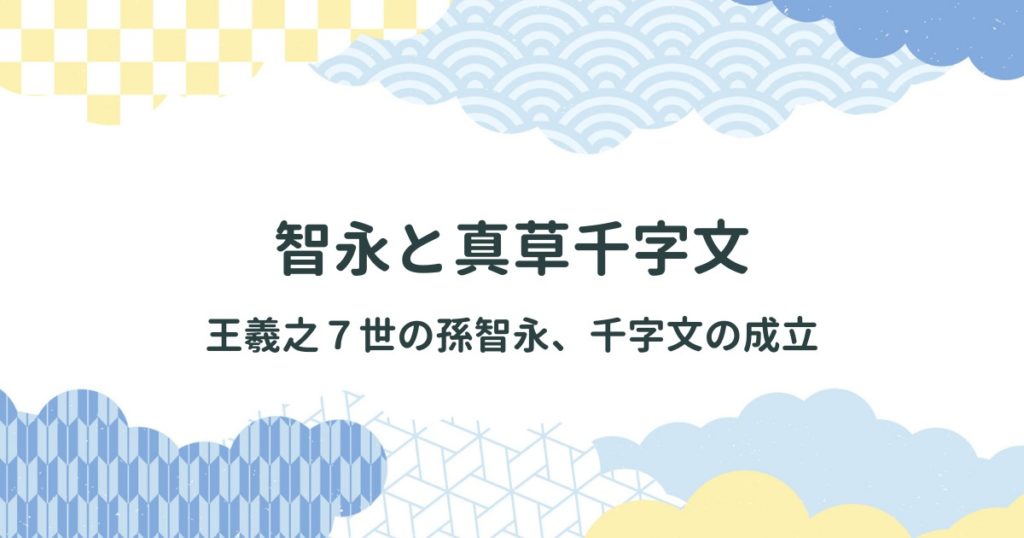
智永の真草千字文:内容や智永の制作意図とは
千字文は、習字帖として古くから中国・日本で活用され親しまれてきました。 今回は、千字文の現存最古の古典である王羲之7世の孫、智永の「真草千字文」について紹介していきます。 智永について 智永の住職となり、積年書を学び、彼の書を求めるものが多... -
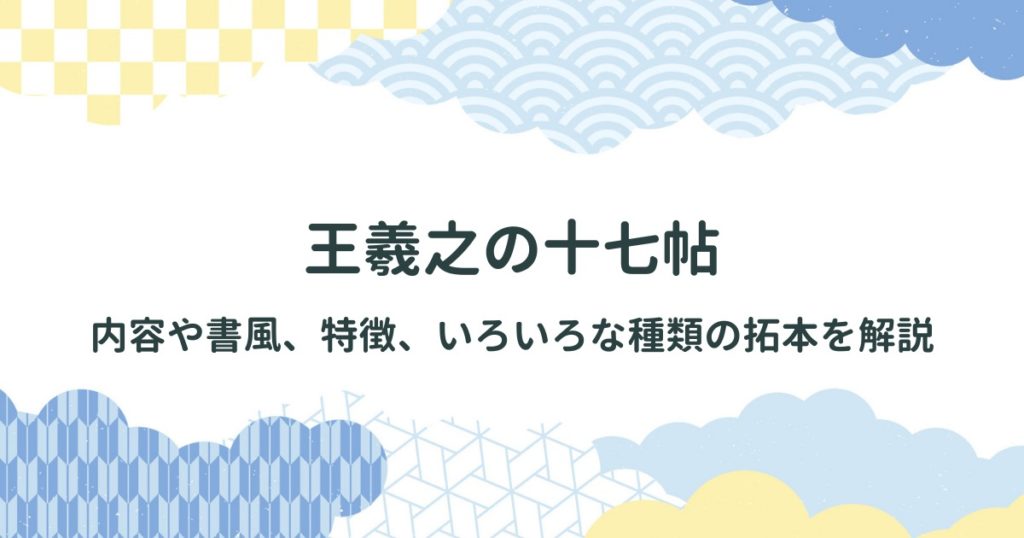
王羲之の十七帖について、内容や書風、特徴、いろいろな種類の拓本を解説
十七帖は草書を習得するため古来より草書の典型とされ、多くの人に尊重されてきました。 今回は、十七帖について、内容や書風、特徴、いろいろな十七帖の拓本を解説していきます。 十七帖について 十七帖(じゅうしちじょう)は、王羲之の手紙29通を集めて... -
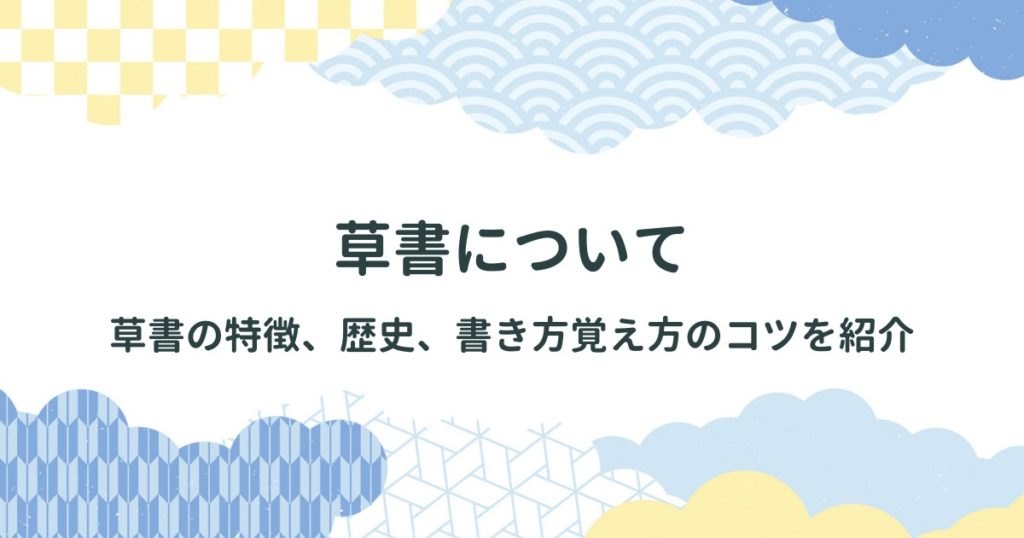
書道の作品制作で役立てたい草書の特徴、歴史、書き方覚え方のコツを紹介
草書は日常生活でほとんど使いませんし、楷書と形がかけ離れているため使いづらいですよね。 書道をやっている人は草書で書かれた作品を制作するときや鑑賞するときに何の字を書いているのか、その字のどの部分を書いているのかを理解しておくのは重要なこ...
1

