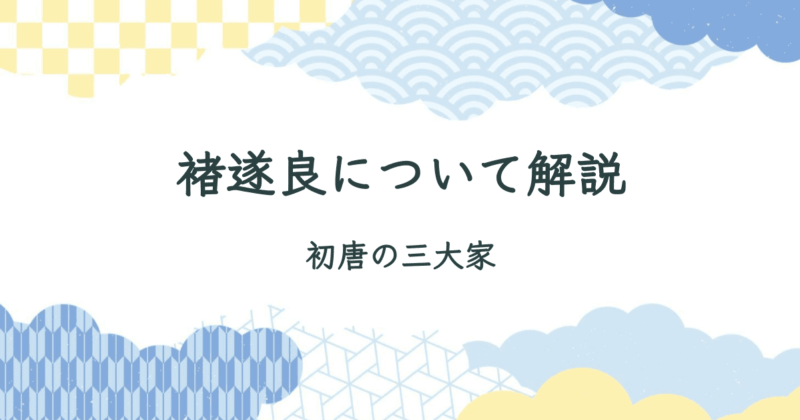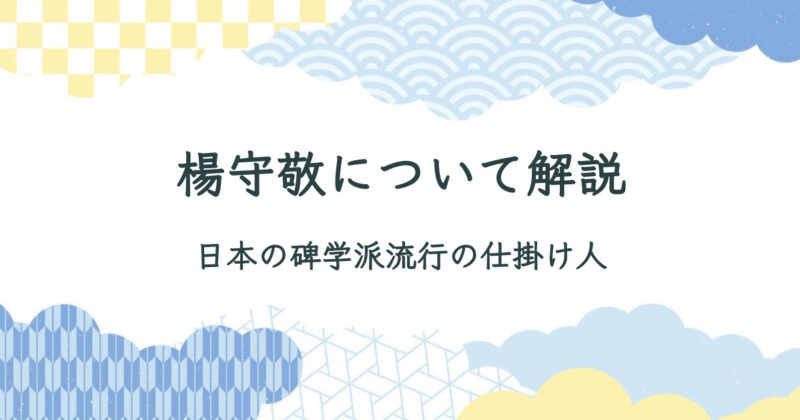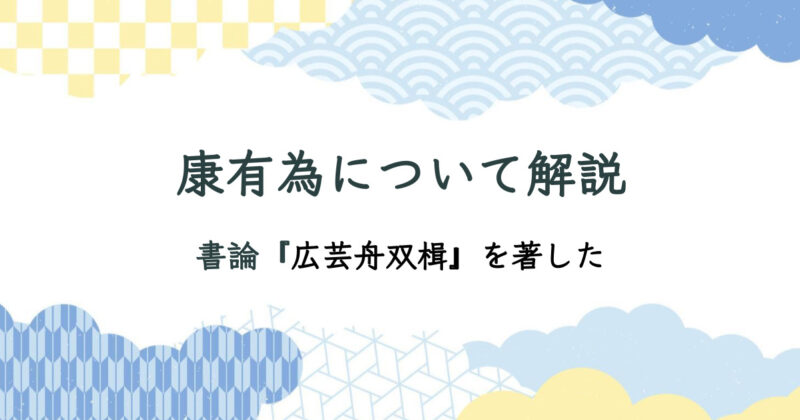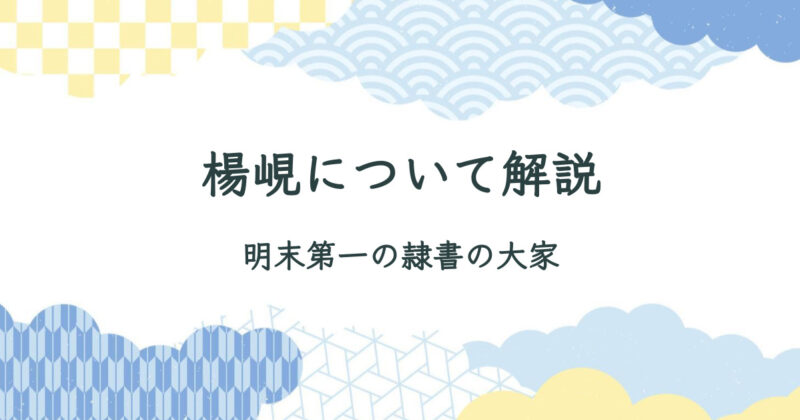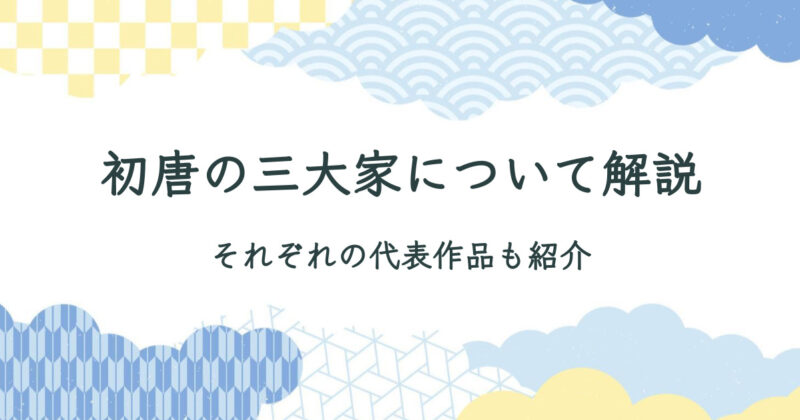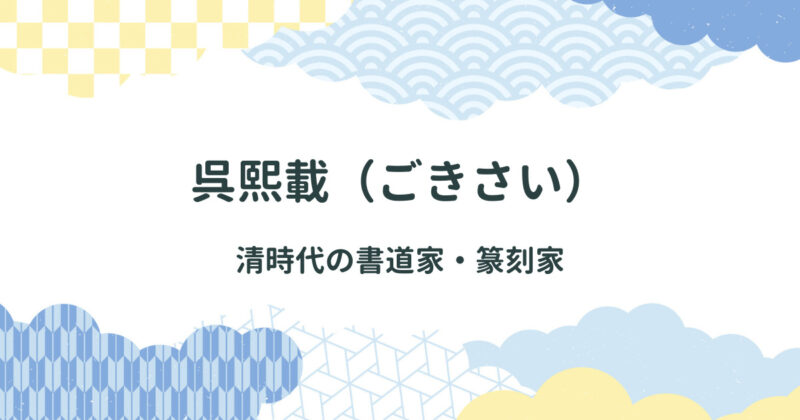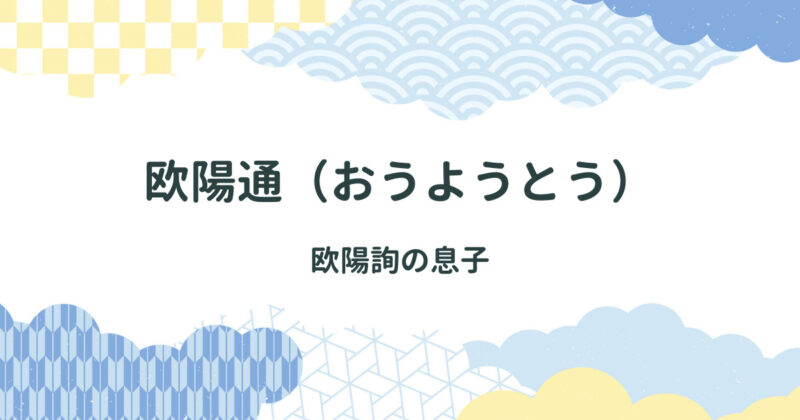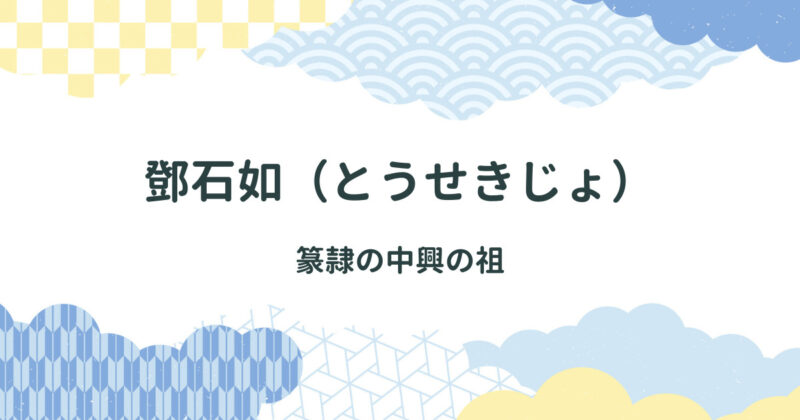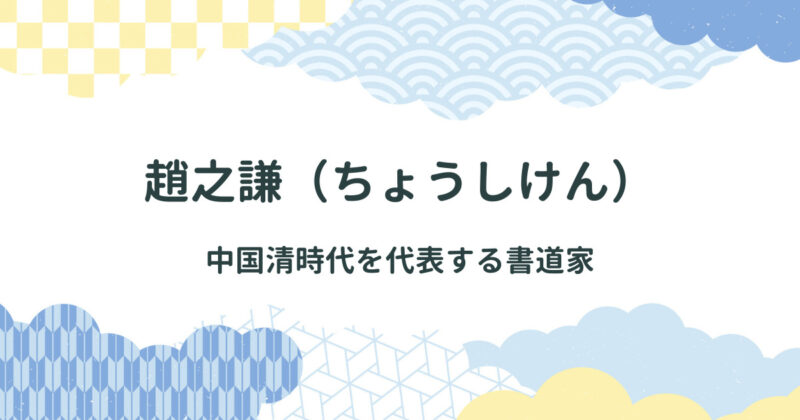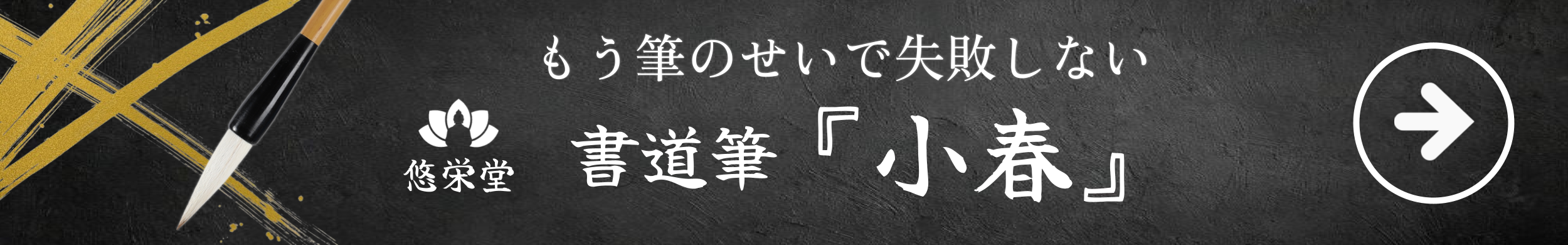中国の書家– category –
-

褚遂良(ちょすいりょう)について解説/代表作品も紹介
【褚遂良について解説】 褚遂良像 雁塔聖教序という人物です。 褚遂良」と呼ばれています。 彼は唐)で生まれました。 中国における書道の名手は、同時にその時代を動かしてきた政治家や学者でもありますが、褚遂良も例外ではなく、唐の建国期を支えた重臣... -

楊守敬(ようしゅけい)について解説/作品も紹介【中国清時代の書道家】
日本では明治の書道が流行し始め、篆書や隷書の作品が盛んに書かれるようになりました。 これは、中国からやってきた楊守敬という人物が日本にたくさんの碑版法帖を持ち込んだことがきっかけとされています。 今回は、日本に碑学派が流行する仕掛け人とな... -

康有為(こうゆうい)について解説【碑学派の書論を著した】
康有為』は、碑学尊重の書論で、日本においても碑学派が流行するにあたって翻訳され、大きな影響をあたえました。 今回は、『広芸舟双楫という人物について解説します。 【康有為(こうゆうい)について解説】 康有為 康有為の名著ものこしています。 1858... -

【清代の書道家】楊峴(ようけん)について解説/作品とその特徴
清の隷書は、清時代後期においても多くの人々によって学ばれ続けました。 漢碑のみを専門として、独自の様式を作り上げ、隷書の大家として後世に名をとどめるほどの人物となると、数は限られます。楊峴ははそのなかの最たる存在といってよいでしょう。 今... -

初唐の三大家とは?【彼らの功績・代表作品とその特徴】
『初唐の3人を合わせた総称です。 それぞれ独自の書風と特徴を持つ代表的な作品は、楷書の発展に大きく貢献しました。彼らは書道の歴史において非常に重要な存在となっています。 この記事では、初唐それぞれ3人の生涯や代表作、その書風などについて詳し... -

呉熙載(ごきさい)について詳しく解説:清時代の書道家・篆刻家/別名呉譲之(ごじょうし)
【呉熙載(ごきさい)とは】 呉熙載像 呉熙載時代の書道家・篆刻家です。 はじめ名前を廷颺し、熙載を改めて譲之を名前としました。 他にも言菴といいました。 呉熙載(官僚登用試験)の試験を受けず、平民として売書、売印の生活をおくりました。 官歴が... -

欧陽通(おうようとう)を紹介/欧陽詢の息子
欧陽詢の三大家」の1人であり、楷書の典型の確立に大きく関係していることは有名な話です。 今回紹介する欧陽通の息子で、彼も書道を得意としたことで有名です。 【欧陽通(おうようとう)の基本情報】 欧陽通像 欧陽通(湖南省)の人です。 正史の3人の... -

中国清時代の書道家・鄧石如(とうせきじょ)について解説
【鄧石如(とうせきじょ)の基本情報】 鄧石如像 鄧石如が専門の書道家です。 1743年(乾隆8年)~1805年(嘉慶10年)、本名は琰に変えました。 安徽省集賢関の人です。 懐寧県とも名乗りました。 鄧石如されるものではありません。以下、「完白山人伝」... -

清時代の書道家:趙之謙(ちょうしけん)について解説/特徴・隷書・行書の作品を紹介
【趙之謙(ちょうしけん)の基本情報】 趙之謙像(清代学者像伝第二集) 趙之謙時代末期において、書・絵画・篆刻の世界でもっとも華やかで力強い作品を残した芸術家として有名です。 趙之謙についての伝記は、『清代画家詩史』辛巻、『国朝書画家筆録』巻... -

李邕(りよう)について詳しく解説/唐時代に活躍した行書専門の書道家
中国唐がつくられるなど、楷書が注目されました。 盛唐のころになると、楷書よりくだけた行書に優れた書人があらわれます。そのなかでも特にすぐれた書人が、今回紹介する李邕です。 【李邕の基本情報】 李邕時代の行書の名手として第一に挙げられる人物で...