日本の法帖– category –
-

空海の代表作品:風信帖(ふうしんじょう)を解説/臨書に役立てたい書き方・特徴
「風信帖に宛てた手紙で、空海の代表作の一つです。この作品は、当時の文化を知る貴重な資料としても高く評価されています。 この記事では、風信帖の書き方や特徴について詳しく解説し、空海と最澄の関係にも触れます。歴史的背景を理解することで、風信帖... -
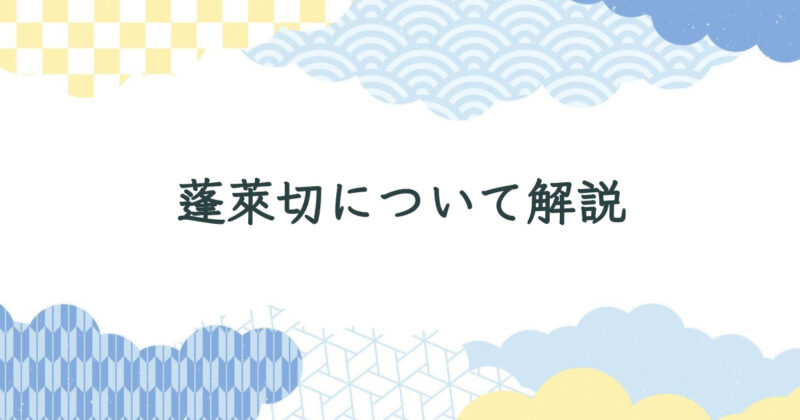
蓬萊切(ほうらいぎれ)について解説【作者・読み方】
蓬萊切(ほうらいぎれ)について解説 蓬萊切 五島美術館蔵 蓬萊切(切とは断簡のこと)は、『拾遺抄』『拾遺和歌集』から4首、『後撰和歌集』から1首を書写した古筆断簡です。 もともとは巻子本でしたが、昭和9年(1934)1首ずつ5枚に分割されました... -
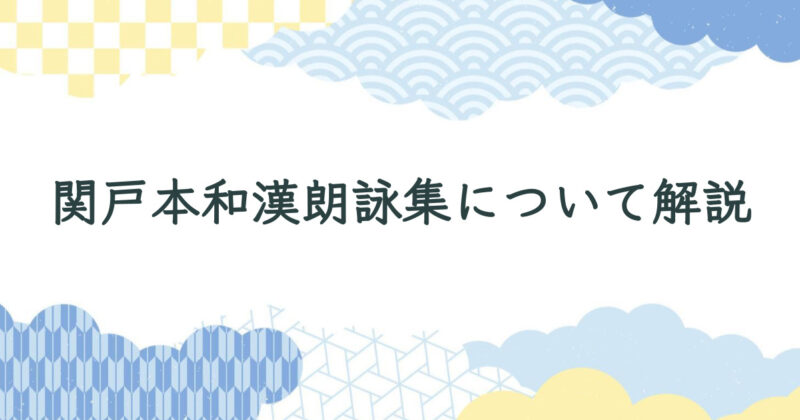
関戸本古今集(せきどぼんこきんしゅう)について解説/臨書に使える画像
関戸本古今集について解説 関戸本古今集 関戸本古今集の作者は、伝藤原行成です。 名称由来は、名古屋の関戸家に零本が伝来したことにちなんでいます。 書写内容は『古今和歌集』です。 装丁は綴葉装の冊子本です。書写年代は11世紀半ばです。 料紙は紫、... -
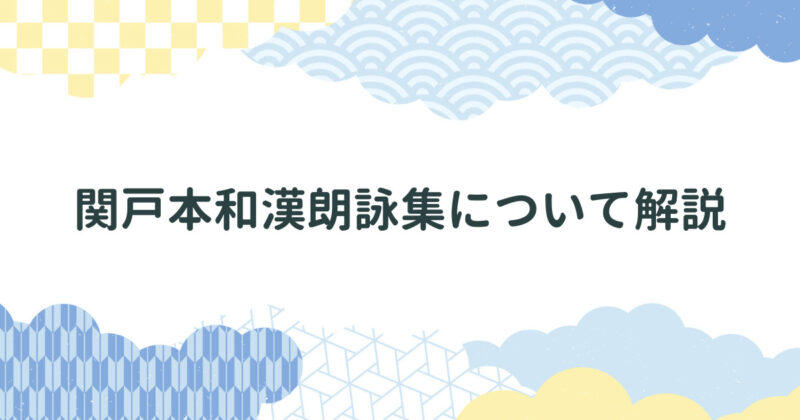
関戸本和漢朗詠集について解説
関戸本和漢朗詠集について 関戸本和漢朗詠集 関戸本和漢朗詠集筆とされています。 関戸本和漢朗詠集の名称の由来は、名古屋の関戸家に伝来したことからこの名称がつけられました。 書かれている内容は、『和漢朗詠集』です。 装丁は巻子本、書写年代は11世... -
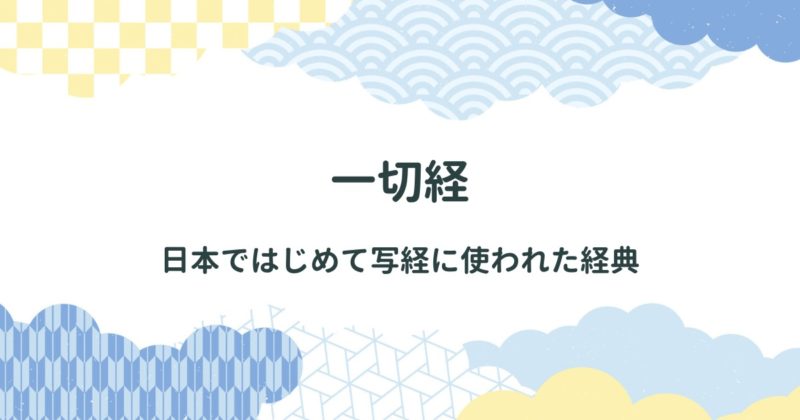
一切経(いっさいきょう)について詳しく解説【日本ではじめて写経に使われた経典・金泥一切経と銀泥一切経・一日一切経・一筆一切経】
今回紹介する「一切経」は、日本に写経が伝わり、はじめて写経につかわれた経典です。 日本では、この一切経の写経がもりあがり、金色の文字で書いたり、とてもたくさんの人々の協力のもと1日で写経を完成させるというイベントが開かれたりしました。 今... -
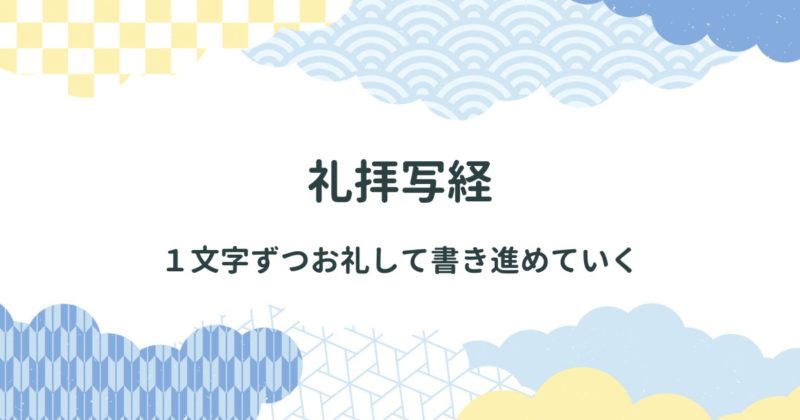
礼拝写経を紹介【お経の文字を1文字書くごどに礼拝を行う写経方法/一字一礼・一字三礼・一行三礼・一巻三礼】
写経は、亡くなった方を供養し、成仏を願って行われました。 この想いを写経に表現するだけでなく、表現としては残りませんが1字1字に祈りを込めて筆を運びました。 このお経を写すにあたって、以下の3種類の祈りが行われました。 1字書くごとに1礼、... -
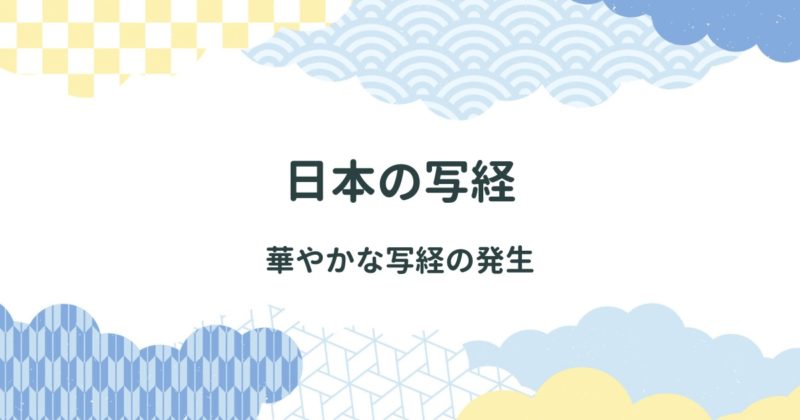
日本に写経(しゃきょう)が伝わる/日本独自の華やかな写経
写経のことをいいます。 中国大陸から日本に伝わり、日本でも写経が行われるようになりました。 日本に写経が伝わると、日本独自のとても華やかな装飾を施した作品としての写経が作られるようになります。今回は、日本に写経が伝わってから日本独自の華や... -
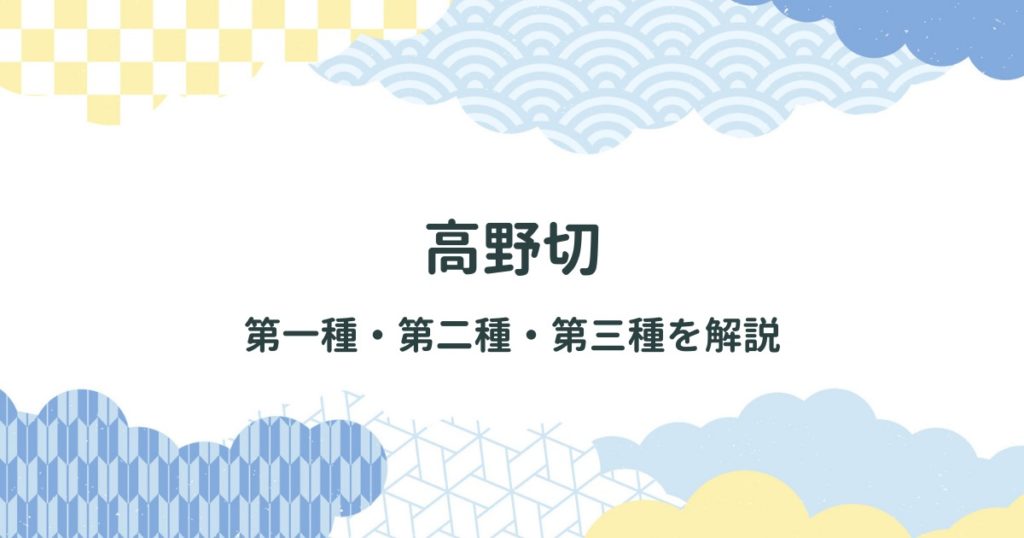
高野切第一種・第二種・第三種について時代や特徴を解説
高野切は、私たちが学ぶかなの古典の中でもっとも有名なもの、そして最も正統的だと考えられています。 今回は、高野切とは一体どのようなものなのかを解説していきます。 高野切について 高野切第三種 巻十九断簡 ※クリック/タップで拡大 「高野切」と... -
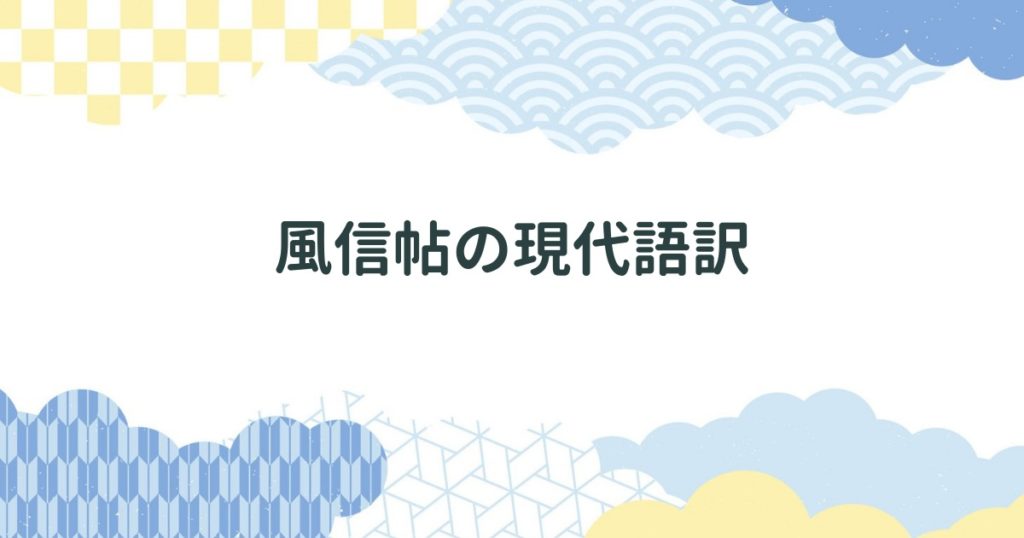
風信帖の内容を全文現代語訳で紹介
風信帖)計3通をつなげて1巻に仕立てた総称です。 こちらでは、風信帖3通の内容を全文現代語訳で紹介します。 第1通「風信帖」 釈文 風信雲書、自天翔臨。披之閲之、如掲雲霧。兼恵止観妙門、頂戴供養、不知攸厝。已冷。伏惟法體何如。空(海)推常、... -
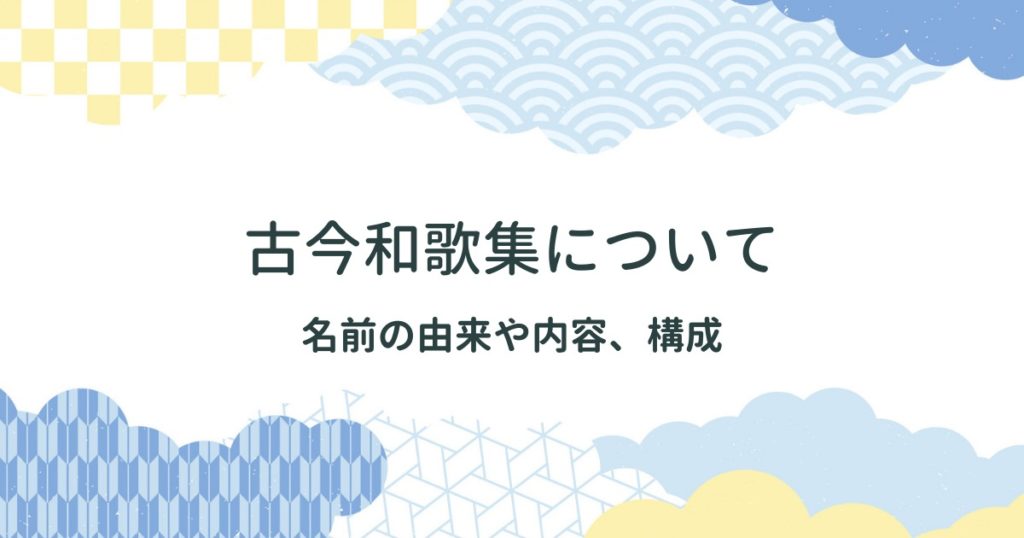
古今和歌集の名前の由来や内容、構成などを分かりやすく解説【最初の勅撰和歌集】
古今和歌集の由来 古今和歌集という名前の由来について説明していきます。 まず、「和歌集」という部分は理解できると思います。和歌を集めてそれをずらっと書き連ねたものをいいます。 「古今」とは何を意味しているのでしょうか。 「古」とは『万葉集』...
12

