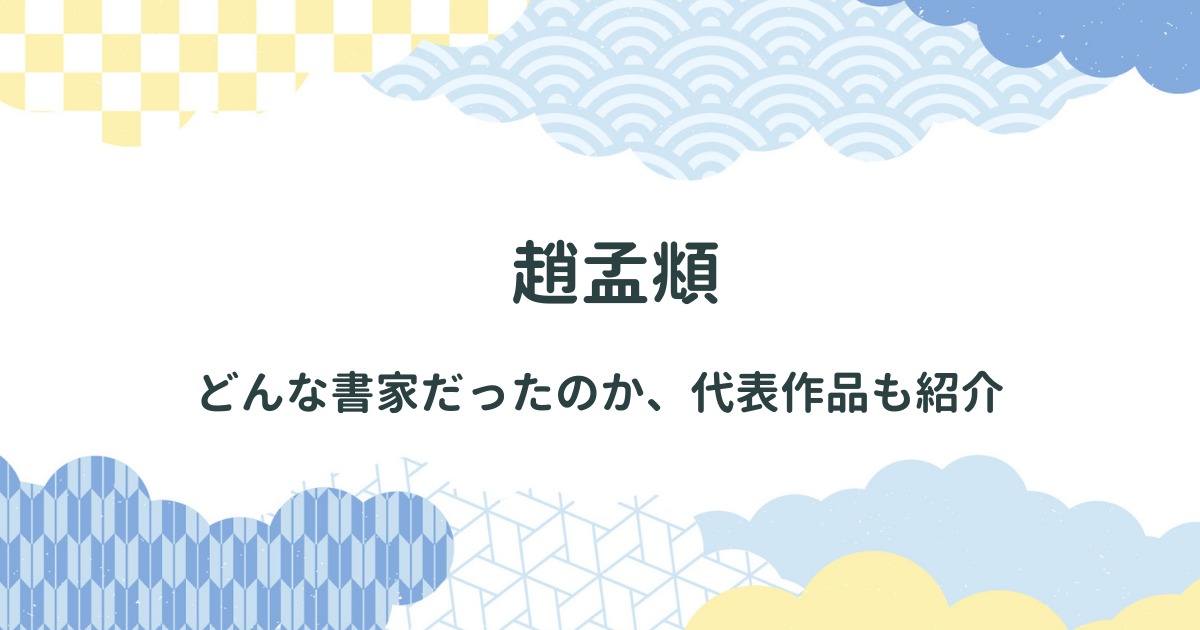趙孟頫は宋末に生まれ、13世紀から14世紀にかけて活躍し、元王朝の書壇を従わせた書家です。
また、中国歴代を通じての大家であり、書だけでなく、画・詩・文にも大きな足跡を残しました。
今回は、趙孟頫とはどんな書家だったのか、彼の代表作品も紹介していきます。
書道をはじめるなら、オンラインという選択肢も!
SHODO FAMなら、あなたのペースで、いつでもどこでも書の学びを深められます。

書き方動画を見ながら練習して、書いた作品はスマホで撮って提出するだけ。
添削・サポートつきだから、ひとりでも安心して続けられます。
\6月30日まで!7日間無料キャンペーン/
趙孟頫の基本情報
趙孟頫は南宋の宝祐2年(1254)に生まれ、至治2年(1322)に69歳で亡くなりました。
いまからおよそ700年前に生きていた人物ということになります。
趙孟頫は宋の皇族の子孫です。
字を子昻、雅号は松雪道人・鴎波、おくり名を文敏。
また、呉興(浙江省湖州市)のひとなので趙呉興、官位によって趙栄禄とも呼ばれます。
趙孟頫の人生
趙孟頫の家系は、宋王朝を作った太祖 趙匡胤(宋の初代皇帝)までさかのぼります。
北宋の1代目は、太祖の弟の太宗の系統から皇帝を出しているので、趙孟頫が属する太祖の直系はきわめて不遇な状態におかれていました。
しかし、太宗の血統は南宋初代の高宗で途絶えてしまい、趙孟頫の家系から入った養子が第2代考宗となりました。
従って、趙孟頫の家は南宋ではれっきとした皇族でした。
ところが趙孟頫が26歳の時、宋はモンゴル政権によって滅亡して、元王朝になります。
趙孟頫は故郷に引きこもる生活をおくっていましたが、33歳の時、元の世祖(フビライハン)の王朝に抜擢されます。
それから35年間、世祖・成宗・武宗・仁宗・英宗の5朝に歴任します。
はじめは地方官を務めますが、のちに大都(今の北京)の中央政府に入り、とくに仁宗のときに優遇されて翰林学士承旨、栄禄大夫までなりました。
敵政権に仕えた趙孟頫
宋の皇族の出身でありながら、自国を滅ぼした敵国である元の朝廷に仕えた無節操な人間だとして、趙孟頫は親戚や知り合いから非難されました。
そこには、彼1人だけが新王朝に抜擢され、日の目をあびていることに対する嫉妬心も含まれていたでしょう。
また、元の朝廷では宋の皇族の出だということで、モンゴル人官僚からは警戒の眼をもって迎えられました。
地位と名誉に恵まれながらも、趙孟頫の精神衛生面は良くなかったと思われます。
趙孟頫の書風
書人としての趙孟頫は、「復古主義」に終始しました。
彼の目標は王羲之であり、その伝統を守ろうとしたのです。
王羲之の書を尊重するのは、太宗時代以来、宋の皇室の伝統のようになっています。
皇族の子供として生まれた趙孟頫が、王羲之の貴族的な書を最高のものであると考えたことは、その環境からして自然なことでしょう。
この「復古主義」は同時代の書人たちにも影響を及ぼし、さらに、明清の時代にも多くの追随者を得ました。
趙孟頫の風格高く、貴族的な雰囲気の美しい字は、多くの人々をひきつけるだけの価値あるものなのです。
趙孟頫の書の批評
趙孟頫の書の特徴を評価する言葉に、「筆法妍媚」「結体淳古」というものがあります。
このような美しさをもっているところが彼の長所ですが、その反面、力が足りないとか、起伏・屈折がないとかいう批判もありました。
その中でもっとも趙孟頫の書を容赦なく批判している人物として、董其昌が有名です。
「古人の書は、ただ礼儀正しく、まっすぐには書いていない。横へ傾いたような変化をもった字を書きながら、それでいて、全体としてまとまって芸術的効果を上げているのであるが、趙孟頫はそのところが分かっていない。だから、きれいに書くことだけしか知らないのだ」(意訳)
董其昌が批判している点はなるほどと思わされますが、では董其昌の方が趙孟頫よりも優れていたのかどうかというと、そうとは言い切れないように思います。
董其昌は人格に問題があったという記録もありますし、2人の画(絵)のほうを見比べてみると、圧倒的に趙孟頫の方が優れています。
だいたい発言力のある人のなかには、だれだれよりも自分の方が優れていると主張したがる人もいます。
董其昌は、趙孟頫が生まれ持った才能で、王羲之の本質をつかみ、王羲之以来の第一人者だと世間から考えられている事実に反発せざるを得なかったようです。
趙孟頫の書の美しさは分かりやすくはっきりしています。
趙孟頫は王羲之の字に正面から向き合った結果、多くの人が理解しやすいため、批判もしやすかったのでしょう。
趙孟頫の代表作品
ここからは、趙孟頫の代表作品を紹介していきます。
蘭亭十三跋(らんていじゅうさんばつ)
至大3年(1310)、57歳時の行書作で、いまは東京国立博物館に所蔵されています。
原跡は清時代の乾隆年間に、火災のため本紙の上下が焼失してしまいました。
内容は、皇太子(のち仁宗)に召され、呉興から都へ上る1か月あまりの船旅の途中で、1人でいた長老から譲られた定武蘭亭序を鑑賞し、日を追って書いた本文の後に書いたあとがきです。
王義之の書の書品と、用筆・結構にわたる学書法などの文章が13個あるので、この名でよばれています。
快雪時晴帖跋(かいせつじせいじょうばつ)
延祐5年(1318)
仁宗の勅命で、王義之の快雪時晴帖に跋した、65歳の時の小楷です。
鮮子極が「かれの篆隷楷行草書は当代随一。中でも、小楷はその諸体中の第1である」
と褒めたたえているとおり、寛雅で婉麗なこの作は、晩年の傑作です。
帝師胆巴碑稿(ていしたんはひこう)
延祐3年(1316)
北京・故宮博物院に現蔵し、33.66×166㎝の紙本巻子装で、巻首に半紙4字書きほどで自筆の篆題18字があります。
内容は、世宗朝の国師である僧・胆巴の事蹟を記したものです。
この中字の楷書は、晩年に李亀・柳公権を学んだという、その李島風です。
ただし、小楷にくらべれば骨力に乏しいと評価されています。
前後赤壁(ぜんごせきへきふ))
大徳6年(1301)
台北・故宮博物館の所蔵で、もとは巻子装でしたが、現状は毎幅四行、27.2×11.4㎝、21幅の冊子に改装してあります。
得意の行草体によって、蘇軾の名文「赤壁賦」を書いたものです。
明遠という人(この人の詳細は分かっていません)に書き与えた作品で、蘇軾の肖像画(七頁章扉)を、巻首に描き添えためずらしいものです。
この書は、47歳時の作例で、でに王羲之の書法をすっかり吸収して、自信に溢れた一家の見識をうち出しています。
般若心経(はんにゃしんぎょう)
遼寧省博物館蔵。白描画の観音像などとともに、冊仕立てに合装されています。
心経の部分は6頁で、毎頁に4行を入れ、28.8×10.8。
書写年代は不明だが、王法に机心した中年期の作品かと思われます。
一見、集王聖教序末の心経を臨書したかと思うほどですが、よくみると王羲之書法を消化した独自の書風です。
尺牘(せきとく)・塵事帖(じんじじょう)
台北・故宮博物院の現蔵。
『趙氏一家法書冊』と題し、13幅を収めたうちの1幅で、28×53.1㎝の紙本に16行で書いた書翰であす。
書写年代は記されていませんが、最晩年の作品であるとされています。