明末から中華民国にかけて活躍した書画家・王一亭(1867~1938)は、呉昌碩と関連づけて語られることが多いです。
それは、王一亭は呉昌碩晩年のよき友人、弟子であり、時には代作をつとめるほどの人物だったからです。
では、どうして王一亭が晩年の呉昌碩とこういった親密な関係を持つようになったのでしょうか。また、王一亭にとって呉昌碩とはどんな存在だったのでしょうか。
今回はこういった疑問についてわかりやすく解説していきます。
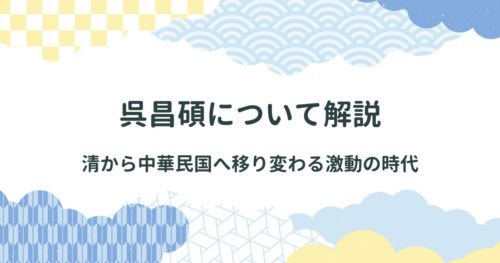
書道をはじめるなら、オンラインという選択肢も!
SHODO FAMなら、あなたのペースで、いつでもどこでも書の学びを深められます。

書き方動画を見ながら練習して、書いた作品はスマホで撮って提出するだけ。
添削・サポートつきだから、ひとりでも安心して続けられます。
\6月30日まで!7日間無料キャンペーン/
王一亭について

まず、王一亭という人物についてふりかえります。
王一亭は名を震といい、字を一亭としました。仏教を信仰し、法名を覚器といいます。
1867年(清王朝)、上海浦東三林塘の母方の祖母・趙氏の家に生まれました。
本籍は浙江省呉興区(湖州市)で、その西北にある白龍山という山にちなみ、40歳以降、雅号を白龍山人としました。
代々農業を営んでいた家系でしたが、父・王馥棠の代にはじめて商業に従事し、馥棠は太平天国の乱を避けて江蘇匯浦県周浦鎮にやってきました。
しかし、父の馥棠は早くに亡くなってしまったため、王一亭は上海にいた母方の祖母に育てられました。
10歳のとき、祖母から『考経』を学ぶかたわら、すでに亡くなっていた母方の祖父の画を観たことにより画に興味を持ち、しばらくして画家の徐小倉から画を学びました。
13歳のとき、李平書が設立した金融機関・慎余銭荘に見習いとして入り、夜は広方言館で外国語を学びはじめましたが、総長と深夜に時間を見つけては画の練習をしていました。
そんなある日、近所の表具店で私淑していた任伯年の画を見つけ、臨摹していたところを任伯年本人に見込まれ、その弟子に加えらてもらったといいます。
20歳になると、これも李平書の経営による海運会社・天余号に移動し、営業からはじまっての途に経理(取締役)となりました。
1907年、41歳のとき、日本に日清汽船株式会社が東京で成立し、子会社を上海にも作りました。
王一亭は李平書の紹介で上海子会社の管理者となり、後には大阪郵船株式会社の管理者および三井洋行が設けた上海製造絹糸社の社長も兼任し、莫大な収入を得るようになりました。
住居は上海の南市に梓園という庭園を築き、そこに住み始めます。
呉昌碩と王一亭の出会いと入門
王一亭が呉昌碩といつ、どのような形で出会ったのか、はっきりとしたことは分かっていません。
ただ、1909年4月22日に創設された上海豫園書画善会の発起人に、呉昌碩と王一亭の両方の名前があることから、また、当時蘇州にいた呉昌碩がこの会の創設にあたり上海に行ってるので、この時に会っている可能性がとても高いとされています。
さらに、1910年、呉昌碩が自分が上海進出する前にさきだって弟子の趙子雲を上海に送り出した際、王一亭への紹介状を持たせていることから、少なくとも上海豫園書画善会が創設された1909年には、2人は出会っていると考えてよいでしょう。
そして1911年、呉昌碩は蘇州から上海に移住し、1913年、王一亭は呉昌碩に弟子入りするのです。
したがって、王一亭は呉昌碩と少なくとも1909年には知り合っていたとされているのに、4年後の1913年までその門下に加わらなかったということになります。
王一亭は書画家であるとともに、実業家でもあったためそのことも影響しているのかもしれません。
とても仲良しな呉昌碩と王一亭
王一亭は、「六三園」という日本人・白石六三郎が経営する日本料亭に、呉昌碩をたびたび誘ったそうです。
呉昌碩はこの六三園での宴会がとてもお気に入りだったようで、誘われれば2つ返事で行き、泥酔してはいきなり声を出すなどしてお供の王一亭をはらはらさせました。
ついには王一亭に抱きかかえられて連れ出されようとすると、子供のように心残りな態度をしつつも素直にしたがったといいます。
どうして王一亭は呉昌碩と仲良くなろうとしたのか
どうして王一亭は晩年の呉昌碩とこういった親密な関係を持つようになったのでしょうか。
王一亭は、実業家であり、政治家・革命家でしたが、政治家・革命家であることをやめ、書画家となって新しい人生を歩むために呉昌碩に入門しました。
これは仕事を書画家とするためのビジネスライクなものではなく、王一亭にとって呉昌碩は人生の後半の拠り所であり、この拠り所があるからこそ実業家としての苦しみも忘れることができたのです。
また、呉昌碩も王一亭に自分の苦悩や葛藤を打ち明けていました。
呉昌碩が王一亭との関係において、書画の師匠以上の役割を果たしていたことが感じられます。







