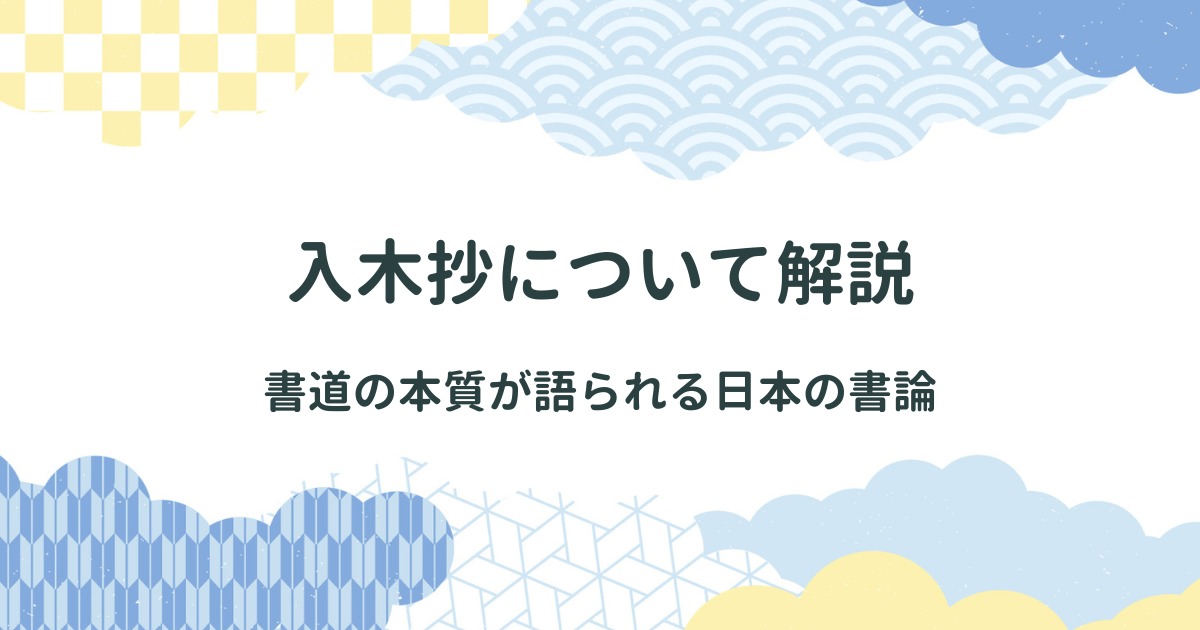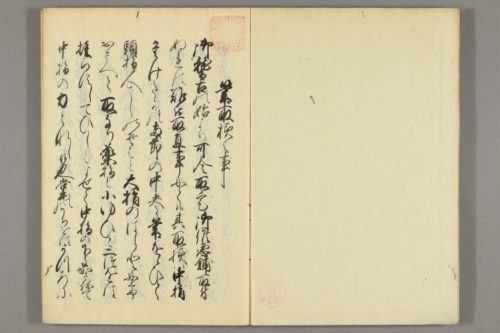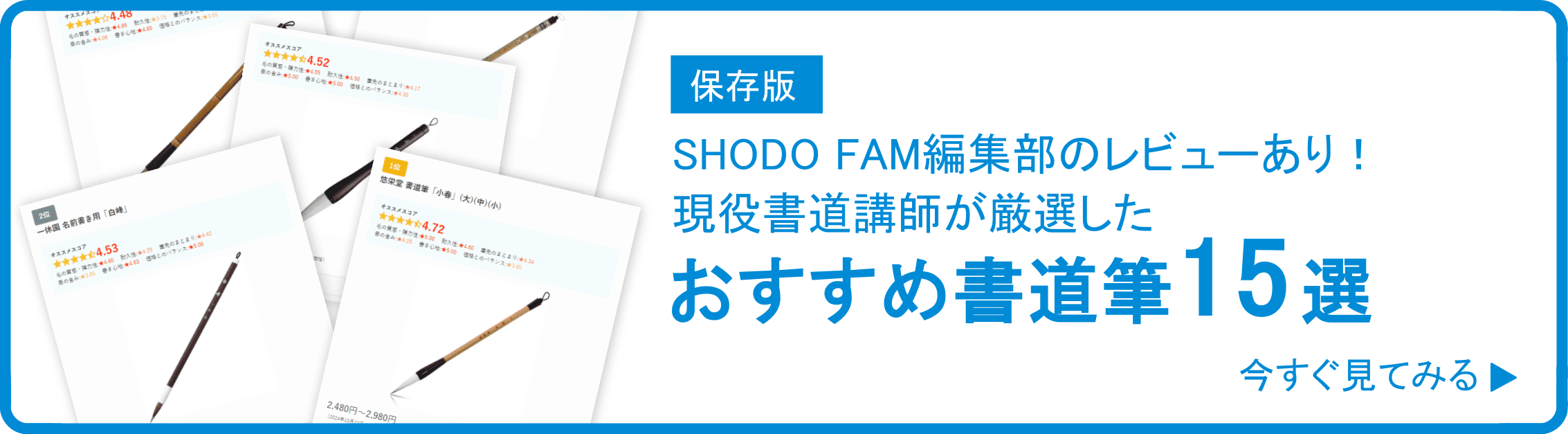書道をはじめるなら、オンラインという選択肢も!
SHODO FAMなら、あなたのペースで、いつでもどこでも書の学びを深められます。

書き方動画を見ながら練習して、書いた作品はスマホで撮って提出するだけ。
添削・サポートつきだから、ひとりでも安心して続けられます。
\6月30日まで!7日間無料キャンペーン/
- 入木抄(じゅぼくしょう)について解説
- 入木抄の内容を現代語訳で紹介
- 1,筆の持ち方について
- 2,お手本は一部分を完璧にしてから次へすすむ
- 3,字の大きさについて
- 4,筆遣いは大切である
- 5,昔の人の筆遣いについて
- 6,邪僻を離れて、正しい姿をひたすら追い求めるべき
- 7,異様の字を好んではならない
- 8,楷書・行書・草書について
- 9,お稽古の進歩の度合いが表れる
- 10,稽古の間、調子のいいときと悪いときがある
- 11,お稽古の時間について
- 12,手本を選ぶこと
- 13,手本が多いのは大切である
- 14,現代は手紙を手本とすることが多いが、そうするべきではない
- 15,筆について
- 16,墨について
- 17,料紙について
- 18,入木道の一流
- 19,日本では書体は一つですが、時代によって書風がはっきりしている
- 20,能書を登用なされること
- 21,最後のまとめ
入木抄(じゅぼくしょう)について解説
入木抄は南北朝時代に、尊円法親王が後光厳天皇に書道の入門書として上奏したものです。
上奏とは言っても、尊円法親王は55歳、後光厳天皇は弱冠15歳のときで、書道の上では師弟関係にありました。
内容は、書道上達のための心得を教える講義内容が書かれています。
成立の詳細な年は、その伝写本の奥書に「文和元年十一月十五日」とあることから、西暦でいうと1352年とされています。
入木抄の入木とは、「書道」と同義語として使われています。入木道ともいいます。
入木抄の抄とは、書き写すことをいいますが、入木抄のほかにも「才葉抄」「夜鶴庭訓抄」などという書物があり、「~抄」という使われ方をしています。
「入木抄」より前に書かれた「夜鶴庭訓抄」は、日本において「入木」の語を定義した最も古いものとされています。↓

入木抄の内容を現代語訳で紹介
1,筆の持ち方について
(筆を取る事)
筆の持ち方
(御稽古の始めより取り定め御すべく候。悪しく取り付き候いぬれば、改められ難き事にて候うなり。)
お稽古を始めるときから、どのように筆を持つかをお決めにならねばなりません。悪い持ち方を身に着けてしまうと、直しにくいものです。
(その取り様は、中指クケタカの両節の中央に筆を置きて、頭指人さしのそばと大指の腹とにて押さえて取り候うなり。薬指と小指と二つをば握らずして、ひしと寄せて、中指の下に重ねて、中指の力に成し候うなり。)
その持ち方は、中指の第一関節と第二関節の中間に筆の軸を当て、人差し指の側面と親指の腹とで押さえて筆を持ちます。薬指と小指の二本では握らずにぴたりと寄せて、中指の下に重ね、中指の力添えにするのです。
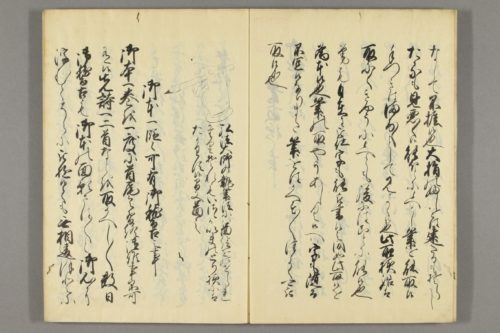
(たなごころの内をば、うつろになして握らず候うなり。大指の節をば、立てたるも反らしたるも、見悪しく候。よき程に筆をよく取りて、手つきはまろまろとしてよく候うなり。)
手のひらの中を空虚にしておき、握らないようにします。親指の関節を立てたりするのも、逆にそらしたりするのも見苦しいものです。このようにほどよく筆をもつと、手のこうが丸々として見良いものです。
(この取りようは、初めは取り悪くき様に候えども、後には殊によく候。筆も自在に使われ、字もよく書かれ候う間、かくのごとく取り候うを本とし候うなり。)
この握り方は、初めのうちは握りにくいようですが、後には、この上なく良い握り方になります。筆も自由自在に取り扱うことができ。字もよく書くことができますので、このような持ち方を基本としています。
(筆の取り様悪しく候えば、字も従いてよろしからず。また、筆をいか程にも強く取り候うなり。)
持ち方が悪いと、書かれた字もそれに伴って良くありません。また、筆を強く持つことにもなって自由さを失います。
(弘法大師の執筆法には、図絵を載せられたり。それも、いささか今の執り様には違わず候う間、またこれを図く。)
弘法大師(空海)の執筆法には、図を載せておられます。その執筆法は、現在の執筆法と少しも違いがないので、またここに図示しました。
2,お手本は一部分を完璧にしてから次へすすむ
(御手本一段一段御習いあるべき事)
お手本は、一段一段お習いにならねばならないということ
(御本一巻を、一度に首尾を習わせ給う御事はあるべからず候。まず詩一、二首などを、取り返し取り返し数反数日御稽古候いて、御本の面影さわさわと御心に浮かみて、そらに遊ばされ候も、相違無き候程になりて後、次第に奥をも御習いあるべし。)
お手本一巻を、始めから終わりまで一度に通して習うようなことをなさってはいけません。まず、詩の一首か二首程度を、数日間何回もくり返しくり返しお稽古なされ、お手本の筆遣いや形が明らかにはっきりと心の中に浮かんで、ご覧にならなくても手本通りに書けるようになってから、だんだんとそのあとの方もお習いなさい。
(初めよりよく稽古し候いぬれば、後にはそれ程に功も入れわねども、易く相似候うなり。)
はじめうちからこのようにお稽古をしていますと、後には、それ程練習を積まなくても、容易にお手本に似てまいります。
3,字の大きさについて
(字の勢分の事)
字の大きさについて
(初心の程は、本よりも殊の外に、大に書かれ候う事にで候。ただ、手本の文字程に習い候うなり。)
初歩のうちは、お手本よりも意外に大きく書いてしまうものです。ただひたすら手本の文字の大きさになるように習います。
(また、いかにも、本よりは大にて筆細くなり候う事にて候。これが悪しく候。)
また、手本より文字は大きくなって、点画すなわち線は細めになってしまうものです。これが良くありません。
(字の勢、大に候わば、筆の太さも、本より太くてこそ相応すべく候え。)
文字の形が大きくなれば、点画の太さもお手本より太くなってこそ似合うのです。
(所詮、字の勢も筆の太さも、本に違うべからず候うなり。本より、いささか見勝り候う苦しからず候。本より小さくは遊ばすべからず候なり。)
結局、字の大きさも線の太さも、手本に違ってはなりません。手本よりも少し大きく見えるのは差し支えありません。手本より小さく書いてはなりません。
4,筆遣いは大切である
(筆仕い肝要たる事)
筆遣いは大切であるということ
(紙上に字を成し候う事は、能筆も非能筆も、同じ事にて候えども、筆仕いによりて、善悪相分かれ候なり。)
紙の上に文字を書くことは、能筆の方でも非能筆の方でも同じですけれども、筆遣いによって、良い書であるか、わるい書であるかにわかれるのです。
(その筆仕いの様は、古筆をよく上覧候いて御心得有るべく候。)
その筆遣いの方法は、古筆をよくご覧になって会得してください。
(それにつき、なお御不審の事候わば、仰せ下され、申し入れるべく候。)
それでもなお、古筆の筆遣いに疑問がおありでしたら、お尋ねくださればお答えいたします。
(所詮、手本を習い候うについて、字形と筆仕いと、よく習い候う人は、一致にして相違無く候。)
結局、習い方の良い人は、字形と筆遣いに矛盾が見られず、両者にずれがありません。
(悪しく習い候う人は、文字の姿を似せんとし候えば、その姿は似候えども、筆勢を写し得ず候えば、精霊無きがごとくに候うなり。これは、いたずら物にて候。)
習い方が悪い人は、文字の形を似せようとするので、その形は似ますが、筆勢を表現することができないので、気力がないようなものです。これは、形は似ているがつまらないものです。
(仮令、字形は人の容貌、筆勢は人の心操・行跡にて候。所詮諸道の習字は、心の上の所作にて候う間、よく古賢の心に基づきて、その道を学び候えば、自然に妙を得候うなり。)
例えば、文字の形は人の顔かたちであり、筆勢は人の心の動きとか行いのようなものです。結局、いろいろな道の学習は、心に関する行為ですから、昔の賢人の心にもとづいて、よくその道を学べば、自然に優れてまいります。
(屈曲横堅の点、一々に自由に任せず、先哲の行跡に従いて、筆を下し候えば、おのずから通達し候うなり。)
折れ・曲がり・横・縦について一つ一つを気ままにせず、先人の残した学習方法に従って筆を下ろしますと、自然に熟達してまいります。
(御稽古の始めは、相構えて御筆を静かに、よくよく執して遊ばさるべく候。御通達の後は、御筆に任せられ候うも、筆法に違すべからず候。)
お稽古の初めは、居ずまいを正し、筆を静かに運び、よくよく心をこめて練習をなさいませ。ご熟達になった後は、筆に任せてお書きになっても、筆法から外れることはありません。
(孔子の言葉に、「七十にして心の欲する所に従えども、矩を踰えず。」と申し候もこれにて候。)
孔子の言葉に、「七十になって、心のままに行動しても法度を越えない。」とあるのもこのことです。
(御手跡の御稽古も、これをもて是とすべく候うなり。)
書道のお稽古も、筆遣いをもっとも重要なこととしています。
5,昔の人の筆遣いについて
(古賢の筆仕いの事)
古賢の筆遣いのこと
(この事、古筆を開きて、御心得あるべきよし載せ候いおわんぬ。)
このことは、古筆をご覧になって会得なさいますようにと前の条で述べておきました。
(言を以て述べ難く候。筆を以て記し難きの故なり。ただ、細々眤近もかなうべからざる上は、きと申しひらき難く候。)
筆遣いは、言葉で言い難いのです。文字に書き表し難いのです。直接頻繁に、親しくお目にかかることもできないので、はっきりと説明申し上げることが難しいのです。
(然ればまたこの一か条は殊に肝要なり。)
それであるからこそまた、この一か条「古賢の筆遣いを会得すること」は重要でございます。
(誠に筆語の及ぶ所までは、書き述べる候うなり。)
誠に、文章で説明できる限りの所までは、書き記しましょう。
(古賢能書の、筆つかい様は、いずくにも精霊有りて弱き所無し。筆を立て始めるより、引き果てつる処、点ごとに心を入れて、あだなる所無く書くべきなり。)
古の能書すなわち優れた書家たちの筆遣いは、すみずみまで気力がこもっていて、弱いところがありません。起筆から終筆まで、どの点画にも心を集中し、気の抜いた所がないように書くものです。
(能書は、筆を打ち立てる所、終わる点、折り候う所、跳ねる所、かくのごときの処々に心を留めて、精を入れ候うなり。)
書に優れた人たちは、起筆のところ、終筆のところ、転折のところ、はねるところ、このような節々に注意して、気を込めて書きます。
(非能書の書きたる物は、木などを折りかけたる様にて、用の無きなり。)
能書でない人たちの書いたものは、木などを折り曲げたようで、筆の働きが生き生きとしません。
(所詮は、一点を下すごとに、その心を思えば、あだなる点あるべからず。一点もあだなる所あれば、一字皆悪く見ゆ。まして一時を心を止めずば、さながらいたずら物なり。)
結局、一つの点画を書くごとに、その点画に寄せる優れた書家たちの心づかいを考えると、いいかげんな点などがあってはなりません。一つの所でもいいかげんな所があると、一字全体が悪く見えます。一字全体を不注意に書いてしまうと、全体がいい加減なものになってしまいます。
(広くこれを申し候わば、浮雲滝泉の勢、龍蛇の宛転たる姿、老松の屈曲せる木立ち、これ等然しながら手本なり。古賢の筆仕いただこれにて候。羲之が用筆の図にかように引き枯らして候う点を、万歳の枯藤と申して候。)
ひろくこれを外の例にたとえますと、浮雲や滝泉を思わせる横画の形、龍や蛇のうねるとめぐる姿を連想させる曲線、老松の曲がりくねった木立にみえる縦画の形などの自然の姿がそのまま手本になります。古の能書たちの筆遣いは、ただ自然を手本としたのです。王羲之の用筆の図に、今述べてきたような筆遣いで書いて老木を思わせる線を、万歳の枯藤と申しております。
(これ等にて候。御心得有るべく候。)
筆勢が生きているとは、これらのことです。ご会得ください。
(所詮、能筆の手跡は、生きたる物にて候。精霊魂魄の入りたる様に見え候うなり。)
つまり能書の筆跡は生き生きとして生物のようです。心や魂の入っているもののように見えます。
(さ候えば、字勢分よりも大に見え候。これは用を具足したる故にて候うなり。)
ですから、字の大きさは実際の大きさよりも大きく見えます。これは、筆の働きが十分にそなわっているからでございます。
6,邪僻を離れて、正しい姿をひたすら追い求めるべき
(邪僻を離れて、正しき姿を専らにすべき事)
邪僻を離れて、正しい姿をひたすら追い求めるべきこと
(この道を知らず、口伝を受けずして、なまじいに道にふける輩、多く正路にかなわず、必ず邪僻を起こすなり。)
昔の優れた書家たちの筆遣いの方法を知らず、口伝を受けず、どっちつかずの態度で書の道にたずさわっている者は、多くの場合、正しい道からはずれて必ずよこしまなかたよった心を起こします。
(古筆を見ても、極めてなびやかに美しき所をば習わずして、達者の筆勢を振い、眼前の風流たる所の目遠き様を、請い願いて写さんとするなり。返す返す説くべかざる事なり。)
古筆を見ても、極めて自然でおだやかな美しい所を学ばずに、上手な振りをして威勢の良い筆遣いをし、一寸見ると華やかに見える工夫をこらした目新しさを求めて書き写そうとするのです。この道の真意は、どうしても言葉では言い表せないところです。
(そのくらいに至りぬる上の所作は、ともかくも自在なり。何と書きたるも殊勝なり。)
能書の位置に到達してしまってからの書きようは、いずれにせよ思いのままです。どのように書いても優れた文字です。
(これを悪しく習い候えば、正しき所をば写し得ぬままに、きと目にたつ所を似せ候う事、極めて悪く候うなり。)
これを正しい道からはずれた習い方をしますと、正しい書法を習得することができないで、一見して目立つところを似せるだけとなってしまい、極めて悪くなるのです。
(ただいささかも異途に目を掛けずして、一筋に正路に従いて、正しき所を習い書き候えば、その筆に達し候いぬる後は、彼の自在無窮の体も、心に任せて書かれ候うなり。)
異様な書法に目を向けないで、ひたすら一筋に正しい道に従って、正しい基本を習いますと、その筆遣いに熟練しますが、そのあとは古筆優れたの自由で伸び伸びとした姿も、心のままに書くことができるようになります。
(曲折風流を本とし候えば、更に風流曲折も、麗しく写されず候。)
目先がちょっと変わっただけの趣を基本としますと、本当に正しく美しい趣としての変化も、美しく書き写すことができません。
(見知らず候う人は、其の体ばかりを浅く見なして、相似たりと見候えども、道を知りたる眼の前にはあらぬ物にて候うなり。)
見て分からない人すなわち鑑識眼のない人は、その見えた姿だけを単純に似ていると見ますけれども、書の道の本質をわかっている人の鑑識眼から見れば、似ても似つかないものです。
(美しからんとて、筆を繕いて、わななき書きたれども、弱くかわゆげにこそ候え、一切美しくは見えず候。また、強からんとて、筆を紙に強く当て、筆を悪しく仕い候えば、ただ狼籍に荒れたる物にて候。更に強き所無く候うなり。)
美しく書こうとして、筆を整えてふるえるほど懸命に書いても、か弱く、見るに堪えないもので、まったく美しくは見えません。また、強く見せようとして筆を紙に強く当てるのですが、筆を下手に使うので、ただ乱暴で乱れたものになります。さっぱり強いところがありません。
(かくのごとき事を、外道の邪見などは申し候。道の魔障にて候。)
このようなことを、「外道の邪見」すなわち「正しい道以外のことに従うよこしまな考え」などと申します。これは正しい書の道のためには障害です。
(この事に限らず、この道その実を申し候えば、仏法の悟りより起こりて、世俗の技芸に出で候いては、管絃、音曲、詩歌、何れも何れも、諸の道の邪正これにて候。)
書道に限らず、芸道は、実は仏法の悟りから起こったものです。仏法の悟りから起こって、世間の技芸などのようなものに出現しては、管絃、音曲、詩歌などとなり、どれもこれも、諸芸術での邪僻と正路が現れるのはこのことです。
(用捨あるべく候。一切の事、その理二は候わず、その悟りに一にて候。されば、万法さながら実相の一理にて候なり。)
何を本質とするのか、よろしく取捨選択ください。全ての事に、二つの道理はありません。その悟りは一つです。だかた、あらゆるものは外にあらわれてはいろいろな形をとるけれども、その真実のすがたは宇宙の本体という一つのものに帰するという仏法の思想と通じます。
(この二か条、殊に詮要にて候。よくよく御心得有るべく候。)
第五条と第六条の二か条は、とても重要です。よくお心掛けください。
7,異様の字を好んではならない
(異様の事を好むべからざる事)
異様のことを好んではならないこと
(初心の時、器量ある人、左字・倒れ字・うつぼ字等、筆に任せて書き候う事、世に興有りてうらやましく覚え候うなり。)
初歩のころは、腕前のある人が、左字(左手で書いた裏返しの文字・倒れ字(狂草)・うつぼ字(割れた筆で点画の中を空にするように書いた文字)などを、筆にまかせて書くのを見て、たいそう趣があるとうらやましく思うものです。
(従いて、これを書くに、その骨あれば、人もこの事をもてなし、我も興に乗るの程に、一向これが正宗になりて、本体の稽古は次になり、返す返す斟酌すべし。)
したがって、そのような字を書く才能があれば、世間の人もこれをもてはやし、自分自身も興趣にのってしまって、まるでそれが本筋のようになり、本来の稽古は二の次になってしまうので、よくよくそのようなことは差し控えてください。
(かかる事を好む人の手跡は、さほどの事を書きたるは、さように見ゆれども、極信なる清書は、いかにも僻事書きたるには、劣りなり。)
このようなことを好む人の筆跡は、ちょっとしたものを書いたときは、一応立派そうに見えるが、厳格なものを書いた清書などはどうしても自分の力の劣ったのが現れます。
(甚だ本意無きなり。)
これははなはだ残念なことです。
(これを好み用いるは、易き事なり。)
これらの異様なことを好んで用いるのは容易なことです。
(ただ幾度も、麗しく正しく書く事、大事なり。)
けれども、ただひたすら何度も美しく正しく書くことが大事なことです。
(大道は遠くして随い難く、邪径は近くして踏み易く覚え、殊に器量の人のありぬべき事なり。よくよく謹慎すべきなり。)
入木の正しい道は遠く、また追い求め難く、よこしまな道は近く歩みやすく感じ、そういう意味で才能のある人のあってはならないことです。ようよく慎まねばなりません。
(弘法大師は、大唐にて左右の手足、並びに口に筆を差し挟みて、五行の字を一度に書きて、五筆和尚の名を得たり。)
弘法大師(空海)は、唐の国で、左右の手足、および口に筆をはさんで、五行の文字を一度に書き、五筆和尚の名を得ました。
(日本にては、応天門の額を門上に掛けて後、応字の上の円点を下より投げ加えられたり。)
日本に帰ってきて、応天門の額を書きましたが、門の上に揚げて後、応の一画目の点の書くのを忘れたことに気づき、下から筆を投げ上げて書き加えました。
(大権の垂跡なり。入木の達者なり。)
仏様が仮に日本の地においでになって人間の姿になられたのです。大師は書道の達人であります。
(たとい権者に非ず候うとも、大師ほどの能筆ならば、いかで不思議を現ぜざらむ。たとい能筆の達者ならずとも、権者現化として、自余の不思議多く候えばもちろんなり。)
たとえ仏様でははなかったとしても、弘法大師ほどの能筆であれば、どうして先に紹介した不思議な逸話を実現しえないでしょう。実現できるのです。反対に、たとえ優れた書の達人でなくても、人間界に現れた仏様として、この逸話のほかにも不思議な逸話が多いので、書についての不思議な逸話も実現しうることはいうまでもありません。
(今人末代に及びて、かくのごときの跡を心に掛くべからず候うか。)
現在の人は、後世に生まれて、このような不思議な事跡を、肝に銘じなければなりません。
(大文字など時々書き候う興有る事なり。また字の勢も出来、かつまた、壁字等には、御用の事も有るべく候。)
大きな文字などを時々書くのは、興味がわいてよろしいことです。また、それによって筆の勢いも出てきますし、それにまた、壁字などを書かれるご用もおありでしょうから、好都合なことです。
8,楷書・行書・草書について
(真・行・草字の事)
楷書・行書・草書のこと
(まず行字を御習いあるべく候。行は中庸の故なり。)
まず、行書をお習いになるべきです。行書は楷書と草書の中間の書体だからです。
(点を略さずして、筆体を行に書きたるは行の真なり。)
点画を簡略化しないで、字体を行書風に書いたのは「行の真」です。
(点を略し、草の字作りをも書き交じえて、行に筆を仕いたるは行の草なり。)
点画を簡略化して、草書の字体をも書きまぜて、行書風に書いたのは「行の草」です。
(すなわち、通用稽古のためよろしきなり。)
すなわち、行書の用筆は楷書にも草書にも通用し、稽古する上では都合がよいのです。
(いささか行の字を習い得て後、草をも真をも学ぶべきなり。真は行・草に通ぜず、草また真・行に通ぜず候うなり。)
はじめに行書をある程度習ったあと、草書を、または楷書をも学ぶべきです。楷書の用筆は、そのまますぐには行書・草書に通用しませんし、草書の用筆はまた、直ちに楷書・行書に通用しません。
(真は一々の点を引き放ちてこれを書く。草は点も字も連続して兼ねたる体なり。)
楷書は一画一画をつづけないで引き離して書きます。草書は点画も文字も連続して書き、あるいは二つの文字を一つに兼ね合わせるようにして書く書体です。
9,お稽古の進歩の度合いが表れる
(御稽古の分限露顕すべき事)
お稽古の進歩の度合いが表れること
(五日十日などに一度、御本の字を暗によくよく執して遊ばされ候いて、月日を書き付けられて置かるべし。後々ご覧合せられ候わば、勝劣分明なるべく候。)
五日とか十日ごとに一度くらい、お手本の字をご覧にならないで書けるように熱心に練習なされ、その月日を書きつけておきなさい。後日、ご覧になれば、その文字の良し悪しがはっきりといたします。
(かつは、未熟の所をも、よくよく御覧定せられ候いて直され候えば、次第に御意のごとくなるべく候うなり。)
その上、下手な所もよくよく見極めて、ご自分で直されますと、次第に意図にそった文字が書けるようになるでしょう。
(またさように取り置かれ候わんを、細々に下し給い候いて、所存を申し上ぐべく候。)
また、そのようにして置かれたのを、一つ一つ私の方におよこし下されば、それについてのご批評を申し上げます。
10,稽古の間、調子のいいときと悪いときがある
(稽古の間、善悪常に相交わる事)
稽古をしている間に、常に善悪が起こってくること
(初心の時は、手習いをし候えば、にわかに筆も詰まり、字形も本に似ず、およそ不思議の事必ず必ず出で来候。)
初歩のうちは、手習いを致しますと、急に筆が渋滞し、字形も手本に似なくなります。必ず思ったように書けなくなるものです。
(この時、ものぐさく成りて、退屈の所存起こり候うなり。それに目を掛けずして、ただ同じ様に稽古候えな、四、五日ないし十日こと候え、またよくなり候。今度は、以前によく書き候うように覚え候いつるよりも、なお優れ候うなり。)
その時に、なんとなくいやになり、怠りの心が起こります。そのようなことに目もくれずに、ただ、同じように稽古を続けますと、四、五日から十日ぐらいたつとよくなります。そうなると、今度は以前によく書けたように思ったものよりも、さらに優れた文字が書けます。
(かくのごとき数遍に及び候。)
このような状態を何回か繰り返して上手になるものです。
(初心の程は、更に断絶せざる事なり。やがて一段一段かさの上がる体にて候うなり。)
初心のうちは、それに加えて休まないことです。「繰り返す」「休まない」という事を心掛けていると、そのうちに一段一段と腕前が上がっていくものです。
11,お稽古の時間について
(御稽古の時分の事)
お稽古の時機のこと
(毎日一時二時など、しばらく御沙汰あるべく候。)
習い始めた当分の間は、稽古の時間を、毎日一時とか二時とかお定めください。
(およそ万機御会計、他事御稽古差し置かるべきにあらず候。これをもって本とせらるべからざるの条、もちろんただ時折有るべく候。)
およそ、政治上のことで取り込むことがおありでしょうが、政治以外のこととしてお稽古を後回しにしてはなりません。お稽古を天皇の本務とすべきでないことはもちろんですが、ただお稽古には時機があるのです。
(ただし諸道稽古の法、しばらく励みて功を入れ候わねば、成り難く候うなり。一、二年、せめては二、三百日も、まずいささが火急に御沙汰然るべく候。)
一般に、諸芸道の稽古の方法として、ある期間は励んで練習を積まなければ大成し難いものなのです。まず一、二年、せめて二、三百日ぐらいでも、まず少しばかり取り急ぎ計画をお定めになることがよいのです。
(それそののちようように御沙汰、相違あるべからず候なり。)
そのようにして、基礎の力がついたならば、そのあとは稽古の時間をいろいろにお定めになっても間違いはありません。
12,手本を選ぶこと
(手本用捨の事)
手本を選ぶこと
(三賢等の筆なればとて、初心の人、先達に談せずして、この本面白し、彼の字興有りとて習うも、時に従い筆仕い同じからず候。)
三賢(三跡のこと)すなわち小野道風・藤原佐理・藤原行成の筆跡だからといって、手本とするについて注意しなければならないことがあります。初歩の人が、先生に相談せずに三賢のこの手本はおもしろい、この字は興味があるとかいって習っても、上達するとは限りません。三賢の立派なしょでも、時によって筆遣いは同じではありません。
(何としても書きいだし候えば、殊勝の物にて候えども、手本のため、これを習うべき風体も候。)
何はともあれ、達人の書として書かれているものであるので、すばらしいのですが、お手本として習わねばならない書風もあります。
(初心の人、これを習うべからず候う筆体も候うなり。)
初歩の人では習ってはならない筆体もあります。
13,手本が多いのは大切である
(手本多き大切の事)
手本が多いのは、大切であるということ
(多本歴覧大切の事に候。)
多くの手本をご覧になるのは大切なことです。
(御稽古は、御本を定められ候いて、数本を御覧候えば、御才学になるべく候うなり。)
お稽古には、多くの手本のなかからどれか一つの手本をお決めになって、それを基本として習い、その他に数種類のお手本をご覧になって参考にいたしますと勉強になるでしょう。
14,現代は手紙を手本とすることが多いが、そうするべきではない
(当世多く消息を手本とす。然るべからざる事)
現代は手紙を手本とすることが多いが、そうするべきでないこと
(近日手本所望のともがら、多分は消息なり。)
近ごろ、手本を欲しがる人たちは、多くは手紙です。
(所存にたがうといえども、人の所望に従いて、多くもって書き与うるものなり。これしかしながら、案内を知らざる人の所為には、一おうまた、かくの如き道理にて候。)
私の考えに反してはおりますが、人の求めに応じて、多くの場合は書き与えております。これはしかし、手習いのあり方を知らない人のすることとしては、一応はこうするのももっともなことです。
(かのともがらが意に思う様を察し存じ候うに、能書に成りて手本をも書き、色紙形、諷誦、願文をも清書せん事は不審なり。)
そのような人々の考えを推察いたしますと、書の達人となって手本を書いたり、色紙型、諷誦文、願文などをも清書しようというようなことは考えていないようです。
(ただ指し当たりて、消息一通、なだらかに書きたらんに足るとなすべし。すなわち、消息を習うべしと存じ候うか。)
ただ、さしあたって、手紙を一通さらさらと書くことで十分としているのでしょう。だから手紙だけを習えばよいのだと思っているのでしょうか。
(この条、ひとえに道を知らざる故なり。)
このようなことになるのは、まったく書の道を知らないのが原因です。
(まずこの道をばいかに意得、我が器量をばいかに存じて、みだりにその法を定めて、分斉を置くべきぞや。)
まず、この入木道をどのように心得、自分の才能はどの程度であるかを理解して稽古をするべきで、勝手気ままに習い方を決めて、それに自分を合わせるべきではないのです。
(一切の事、稽古の道の、更にその際限なき事なり。)
すべて稽古の道は、行きつく果ての無いほど奥深いものです。
(仏法を学するも、大師先徳の已証を探り、仏知仏見を悟り極めむと学び候えば、更にその極め無き事にて候。)
仏法を学ぶ者も、仏や有徳の先人の悟りの跡を探り、仏の奥深い知恵、通達した見識を悟り極めようと学びますので、更にその行きつく果ては無いのです。
(世間の技法に及びてまた同じかるべく候。)
世間の技芸についてもまた同じでありましょう。
(消息と申す物は、あながちに筆体をかい繕わず、ただするすると書き下し候う間、古賢の筆も手本に成りぬべきは、希有の物にて候。まして当世の手跡、沙汰の外の事にて候。)
手紙というものは必ずしも字形を整えず、たださらさらと書き下しますので、古賢の書いたものでも手本になるのは極めてまれです。まして、現代の人の筆跡は論外です。
(しかるを、我は消息を習わむとて、能筆の書き捨てたる消息、拾い集めて習学候うは、更に消息をもなだらかに書き得ず候。)
そうであるのに、「自分は手紙を習おう。」といって、達人の書き捨てた手紙を拾い集めて手習いをしていますが、そのようなことではさっぱり手紙さえもすらすらと書くことはできません。
(まずいかにも道に志を深くして、清書の本を習い候わむに、数奇もすたれ、器量も及ばず候うは、さて止まり候うとも、さすがに一しきり習いて候わんに、功むなしかるべからず候えば、能書までならず候うとも、消息などは、見苦しからぬ程に書き候うべく候。)
まずぜひともと、深く入木道に志して清書の基本を習いますと、たとえ書に寄せる心も衰え、才能も及ばなくなり、そこで腕前が止まったとしても、一時期盛んに習っていたので練習の積み重ねは無駄ではなく、達人にまではならなくでも、手紙などは見苦しくない程度に書くことができます。
(初めより消息と出で立ち候わば、消息をも書き得ず候うなり。)
初めから手紙を書くことを目標としてお稽古をしますと、手紙さえも書くことができなくなります。
(太宗の詞に、「法を上に取る故に中となる。法を中に取る故に下たることを得。」ともうすこともこの心なり。)
太宗の言葉に、「目標を上に置けば中ほどにとどまり、中に置けばせいぜい下程度にしか達しない。」とあるのもこの意味です。
(手本とて往来など書くは、ただ書状などには似ず、いささか筆をかい繕いてこそ書き候えども、それも消息にて候う間、いかにも清書の物には、筆仕いも違い候うなり。)
手本として「往来物」などを書くのは、通常の手紙などとは違って、少しは筆を整えて書きますが、それも手紙ですので、どうしても清書の物に比べて筆遣いも違います。
(さ候えば、上古の手本三賢等の筆は、皆文集の詩にて候。)
ですから、昔の手本である三賢の書は、みな『白氏文集』の詩でございます。
(消息を手本とて書きたるは、いたく見えず候うなり。)
手紙を手本として書いたものは、ほとんど見られません。
15,筆について
(御筆の事)
筆のこと
(御手習いにも、良き筆よろしく候うなり。)
お手習いの時にでも、良質の筆は良いものです。
(御筆、手本の筆に相違し候えば、字形も似ず候。御手本に相応の筆よろしかるべく候なり。)
お筆が手本と違っていますと、字の形も似ないものです。お手本にふさわしい筆がよろしいのです。
(およそ筆を用いる事、料紙により候うなり。)
一般に用いる筆は、料紙によって使い分けます。
(打紙にはの卯の毛、ただの紙には鹿の毛にて候。壇紙には冬毛、杉原には夏毛、綾にも夏毛。布には木筆、木筆は橇木にてこれを作る。)
打紙(打ちたたいてなめらかにした紙)にはうさぎの毛、普通の紙には鹿毛であります。壇紙(厚手で白い)には冬毛、杉原紙(鎌倉時代、播磨国杉原で造られた紙)には夏毛、綾(綾織物)にも夏毛、布には木筆、木筆は橇木で作ります。
(上古は多く夏毛を用う。一切に通用し候。)
昔は多くの場合夏毛を用いていました。すべての料紙に通じて使えるからです。
(昔の夏毛は殊勝に候いき。当世の夏毛悪く成りて、先も候わずいたずら物なり。)
昔の夏毛は優れていました。現在の夏毛は悪くなり、毛先もよく利かずつまらないものです。
(すなわち、杉原の外はただうさぎの毛を通用よろしく候うなり。)
すなわち、杉原紙のほかはすべてうさぎの毛を通用させてよろしい。
(大方筆の毛も悪ろく、筆人も候わず候う間、当世は吉き筆候わず候うなり。)
総じて筆の毛も悪く、優れた筆匠もいないので、現在は良い筆はございません。
16,墨について
(墨の事)
墨のこと
(御稽古には、藤代墨相違あるべからず。)
お稽古には、藤代墨を使えば間違いありません。
(唐墨当時希有に候うか。)
唐墨は、現在滅多にないようです。
(御手習いに枝葉に候うや。)
お手習いに唐墨が良いというのは枝葉末節です。
(唐墨をも悪しく置き候えば、やがて損じ候。包まずして、塗り物に入れ候いて、常に拭い候。)
いくら良い唐墨でも、取り扱いが悪ければすぐにでも痛みます。包まずに塗り物に入れておき、使い終わったら常によく拭くようにします。
(最上の秘事なり。)
これは最上の秘事です。
17,料紙について
(料紙の事)
料紙のこと
(細々の御手習い、檀紙相違無きか。)
こまごまとしたお手習いには、檀紙がよろしい。
(真のものは、打紙よく候うなり。)
楷書には打紙が適当です。
(およそ常に何をも用いらるべく候。)
普通には、常にどのような料紙でもお使いください。
(初心の時は、常に書き付け候わぬ紙には、書きにくく候う間、調練のためには、何紙にも書き候うなり。)
初歩の時には、常に書き慣れていない紙には、書きにくいものなので、訓練のためには、どのような紙にでも書かねばなりません。
18,入木道の一流
(入木道の一流、本朝は異朝に超えたる事)
日本の入木道の一つの流れは、中国よりも優れていること
(弘法大師入唐の時、王宮の壁字、王羲之筆の一間破損す。其の仁無きによりこれを闕く。)
弘法大師が唐の国に行ったころ、王羲之が書いたという王宮の壁字の一間が破損し、それを書くことのできる人がいなかったので、破損したままになっていました。それを弘法大師が天子の勅を奉じて書きましたが、それは晋代より唐朝に至るまで、永い間絶えていた書の道を弘法大師が再興されたのです。
(大師勅を奉じて書けるは、晋代より唐朝に至るまで、久しく絶えたる道を興されし上に、また道風が申し文にも、万里の波濤を隔てて名を唐国にはすと書きたり。文時・匡衡等が文にもこの詞を載せざるか。)
その上に、また、道風の申し文にも、「万里の波濤のかなたの唐国にまで書名を馳せた。」と書いてあります。文時・匡衡などが書いた文章にも、このことを書いているようです。
(測り知りぬ、この道本朝に抜群の人多しという事を。)
これにより、入木道は日本に抜群に優れた人が多いということが推測できます。
(これによりて諸道、唐朝の風を移すといえども、手跡の事は、唐書の説、あながちに、この口伝の外他説を用いず候。)
この事実によって考えてみますと、書道以外の諸芸道は、唐朝の習わしを移しているのですけれども、書道に関しては中国の書物の言うところをそのまま用いてはおりません。この口伝すなわち世尊寺流以外の他の説は用いていないのです。
(従い候いて、近来宋朝の筆体は多分神妙にあらず候。)
近ごろ宋朝の書風が伝わり流行していますが、その多くはよろしくありません。
(当世文学のともがら、宋朝の筆体を摸する間、あるいは懐紙、あるいは綸旨・院宣にすこぶる異体しかるべからざる事に候うなり。)
現在学問をしている人々は、宋朝の書風をまねているので、懐紙とか綸旨・院宣とかに、たいそう変わった書風が見られますが、よろしくありません。
(また「舊は旧、盧は虍」かくのごときの約束の抄物字は用い難き事なり。聖教にも、かくのごとき抄物字多し。「菩薩は▯、菩提は▯」等なり。しかりしこうして抄物の外は書かざるなり。)
また、「舊は旧、盧は虍」のような約束の抄物字(点画を省略した文字)を用いてはなりません。仏典にも、このような抄物字が多くみられます。「菩薩は▯、菩提は▯」などです。けれども、抄物の外には書いておりません。
(本朝は、つねに事跡を追いて国風を失わざるなり。)
日本では、常に過去の事跡を受け継いで、国風を失いません。
(異朝はしからず。)
中国は違います。
(先代の旧風を改めて、当世の風俗を流布せしむるなり。すなわち、筆体も皆改むるなり。硯の作り様にも古今の事異なるなり。)
前代の旧風を改めて、新しい時代の風俗を広めさせます。もちろん書風もみな改めます。硯の作り方でも、昔と今とでは違います。
(本朝は、魚養、薬師寺の額を書く。これ能書を用いる最初なり。一筆に書き候由申し伝えられども、今これを見るに趁字のごとし。まことに不可説の体なり。)
日本では、朝野魚養が薬師寺の額を書きましたが、これは朝廷が公事に能書を登用した初めです。一筆で書いたと伝えていますが、今これを見ると後の世尊寺の流れと合う字です。誠に言葉で言い表せないほどすばらしい書体です。
(この筆体もただ皇后、中将姫当麻の曼陀羅感得の人なり、弘法大師、嵯峨天皇、橘逸勢、敏行、美材等までおおむね一体なり。)
その日本におけるすばらしい書風も、まったく光明皇后、中将姫(当麻寺の曼陀羅を感得した人)、弘法大師、嵯峨天皇、橘逸勢、藤原敏行、小野美材などまで、大体は同じ書風なのです。
(筆は次第に倒れたるように成るなり。)
筆はだんだんと倒れたようになっていきました
(そののち聖廟抜群なり。聖廟以後野道風相続す。この両賢は、筆体相似たり。)
その後は、菅原道真は抜きんでております。菅原道真の後は、小野道風が受け継ぎました。この二人は書風が似ています。
(佐理・行成は、道風が体を移し来たる。)
藤原佐理・藤原行成は、小野道風の書風を受け継いできました。
(野跡・佐跡・権跡、この三賢を末代の今に至るまで、この道の規摸として好む事、面々かの遺風を摸するなり。)
野跡(道風)・佐跡(佐理)・権跡(行成)、この三賢は、後の世の現代にいたるまで、入木道の規範として好まれていますが、それは、三賢のそれぞれが古代の遺風を伝えているからです。
(すなわち本朝の風は、相替らざる者なり。)
このように日本の書風は、昔から変わっていないからなのです。
19,日本では書体は一つですが、時代によって書風がはっきりしている
(本朝は一体なれども、時代に付いて筆体分明の事)
日本では書体は一つですが、時代によって書風がはっきりしていること
(弘法大師前後の程の手跡、大略一様なり。道風以後また、各々野跡の風なり。)
弘法大師前後のころの書風は、だいたい一様です。小野道風以後は、またそれぞれ道風の書風です。
(行成卿は、道風が跡を摸すといえども、いささか我が様を書き出せり。その後一条院の御代よりこのかた、白川・鳥羽の時代まで、能書、非能書も皆行成卿が風体なり。)
行成卿は、小野道風右の書風に倣っていますが、わずかながら個性を発揮しています。その後、一条天皇の御代より以降、白河天皇・鳥羽天皇の御代まで、能書も非能書も皆行成卿の書風です。
(法性寺関白出現の後、天下一向この様に成りて、後白川院以来時分かくのごとし。あまつさえ後京極摂政相続の間、いよいよこの風盛りなり。後嵯峨院ころまでもこの体なり。)
法性寺関白忠通が現れてから、天下はことごとく法性寺様の書風となり、後白河天皇以来、しばらくの期間その書風でした。その上、後京極摂政良経が法性寺様を受け継いで、ますます法性寺様の書風が盛んとなりました。後嵯峨天皇のころまでも、法性寺様の書風でした
(その間に弘誓院入道大納言等、いささかまた体替りて、人多く好みて用いるか。およそは法性寺関白の余風なり。)
その間に、弘誓院入道大納言教家などは、いささかまたその書風に違いが出て、多くの人々が好んで習っていたようです。けれども大体は法性寺関白の書風を受け継いでいました。
(法性寺関白は、また権跡を摸するなり。)
法性寺関白は、また、権跡すなわち行成卿に倣ったのです。
(伏見院の御筆、近来盛りにこれを賞翫し奉る。なかんずく仮名は一向その様なり。この仮名も、法性寺関白以来、照念院関白の筆体なり。これを摸されて、御天骨にてあそばしいだされたるなり。真名は佐跡を摸されしか。)
伏見天皇の御筆跡は、近ごろ盛んに御賞翫申しあげております。それらの中で仮名はとりわけ行成卿の書風です。この仮名も、法性寺関白忠通以来、照念院関白兼平に伝わっている書風でもあります。それに倣われて、生まれついた才能により一つの風趣をお出しになられました。漢字は佐跡を模範となされたようです。
(これ等次第に成り来たるよう御分別なされる事、次に申し出で候うなり。)
これらのことが、次第に変化してきた様子をご理解いただくために、次の事を申し上げます。
(体を改めず、ただ時代に従いて次第に替りたるように外儀見ゆれども、その実は全く同物なり。)
国風という書の本質は変わっていません。ただ、時代にしたがって次第に変化したように外見は見えますけれども、その実質はまったく同じものであります。
(更に異風を交えず、行能卿以来、今の行忠まで殊に同じ姿なり。)
事新しく異国の書風を交えることなく、行能卿以来今の行忠までまったく同じ姿です。
(よくよく写し得たりと見候うなり。)
よくよく受け継ぐことができたものです。
20,能書を登用なされること
(能書を用いらるる事)
能書を登用なされること
(上古には、物を書き候えばとて、左右無く清書に筆を染めず。その道の先達にも許され、また朝家にも用いられ、書役をも仰せられ候う程に成りて、能書とは申されけり。)
昔は書に巧みだからといって、そういう理由だけで清書を書いてはおりません。書道の先輩にも認められ、朝廷からも登用され書役をも仰せ付けられるようになって、はじめて能書の名を得るのです。
(また随分神妙の手跡なれども、その時分なお勝たれる人あれば、それに押されて名望なし。)
また、とても優れた書き手ではありますが、同時代にその人より以上に優れた人があれば、その人に圧倒されて能書という名声は得られません。
(これもこの故なり。)
このような理由によって、次のような例も出てくるのです。
(公任卿は殊勝なれども、行成卿抜群の同時たる故に、人も用いず。我も思いくたして書役を務めず。)
それは、公任卿は優れた方ではありましたが、同時代に行成卿がより優れていたので、人々からも能書として依頼されることもなく、自分自身でもあきらめて書役を務めませんでした。
(それも定頼卿は、父には劣りたれども、その時に行成卿程の抜群の仁なければ、門殿の額以下書役に随い、その賞に預る。)
そうであるのに、定頼卿は父の公任卿には劣っていたけれども、同時代に行成卿ほどの優れた人がいなかったので、内裏の門や殿舎の額を書いたり、書役となったりして、賞を得ました。
(これにてその意を得べき事か。)
このような例で、能書を用いられることについての事情をおわかりいただけるでしょうか。
(以上三か条は、御手習の要次にあらずといえども、次いでを似て注し申し候うなり。)
以上、十八、十九、二十の三か条は、お手習いをなされる上で直接重要な事ではありませんが、ついでに記録いたしました。
21,最後のまとめ
(右の条々、初心御稽古の詮要、大略かくのごとく候。)
右の条項のとおり、初歩の方のお稽古をなさる要点は、おおよそこのようなものです。
(その外の事は、御学習の間、御不審に付きて申し上ぐべく候うなり。)
そのほかの事で、学習をなさっている間に疑問点が出てきましたらご説明申し上げます。
(また、色紙形、ないし額等の事は、追って申し入れるべく候。)
また、色紙形から始めて額などに至るまでのことなどは、そのうちにご説明申し上げましょう。
(か様の事は、道の大事にて候えども、口伝を受け候いぬれば、おおよその入木の道を得候いぬる上には、中々易き事にて候。)
このようなことは、この道の大事なことですが、すでに口伝を受けていらっしゃいますから、おおよその入木道を体得なさっていらっしゃいますので全く優しいものです。
(ただ返す返すも正路に打ち向きて、稽古を沙汰候う事が、第一難き事にて候うなり。)
ひたすら、正しい道に向かってどう稽古を進めていくかをお決めになることが、第一の難しいことなのです。