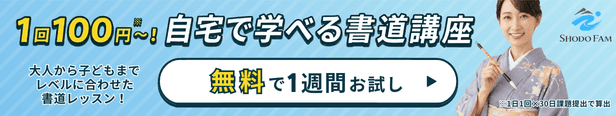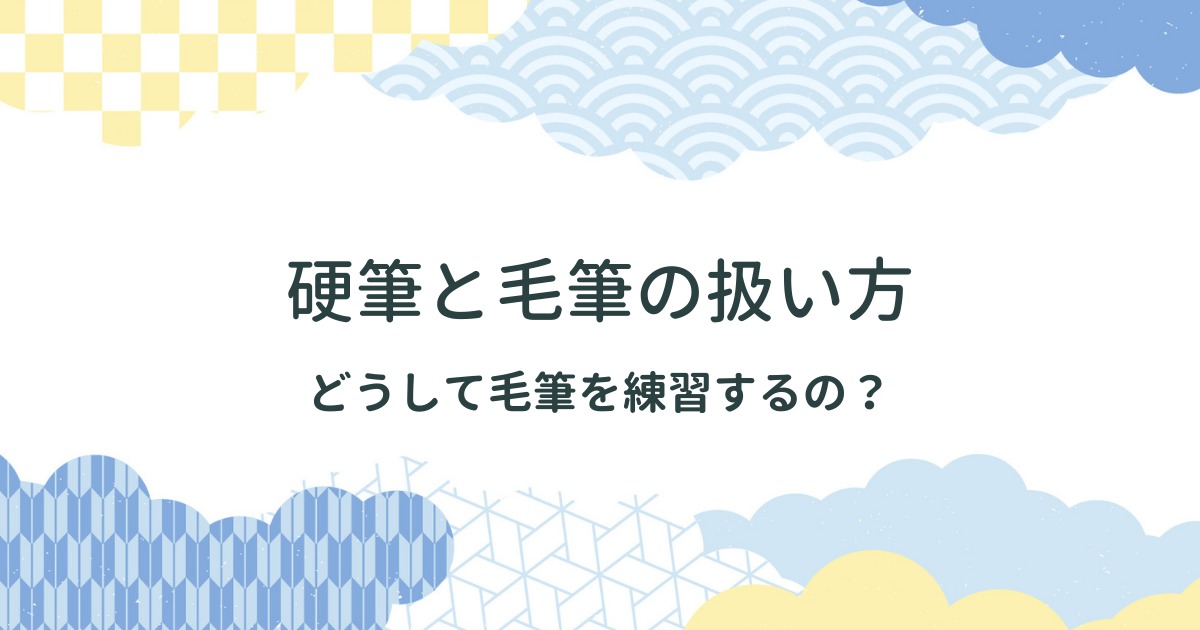小・中学校では書写(習字)の授業で毛筆の練習をします。どうして毛筆を習うのか疑問に思ったことはありませんか?
今回は、習字をしている方にむけて硬筆と毛筆扱い方を確認してから、どうして毛筆を習うのかについて説明します。ついでにそのほかの用具用材(墨・硯・紙)についても書いたのでためになるとうれしいです。
硬筆とその扱い方
硬筆とは鉛筆・ボールペン・万年筆など「先の硬い」ペンのことを言います。おもに書写(習字)の分野で用いられる言葉です。
小・中学校学校の国語には書写があり、通常小学校1,2年生は「硬筆書写」をメインに行い、鉛筆を使用して各種文字の筆順などを学びます。鉛筆は筆圧のかけ方によって、止め・はね・はらいを書き分けることができ、文字の学習に適しています。
硬筆の扱い方
鉛筆
鉛筆は先端がとがりすぎていると書きにくいので、少し丸くして使うと書きやすくなります。硬筆用ソフト下敷きを使用すると、適切な弾力があってより書きやすくなります。
芯の色が濃い鉛筆のほうが太めの芯となっており、止め・はね・はらいなどの筆タッチが表現しやすいため、硬筆書写に使われるのは4B,6Bの場合が多いでしょう。しかし普段の書写指導の場合、小学校低学年では2BかBが適し、高学年および中学校ではHBぐらいが適するでしょう。
ボールペン
ボールペンは携帯に便利で、メモや記録や手紙等の日常の筆記用具として、また、公文書など改ざんできない文書を書くための筆記具としてよく使われています。
ボールペンのような日常生活で用いる筆記用具をそのまま使う硬筆書写は非常に実用性が高く、ペン習字として子供よりもむしろ社会人や主婦、老人の習いごととして定着しています。
フェルトペン
フェルトペンはある程度大きく太く書く文字や、表面がつるつるした用材に書く場合によく使われます。太さや色の種類が多く、油性と水性のものがあり、紙質や筆記面によって使い分けることができます。
先が四角いフェルトペンは、筆と同じように斜め45度で書き始めることで、はね・はらいなどの日本語の文字の点画を表現するのに適しています。ペン先が細いものは、止め・はね・はらいがはっきり書け、手紙にもよく使われます。
毛筆とその扱い方
毛筆は、今から4千年ほど前の殷代で、甲骨文字を刻す前の下敷きを書くときにすでに使用されていました。
毛筆の種類は、筆毛部(穂、筆鋒ともいう)の長さ(長鋒・中鋒・短鋒)、太さ(大筆・中筆・小筆)、材質(剛毛・柔毛・兼毛)、製法(固め筆・さばき筆)などによって分けられます。
小・中学校の書写(習字)では、短鋒や中鋒(穂の長さが軸の直径の4倍くらいを中鋒といいます)を主に使います。剛毛か兼毛で固め筆(穂をフノリで固めたもの)が適しています。
毛筆の使いかた
大筆や中筆は、3分の2以上おろして使います。墨を含ませるときは、穂先に付けるのではなく、おろした部分にたっぷり含ませたのち、余分な墨を硯の縁で落とすようにするのが良いでしょう。こうすることで筆がポンプの役割をして少しずつ墨が下りてくるようになります。点画のつながりや筆圧に注意して、一回の墨つけで一文字または部分を書くようにしたいです。
筆の洗い方
使用後の大筆は、墨のついた部分をよく水洗いします。教室では、失敗した紙で余分な墨を落とした後、あらかじめ水を入れておいたペットボトルの中で洗うようにすると、席を立たずに後始末ができます。
筆の保管方法
筆は、筆巻きに巻いて持ち運ぶか、保管するときは筆巻きから取り出し、通気のよいところでよく乾かします。湿ったままにしておくと、夏期はカビが生えたり、筆毛が抜けたりするので気を付けましょう。
小筆
小筆は、穂先だけおろして使います。使用後は、水を含ませた紙や布で墨をよく拭き取るようにし、穂先を整えて保管します。
毛筆を習う理由
硬筆筆記具が一般に広まり始めたのは明治期後半になります。毛筆に比べて硬筆の歴史は極めて浅いため、毛筆の書き方を参考に硬筆の書き方がなされてきています。
そのため、毛筆によって文字の書き方を学ぶことにより、点画の書き方や書写のリズムを効果的に習得させることがでると考えられています。
つまり、毛筆は硬筆を書くときに役立つように行われているのです。
墨について
墨も殷代から使用されています。油や松を燃やして出る煤をにかわで練って作られます。型に入れて固めたものを固形墨、液状のものを液体墨と呼びます。
朱墨は、辰砂(水銀と硫黄との化合物)から作られるものと、朱色の顔料から作られるものとがあります。
また、弔事(葬儀)の時には薄墨を使います。これは涙で墨が薄まってしまったためとされています。慶事には濃い墨を用い、弔事には薄い墨を用いるのが一般的です。
墨のすり方
固形墨は硯の面に対して直立または傾斜させて硯の面全体を使って、前後または「の」の字を書くように磨ります。水を硯の「海」にあらかじめ溜めておいて、そこから汲みあげるのではなく、水差しやスポイトで「陸」に水を少量たらし、濃く磨りあがったものを「海」に溜めておくようにします。
にかわがノリの働きをするので、磨りかけの固形墨を硯の上に置いたままにしておくと固形墨が硯にくっついてしまうので注意しましょう。
使用後は水分をよく拭きとっておかないと、ひび割れをおこすおそれがあります。
硯について
硯は、古いものでは、秦時代の石制の硯が見つかっています。大きく分けて唐硯(中国製)と和硯(日本製)があります。使用後は墨をよく拭き取るか水で洗うようにしましょう。硯の下に雑巾を置いておくとよいです。
紙について
紙は、古くは前漢時代のものが発見されています。おもに植物の繊維を漉いたもの。
今日では、手漉きの紙は貴重になり、多くは機械漉きの紙が使われていますが、紙の寿命は手漉きの方がずっと長いです。
書道で使う紙は、使用するときは紙の表裏を間違えないようにしましょう。つるつるしている方が表になります。
練習した半紙は、新聞紙の上に広げておいておくか、紙ばさみに挟んでおくと場所を取らなくて便利です。
まとめ
ここまで硬筆と毛筆の扱い方を中心にその他用具用材も説明してきました。
それぞれの筆記具の特性を理解しておくことで、紙への書きやすさや伝達効果を考ることができ、目的に応じて筆記具を選択できるようになります。