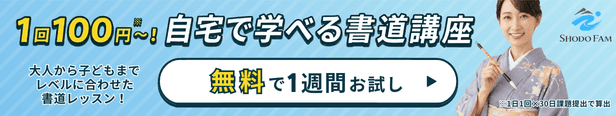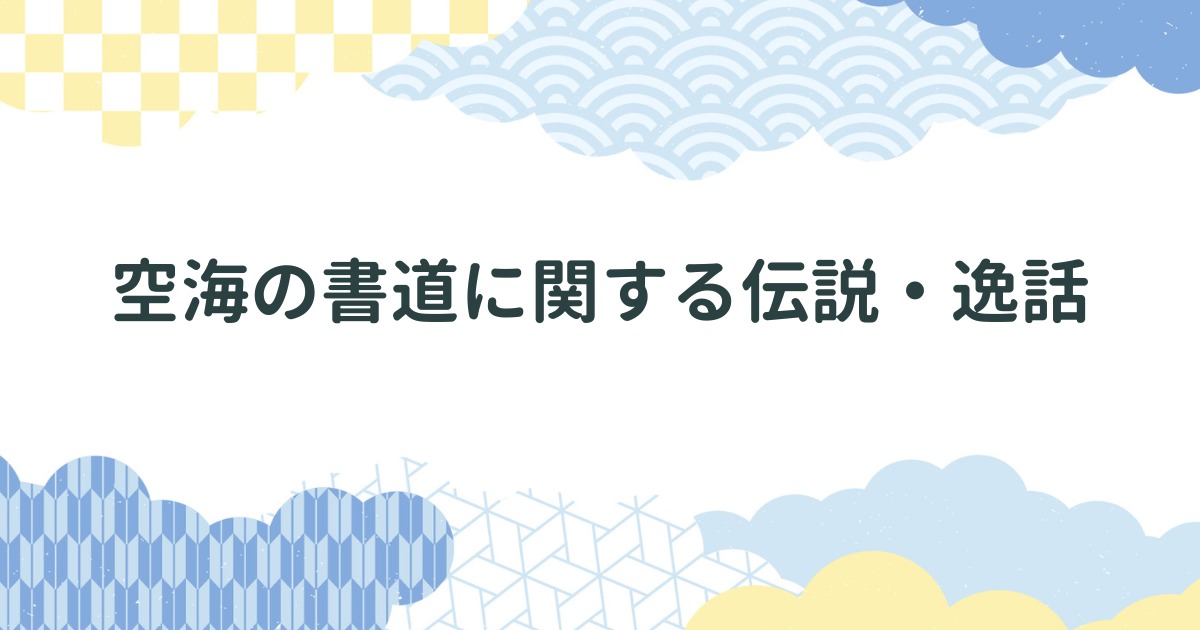空海にはいろいろな伝説や逸話があります。
今回は空海の書道に関する伝統や逸話を紹介したいと思います。
空海は筆を選ばず
「空海は筆を選ばず」ということわざがあります。
これは空海がとても字が上手なので、書をかくときどんな筆を使ってかいても、その筆を自由に使いこなしてよい字が書けるという意味であると考えられます。
実は中国にも昔から同じような話があり、唐時代の欧陽詢という書の上手な人がいたのですが、この人も紙や筆を選ばないでよい字をかくことができたということを、当時欧陽詢とおなじく書の方面で有名だった虞世南という人が書いています。
宋時代の米芾というまた書が上手な人がいたのですが、この人はいつも道具は良いものを使い、さらに気分がのらないと字を書かなかったと言われています。これは反対の極端な例です。
筆をよく選んでいた記録もある
ところが、空海ののこした文章に『狸毛筆奉献表』というものがあります。これは弘仁3年(812)6月、嵯峨天皇に筆を献上したときの文章です。
その文を読んでみると、「楷・行・草の3つの書体の字を書くための専門の筆あわせて4通りのものがある」と記されています。
そしてその説明には、「書をかくには大小、長短、強柔、斉尖なのを字勢の粗細にしたがって取捨選択するのである」といっています。
これは明らかに文字の書き方において、書体や書写する資料によって細かい区別をたてて筆を使い分けしていたことを示すものです。
また空海に「又春宮に筆を奉ずる啓」という一文があり、その中にも「能書は好筆を用ふ」とあり、また「臨池家にしたがって筆を変える」とあって、筆は篆書・隷書・楷行草によって分けられることをくわしく説いています。
これらの記録から考えてみると、空海は筆を選ばずではなくて、逆に筆をよく選んでいたように思えてきますね。
空海は口と両手両足に筆を持って文字を書いた
空海が唐にわたっていたときのことです。
唐の僖宗皇帝のとき、宮中の御殿を修理したところ、2つの部屋に王羲之の書がかいてあったのですが、一方の部屋だけ破損して文字が消えてしまっていました。
そこで日本の空海が字がうまいというので、さっそく空海に書き直してもらいました。
すると空海は5本の筆をとり、口と両手両足に1本ずづ筆をとって、5行に字をかいたそうです。
しかもその筆跡が王義之の字と区別がつかないほどよくできていたので、「五筆和尚」と呼ばれました。(「古筆談」「本朝能書伝」その他)
これは空海が書をよくしたことを褒めたたえるためにつくり上げられた架空的な逸話にすぎないと思われます。
とくに五筆といって、口と両手両足に筆をとって書くなどという下品なことを空海がするはずがありません。
つくり上げられた根拠のない逸話ですが、空海が書聖の王羲之と対等に比べられているということは、相当かれが崇拝されていたことがわかります。
いろは歌は空海が作った説
空海が生きたのは平安時代初期のころです。そして書道の仮名がもっとも盛り上がったのは平安時代後期です。
空海にまつわる俗説に、いろは歌(いろはにほへと…)とこのひらがなのかな文字は、平安時代前期に生きた空海が作ったという説があります。
これについてはすでに今までに研究が進められていて、現在のところは否定されておちついています。
※いろは歌は空海が作った説は間違い
いろは歌は空海が作った説を紹介しましたが、現在の研究ではこの説は間違いとされています。
いろは歌は七五調四句の和讃の形式をもっていますが、空海のころにはまだこのような形式のものは行われていませんでした。
七五調四句の和讃の形式は、僧・千観(918~984)の「弥陀和讃」から以後のものであるため、空海(774~835)のときにはありえないというのです。
また、空海が書いたとされるひらがなのいろは歌が石刻になって伝わっていますが、ひらがなは平安初期にはまだ十分発達していませんでした。
いろは歌がつくられたのは、平安の後半の10世紀のおわりかた院政にかかるころだという見方が妥当な説とされています。