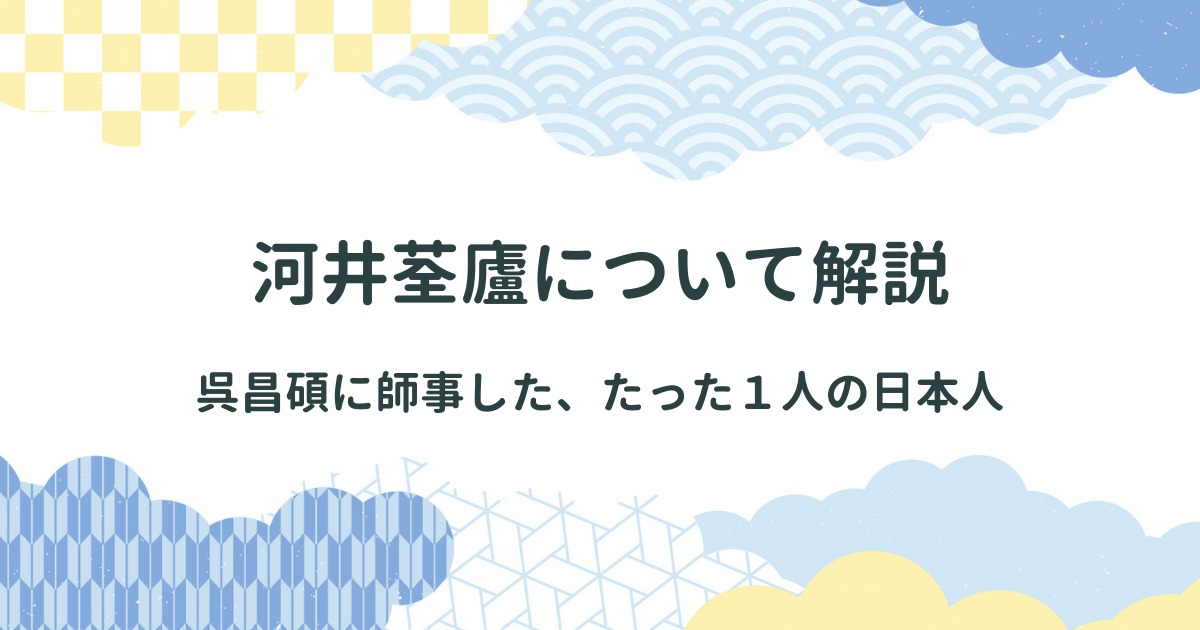呉昌碩は多くの弟子がいましたが、そのなかで日本人の弟子が1人だけいました。
それが河井荃廬です。
荃廬は呉昌碩にあこがれ、呉昌碩門下への入門を望み、それが叶うと毎年のように呉昌碩をたずねました。
今回は、河井荃廬を紹介し、功績や呉昌碩との関係を紹介していきます。
河井荃廬について
河井荃廬かわいせんろ、明治4年(1871)4月22日生まれ。
京都の人。篆刻家。
幼名を得松、名を仙郎、字を子得といい、雅号を荃廬としました。
呉昌碩に直接師事して刻法を学び、呉昌碩が社長をつとめた西泠印社の名誉社員となりました。
また、金石書画にくわしく、日本の書画篆刻界の向上に貢献しました。
太平洋戦争末期、空襲が激しさを増しても自宅は皇居の近くだから爆撃されないと思いこみ、戦禍を逃れようとはしませんでした。
しかし、昭和20年(1945年)3月10日、ついに爆撃に遭い、所蔵する膨大な書画や蔵書などとともに帰らぬ人となりました。
- 1871年0歳
京都に生まれる
- 1890年20歳ごろ
篠田芥津の門に入って篆刻を学んだ
- 1898年28歳
呉昌碩の作風にあこがれ、呉昌碩に宛てて手紙を送る。このとき呉昌碩は55歳
- 1900年30歳
はじめて清(中国)に渡り、呉昌碩の門に入る
- 1903年33歳
東京に移住、金文会をおこす
- 1907年37歳
中村蘭台、浜村蔵六、岡本椿所、山田寒山らと丁未印社をはじめる
「日本新聞」や「毎日新聞」に同志とともに刻印を連載する
- 1927年57歳
師・呉昌碩が亡くなる
- 1945年75歳
太平洋戦争の爆撃に遭い亡くなる
河井荃廬と呉昌碩の出会い
河井荃廬は30歳で清(中国)に渡り、呉昌碩と出会うことになるのですが、そのきっかけは2年前の手紙のやり取りから始まりました。
荃廬が28歳のとき、呉昌碩の作風にあこがれ、呉昌碩に宛てて手紙を送ります。同時に自作の印影も送りました。
呉昌碩から返事が来て、荃廬はまたすぐに2通目を送りました。このように荃廬と呉昌碩の文通が始まりました。
この2通目の手紙の草稿が残っているため、その内容を紹介します。
私は1度貴国を訪問し、先生の門をたたき、教えを受けたいとおもって何年にもなります。ですが、いまだにそれを果たすことができないのは、他でもなく、私はもとより1人の貧乏学生で、渡航費用を出せないのです。とはいえ、数年後には必ずや願いを果たせる時が来るであろうと心中信じております。先生は私といまだ1回の面識さえありませんのに、すでにこれほどまでご厚情をいただき、一読再読して感極まっており、さめざめと涙を流しています。
この手紙の日付は「明治31年(1898)2月24日」となっています。
そして、この2年後の1900年、はじめて清に渡って呉昌碩の門に入りました。
それからほとんど毎年のように、多い時は1年に2回も中国に渡っていました。
呉昌碩は1927年に亡くなりましたが、このとき荃廬は57歳です。
呉昌碩と荃廬の交際は、荃廬が清に渡って以来この年まで常に絶えることなく続けられていました。
昭和6年、61歳のとき、荃廬は西川寧をはじめとする弟子たちと江南に行き、中国に行くのはこれを最後とします。
河井荃廬は書・画・書跡を熱心に収集した
河井荃廬の中国に対する愛情はとても強く、中国に訪れては明清の書画を豊富に日本に持ち込み、収集しました。
ただの趣味の収集ではなく、常に学術的な研究を深めていきます。
30歳代の末年には『談書会誌』の編集にたずさわり、60代の中期から70歳にかけては三省堂の『書苑』をはじめ、『支那名家墨蹟』『南画大成』『墨蹟大成』『増補寰宇貞石図』などたくさんの編集を指揮しました。
師、意外の書画作品を熱心に収集するのに嫉妬する呉昌碩
明清の書画作品の収集に熱心な荃廬は、師匠の呉昌碩からこういうことを言われたそうです。
「缶(呉昌碩)の画は悲庵(趙之謙)に孰れぞ」
(呉昌碩の画は、趙之謙(の画)と比べてどうか)
趙之謙とは、呉昌碩と同じ時代に活躍した書家・画家・篆刻家です。呉昌碩はよく篆書作品を書きましたが、趙之謙も篆書作品を書きました。
呉昌碩が荃廬にこんなことを聞くのは、自分にあこがれ、自分に弟子入りしながら、趙之謙の書画を熱心に収集している荃廬にさみしい思いをもっていたからではないでしょうか。
これは荃廬が優秀な弟子であればなおさらでしょう。そんな優秀な弟子には自分以外に目を向けてほしくなかったに違いありません。
おわりに
河井荃廬は、日本の書道篆刻界の指導者として活躍し、その影響を受けた西川寧や松丸東魚が世間に広く知らせらことで、より尊重されるようになりました。
この荃廬の原点は呉昌碩にあると言えます。
呉昌碩は荃廬の才能を高く評価し、とてもよく面倒をみました。
ただ、優秀な弟子ほど、自分のところだけに留まってはくれず、内心は寂しかったことでしょう。呉昌碩の師としての思いを考察してみました。
書道が上手になりたい!扱いやすい書道筆をお探しの方へ
書道を続けているけど、
「お手本のようになかなか上手に書けない…」
「筆が思うように動いてくれない…」
という方も多いのではないでしょうか?
そんな方のために使いやすさを追求した書道筆「小春」を紹介します。
毛の長さがちょうど良く、穂の中心部分にかための毛が採用されているため、弾力がでてしっかりとした線が書けます。穂の外側は柔毛のため線の輪郭もきれいです。
半紙4~6文字に適しています。
Amazonで気軽に購入できるので、試してみてはいかがでしょうか。
書道ライフをより充実させられる筆に出会えることを祈っています!
当メディア「SHODO FAM」では、
書道についての歴史や作品、美学などを紹介しています。
書道についてのさまざまな専門書をもとに、確実で信頼性の高い情報をお届けしています。
書道についての調べものの際にはぜひご活用ください。