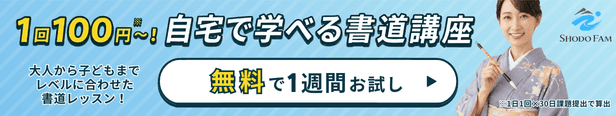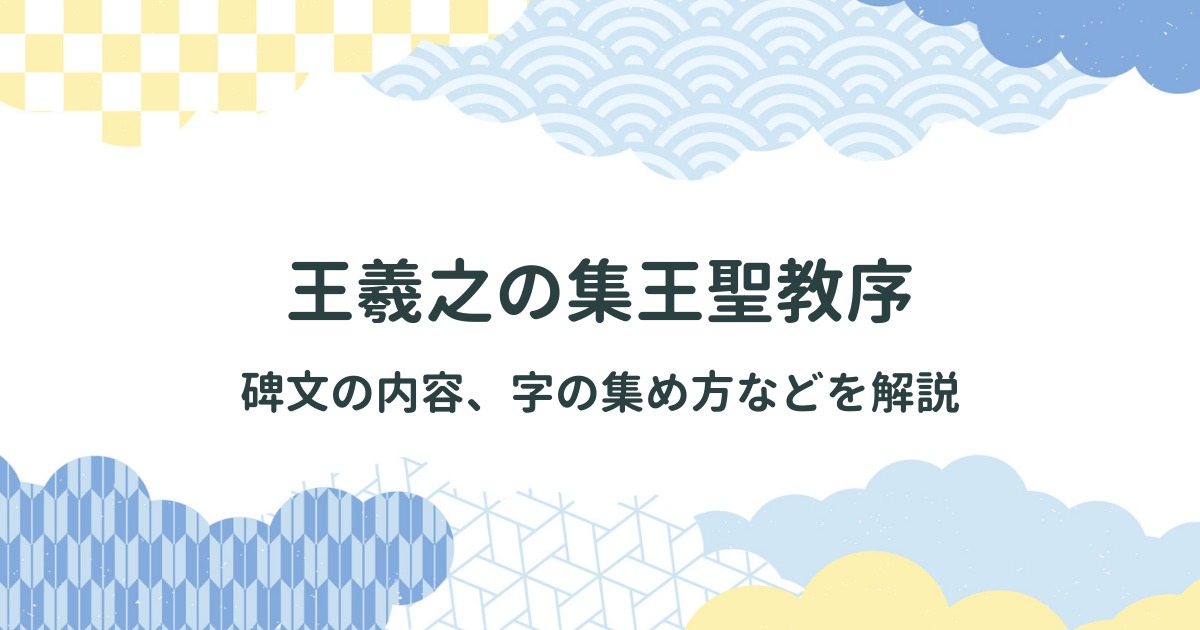今回は、集王聖教序の呼び方で、どういったものなのか、文の内容などを解説していきます。
集王聖教序の概要
「集王聖教序」は、中国唐時代に王羲之の真跡から文字を集めて(集字して)作られた碑の拓本です。
当時の都であった長安の弘福寺の懐仁という僧侶が24年の歳月をかけて完成させ、672年に碑が建てられました。
王羲之の字姿をもっともよく伝えるものとして古来、学書の手本としても珍重されてきました。
碑文の冒頭にあるように「大唐三蔵聖教序」とも呼ばれています。ほかに、碑の上部に七体の仏像が彫られていることから、「七仏聖教序」とも称されています。
王羲之の字を集めて作成されたので、一般には「集王聖教序」「集字聖教序」の名で親しまれています。
これは唐の僧・玄奘法師が持ってきたサンスクリット語(古代インドの文語)の経典を中国語に翻訳した業績を記念するために作られました。
碑文の主な内容は、唐の太宗皇帝が玄奘の経典を翻訳したことを称えるために書いた序文、皇太子・高宗による序記、玄宗による「謝表」、および「心経」です。
玄奘は、三蔵法師という名前で3人の弟子と天竺まで経典を求めて旅する物語、「西遊記」で有名です。
現在は陝西省博物館の西安碑林の第二室に列置され、私たちは高さ350センチ、幅113センチの立派な碑を今でも見ることができます。
碑文のくわしい内容
太宗皇帝による序文、高宗による序記にはどのようなことが書かれているのでしょうか。その内容について簡単にまとめてみます。
太宗皇帝による序文
太宗の序文では、仏教が崇高で奥深いことを説き、その教えがインドに興り、中国にも福音(救い)をもたらしたが、真の教えとは程遠いことを述べます。次に、清らかな精神と非凡な才知をもつ玄奘が、仏教をより研究しようとインドへ行くことを志し、旅の苦労を超えて三蔵の経典を国へ持って帰り、翻訳した功績を称えます。最後に、この経典が広がって日月とともにおろそかにおろそかにならず、至福が永遠にもたらされることを願います。
これに対し玄奘は「あなたにむなしくお褒めの言葉をわずらわせた」と謙虚な返答もあります。
高宗による序記
高宗の序記は、最初に聖教はさまざまな理法(道理にかなった法則)の根元であり、あらゆる経典の規範であるが、奥深くなかなか研究し尽くせない、といいます。つぎに、皇帝陛下の聖徳によって仏教が中国に広められ、玄奘がはるかインドから聖教を携えて帰国し、命令を受けて弘福寺で翻訳した経緯を記します。そして、陛下が美しい序文をおつくりになったので、序記を作ってこれに添えます、と述べます。
これに対しても玄奘は謙虚な返答をし、さらに高宗が「労をかけて申し訳ない」と返答しています。
般若心経
最後に般若心経が刻されています。そもそも般若心経は「大般若経」という600巻におよぶ長編の経典から、その神髄を抽出したものです。原点はサンスクリット語なので、さまざまに漢訳されていますが、日本で広く読まれているのが玄奘訳の般若心経です。
集王聖教序は王羲之の書を集めたもの
この碑は「書聖」王羲之の書跡から文字を集字して、あたかも王羲之が書いたように似せています。
実際、碑文の二行目に「弘福寺の妙門懐仁が晋右将軍王羲之の書を集む」と書かれています。
王羲之は、4世紀中期の人で、集王聖教序が建てられる300年ほど前の人です。その当時から書家として有名で、その書跡は珍重されました。
唐代に入り、太宗皇帝は王羲之の書を大いに好み、「蘭亭序」をはじめとして、大量の王羲之の書跡を収集しました。そして自らも王羲之の字を学び、臣下にもこれを学習させました。
この太宗が収集した大量の王羲之の書跡の中から、文字を集字して作られたのが、この「集王聖教序」です。
懐仁による集字
弘福寺の僧・懐仁が、20年ほどの歳月をかけて集字したとされています。
弘福寺をはじめとする都の僧侶たちが、太宗にこれを石に刻す許可をえて、その後懐仁らに託して王羲之の字を集めて碑に彫らせました。
碑の文字数は、重複を含むとはいえ1900字を超えますから、相当な量の原跡がないと不可能です。
内府に収蔵されていた王羲之の書跡からのほかに、当時懐仁は、王羲之の筆跡を収蔵している人がいると聞くと、どれほど遠くても訪ねていき、それを借り受けました。また王羲之の書跡を持っており、この機会に乗じて高値で売って、大儲けしようというものに対しても、懐仁は大金で買い取ったと言います。
他にも王羲之の文字を集字したものとして、「興福寺断碑」「新集金剛経」がありますが、彼の字をよりよく伝えるものとして「集王聖教序」が最も優れています。
ほかの「聖教序」
玄奘法師は、懐仁に王羲之の字を集めてもらっている間に、当時の著名な大書家である、褚遂良にも「心経」を書いてもらうように依頼し、碑を西安にある慈恩寺の大雁塔の下に建てました。これが、「雁塔聖教序」です。
雁塔は、インドから将来した経典などを安置しておくために建てられた塔です。
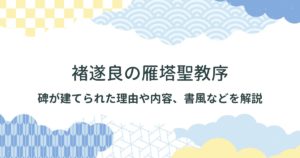
集王聖教序は王羲之の文字を伝える貴重な資料
現代において王羲之の真跡作品は1つも存在していません。
今あるのはこの碑をはじめ、模本といわれる写しや、法帖に刻されたものばかりです。
そのため、この碑は王羲之の文字を伝える最も貴重なものの1つということができます。
「集王聖教序こそ、王羲之の行書にもっとも準拠すべき作だ」、という人がいれば、「間違いなく摸本から採り、懐仁の、すなわち唐人の好みにあった王羲之が入り込んでいるため王羲之の文字の真相を見ることはできない」という意見もあります。