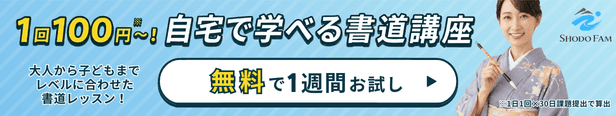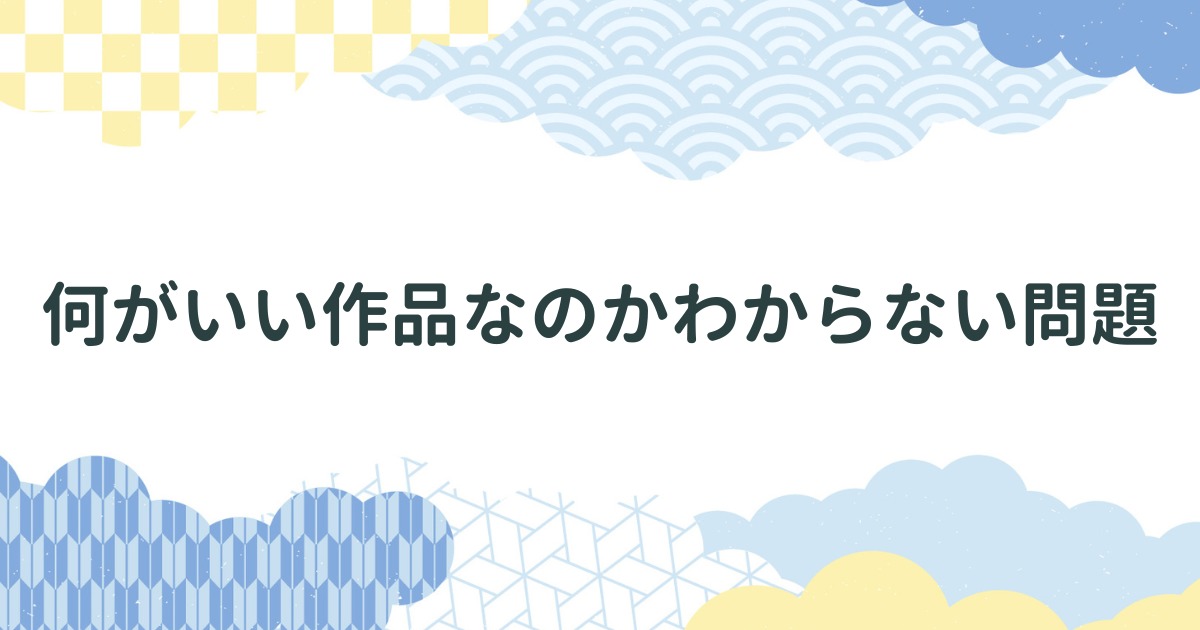なにがいい作品なのか正直よくわからない問題
昔よりは減ったかもしれませんが、現在でも身近に筆で書いた書道の作品を見かけることはあります。お習字教室も、またその発表会に並ぶ作品も書道作品の1つです。
その作品をみてなんとなく「うまい」「へた」「勢いがある」「弱々しい」などとは感じても、本当に「良い」のか「悪い」のか自信をもって判断できる人は少ないのではないでしょうか。
これは、「書道は習い事」という意識によって、現代の書道に対する価値基準がゆがんでしまっているからだと考えられます。
なかには「この作品はいつまで眺めていても飽きない」だとか「心が落ち着く」「勇気づけられる」とおもう人もいます。
もし、書道の作品が人の心を落ち着かせたり、人を勇気づけられたりすることがあるとすれば、書道に「美」というものは確実に存在すると考えられます。その「美」とはどこから来るのか、それを解き明かすことが、本来の書道の在り方を解き明かすことにつながるのです。

書道は習い事の1つという意識
「書道」というと、一般の人は何を思い浮かべるでしょうか。
子どもが習字教室に通う姿や、子育てのめどがついた主婦の趣味など、「習字」を思い浮かべる人がやはりいちばん多いのではないでしょうか。
メディアからわかる書道は習い事という意識
今の時代さまざまなメディア媒体がありますが、新聞においては書道に関する記事がとり上げられることがよくあります。
その内容に注目してみると、ほとんどが町の公民館や美術館などでの団体展、つまり書道教室の発表会です。書道は、華道や茶道と同じような習い事であり、書道展というのは、習い事の発表会という一般の人々の意識が新聞記事からはっきり見えてきます。
華道や茶道のことを、書道よりも下に見ているつもりはありません。むしろ逆で、近代以降、華道や茶道は公の権力や教育機関、知識人から見捨てられてしまいますが、これらの文化を延命させたのは習い事文化であり、一般大衆から受け入れられ続けてきた証拠なのです。
華道や茶道や書道は、多くの人々の根強い共感と支持があったからこそ、これらは習い事に姿を変えながら生き延びてきました。
書道展(公募展)は書道教室の発表会
書道展は、美術展とおなじ美術館で開催されることはあっても、美術展と書道展はちがった様式をとります。
書道展は、たとえ公募展と名乗っていても、それを運営する方々が持っている書道教室の習い事発表会となっています。運営している会派に属していない人が、いくら素晴らしい作品を出品しても、入選できる枠はごくわずかです。
知らない人の習い事発表会を観たい人はいませんよね。そのためほとんどの観客は、出品者とその友人、知人です。
新聞社主催の大きな書道展も同じです。審査で入賞作品を選出する、とうたってはいるものの、書道教室の発表会に変わりはありません。
入賞作品が多すぎるため、間隔狭くみっちりと並べられ、2段、3段と壁を埋めつくすように作品が展示されています。展示作品が多すぎるため、受付で作品を観たい人の名前を言うと、展示してある部屋までの道順を赤色のペンで書きこんだ地図を渡してくれることもあります。
ちなみに、大きい新聞社主催の公募展の出品数は約2万点。入賞率は6割ほどもあります。6割をきると「今年の審査は厳しかった」といわれる世界です。
こういう大規模な書道教室発表会を、文化勲章・文化功労章受賞者・芸術院会員などの肩書をもった書道家が頂点で取り仕切ります。
日本の政治家が、市町村議会議員から都道府県議会議員→国会議員→大臣→総理大臣というコースを描くように、日本の組織は地方から中央へという立身出世型、年功序列型のような形をとりたがるのです。書道の組織構図も例外ではありません。
昔の書道家の作品は評価されない?
書道というとまっさきに思い浮かぶ子供の習字教室や、またその発表会に並ぶ作品も、書道の作品の1種であることには違いありません。
しかし、少し考えてみると、おかしなことに気づきます。
たとえば、書道史に登場する王羲之、唐時代の太宗皇帝、顔真卿、蘇軾(蘇東坡)、黄庭堅(山谷)らは、中国の優れた政治家でした。
日本の空海、嵯峨天皇、小野道風、藤原行成なども、それぞれの時代を背負った有名な能書(字を書くのが上手な人)でした。
現在習字に熱心な子どもや主婦の習字、またはその先生の作品と、これら書道の歴史上の担い手の書道作品は、全く違っています。
「昔の書道家たちの作品を現在の書道展に出品したら、きっと落選するだろう」というブラックユーモアさえあるほどです。
近代以降の書道作品が評価しづらくなった原因を時代のせいにするのは簡単です。時代のせいなのはあたりまえだからです。
しかし、近代以降、とくに戦後の書道作品のとらえ方や見方は、時代的限界に色濃く縁どられた大きなゆがみを持っています。その歪みが近代以前の書道作品を見えにくくし、自分で書くことについても、自信とこれが正解だという確信を失わせてしまっているのです。
近代以降出てきたさまざまな書道についての意見を再検討し、採用するべきところは採用し、捨てるべきところはきっぱりと捨て去り、歴史的かつ現代的視点を獲得することができれば、書道はきっとおどろくほどみずみずしい姿に生まれ変わるのではないでしょうか。
書道は暗く、辛気くさく、古くさいように見えます。事実その通りかもしれませんが、その読み方が深まるとても魅力的なものなのです。
絵画のような書道作品しか売れない
こういった書道=教育という価値観から脱却したいと思い、書道教室でお金を儲けるのではなく、作品を売って儲けたいと思う人たちが出てきます。
しかし、書道展は事実上、書道教室の発表会となっているように、お金を払ってまで作品を買いたいというマーケットは作られてこなかったのです。
そこで、1部の書道家の方々は、書道を絵画のような美術の一環として位置付けることができれば、作品に金銭的価値が生まれると考えたのです。
書道の作品を絵画のように売れる作品にするべきだと考え、現代美術のような作品をつくり、ギャラリーに並べます。本来の書道の研鑽や解明などよりも、現代美術の知識を仕入れることに励んでいます。
気持ちはわからないでもないですが、このような方々は伝統的な書道をしているひとからすると、
「いいとおもうけど、、これは書道なのか、?(笑)」
となります。境界線があいまいになってしまいます。
絵画のような価値観で見てもらう書道作品のほうが売れるのはわかります。伝統的な書道作品に金銭的価値がつかなくなってしまったのは、市場を育成してこなかったこれまでの書道界の責任でしょう。(絵画は金銭的価値がつくように文化をつくってきています。)
書道が身近にない人が、書道に触れる入りはこういった作品でもいいですが、そこから興味をもってくれた人にはルーツ(歴史)も深めていってほしいものです。
書道とはどうあるべきなのか、本来の書道は習い事ではない
書道は大衆の人々による習い事文化によって支えられてきました。
しかし、それがきっかけで書道を教育と考える大衆的意識が定着してしまいました。
書道を教育ととらえる大衆の視点からは、「うまい」「へた」という評価しか生まれてきません。本来の書道というのは、そもそも「うまい」「へた」という評価基準はないにもかかわらずです。
書道というのは、書道という固有の表現です。
近代、現代という時代に、西欧思想が入ってきたことによってかなりゆがんだ形になってしまいましたが、本来の書道とは1つの表現であって、決して教育にとどまるものではありません。
書道の歴史、つまり書道という表現の歴史の末端に現在の書道の表現があるのです。
評論家の文章が国語の教科書に引用されていても、その文章は受験生のテキストではないように、王羲之や顔真卿などの筆跡もまた、書道の手本ではなく、書道という表現の歴史なのです。
「うまい」「へた」、習字・書道教室、書道展といった教育、習い事の観点からは、本来の書道は姿を現しません。
書道の歴史の末端に、可能かどうかは置いておいて、現在の書道の表現があります。その表現を支える根底に、習字・書道教室、書道展があるという視点を回復しない限り、本当の書道の理解、またそのおもしろさには出会えないのです。