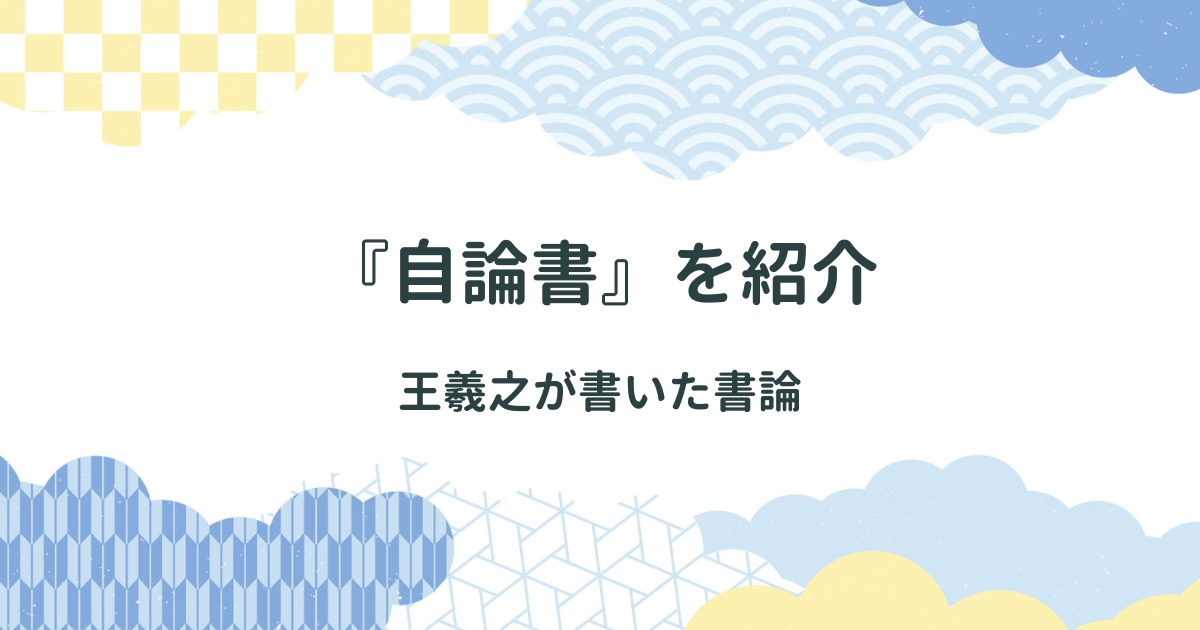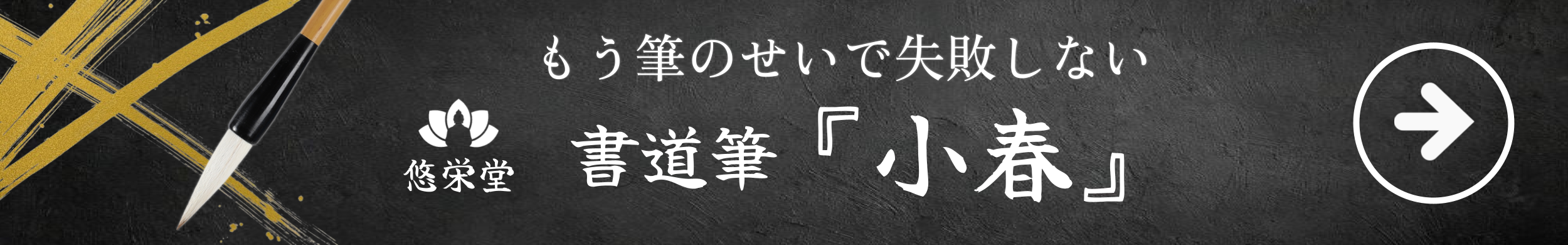自論書について/内容
自論書は、王羲之が書いた書論です。
書論とは、書について語られた文章のことです。
王羲之の書論として伝わるものはほとんどが後世に作られた偽物とされていますが、「自論書」は王羲之自身の手によって書かれたものと信じられる唯一のものです。
自論書の内容としては、王羲之は魏時代の鍾繇と後漢時代の張芝の2人を古今の「二賢」としてあげ、彼自身の書はこれらに対抗できる、もしくはこれらに次ぐという自信を示してします。
文字はもともと伝えるための道具でしたが、後漢時代ごろから書の美しさが鑑賞の対象とされるようになり、その優劣を比較することが大きな関心事となりました。
王羲之も他の書家と自分の書を比べているのです。
鍾繇についてくわしくはこちら↓

自論書の現代語訳
私の書は鍾繇・張芝にくらべてもきっと対抗できるし、あるいはそれ以上であるかもしれません。しかし張芝の草書には少しあとからついてゆかなければならないでしょう。
張芝の技法は成熟において人よりすぐれ、池の前で書を学んでいると、池の水がすっかり墨になったと伝えられます。もし私もこのくらい書に没頭できれば、必ずしも彼におくれをとることはありますまい。後世の達式の人は、私のこの批評がまちがっていないことを理解してくれるでしょう。
私はすぐれた書を作るために心をくだき、また久しく諸々の先人の書を尋ねてきましたが、ただ鍾繇と張芝だけはまことに並はずれて優れており、その他は少しはいいところはあっても、心をとめるに足りません。この二賢を除けば、私の書がこれに次ぐでしょう。
先ごろお手紙をいただきましたが、心ばえいよいよ深く、点画の間にみなすぐれた趣があり、なかなか言葉で言い尽くせないものがあります。妙を得たものは何事につけてもみなそうなのでしょう。平南(王廙)や李式があなたを批評しても、あなたはひけをとることはありますまい。
平南は右軍の叔父で平南将軍の王廙である。李式は晋の侍中。
自論書の原文
吾書比之鍾張、當抗行、或謂過之。張草猶當雁行。
張精熟過人。臨池學書、池水盡墨。若吾耽之若此、未必謝之。後達解者、知其評之不虛。
吾盡心精作、亦久尋諸舊書、惟鍾張故爲絕倫。其餘爲是小佳、不足在意。去此二賢、僕書次之。
頃得書、意轉深、點畫之閒、皆有意。自有言所不盡。得其妙者、事事皆然。平南李式論君不謝。
平南卽右軍叔平南將軍王廙也。李式晉侍中。