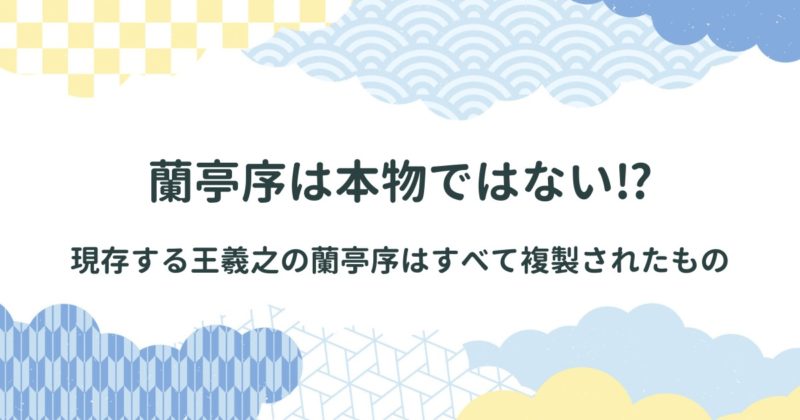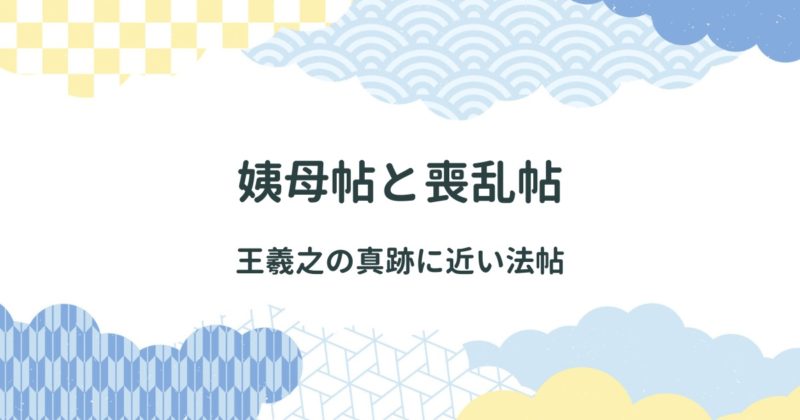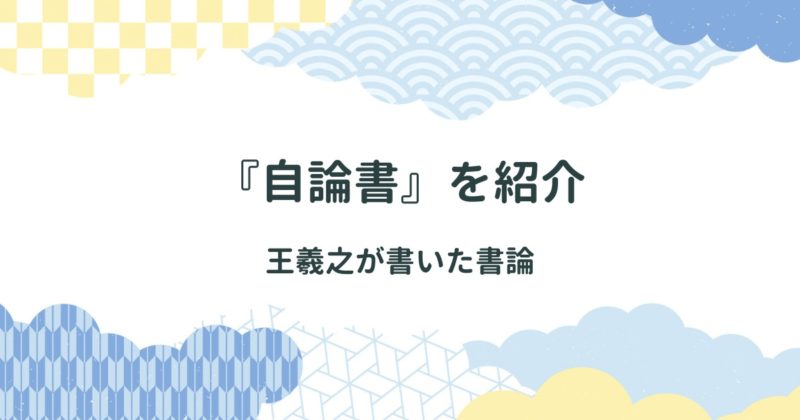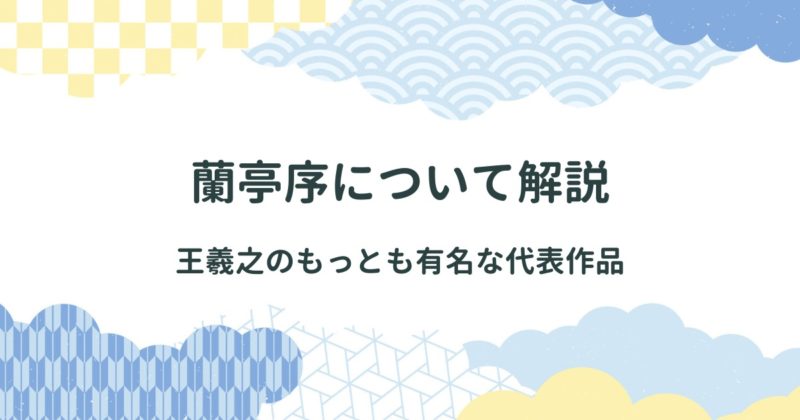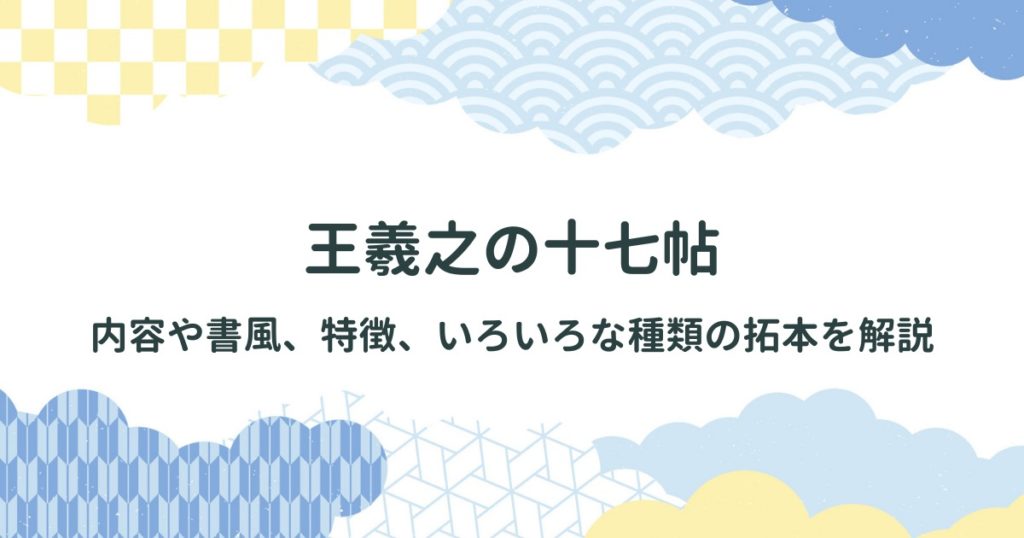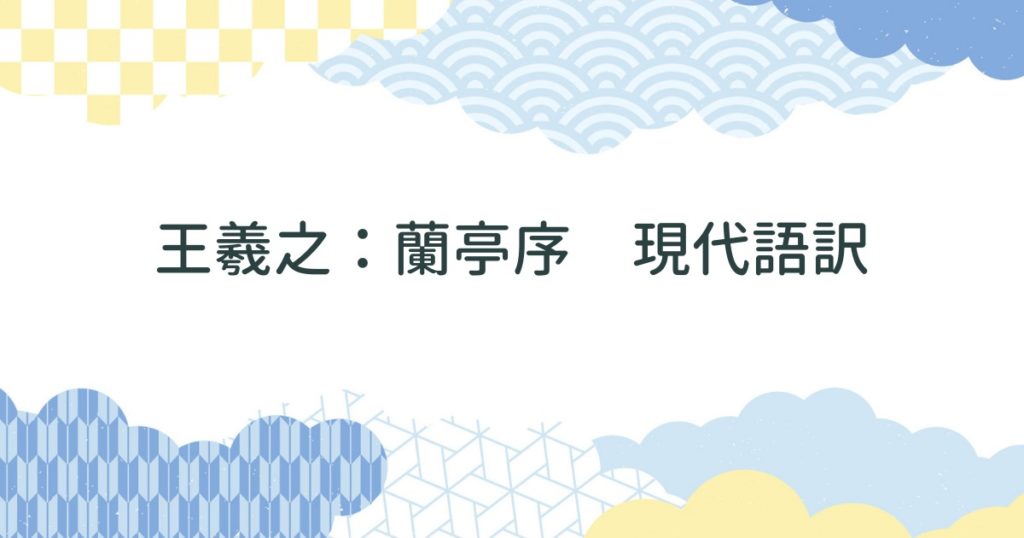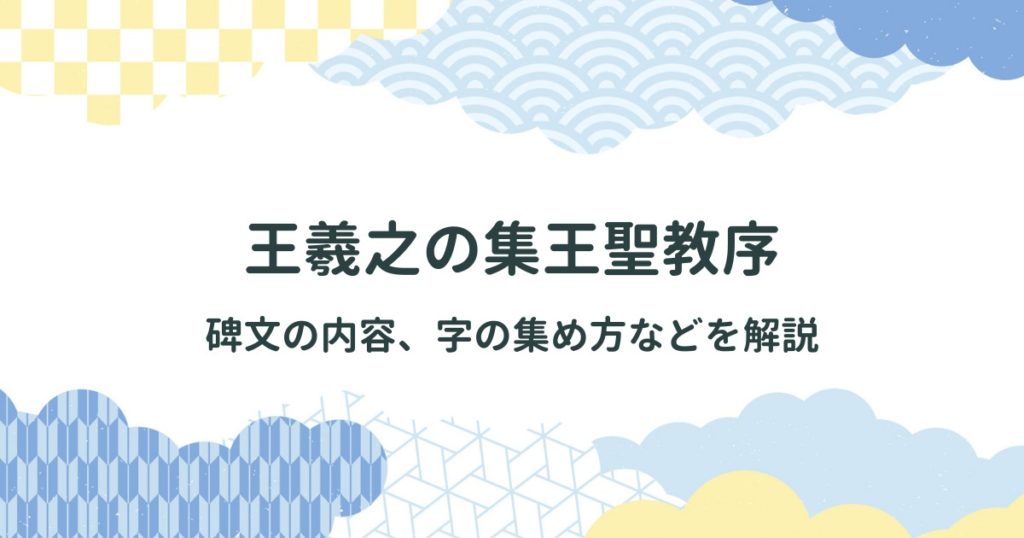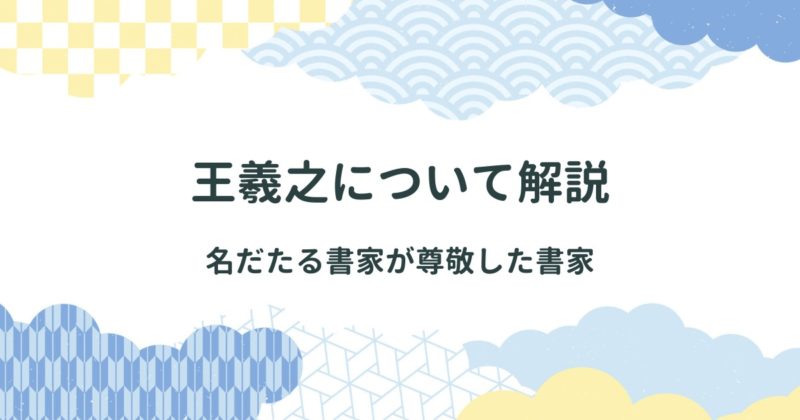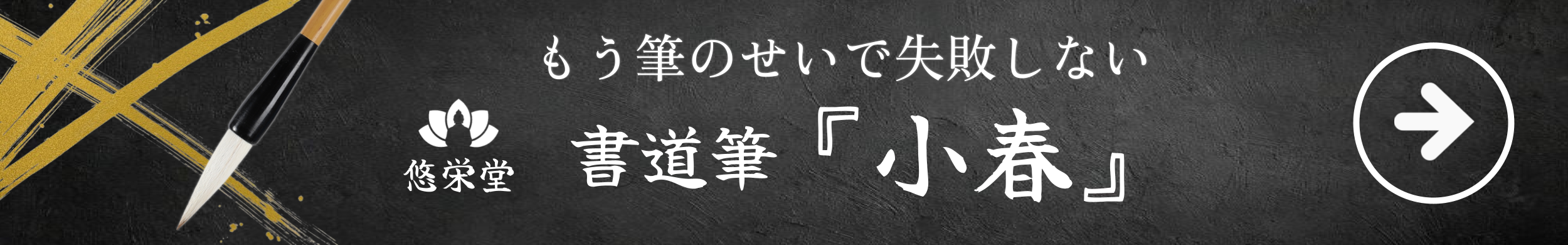王羲之– tag –
-

王羲之が生きていた六朝時代の書風とはどのようなものだったのか/蘭亭序の複製本3つを紹介【ハ柱第一本・第二本・第三本】
私たちがよく知っている王羲之の蘭亭序ですが、じつは本物ではなく、後の時代の人によって複製されたものです。 真跡は現存しておらず、だれもその本物の文字がどのようなものだったのかわからないのです。 そのため、複製本である蘭亭序が当時の文字を正... -

姨母帖と喪乱帖について解説/王羲之の真跡にもっとも近い法帖
王羲之」です。 「姨母帖」は20歳代の若いころの作品であり、「喪乱帖」は晩年の作品です。 姨母帖と喪乱帖について紹介していきます。 【姨母帖(いぼじょう)について】 王羲之「姨母帖」 姨母帖は、『万歳通天進帖』という巻の冒頭にあります。 姨母ん... -

王羲之の書論「自論書」を紹介/内容・現代語訳・原文
【自論書について/内容】 自論書です。 書論(しょろん)とは 書論とは、書について語られた文章のことです。 王羲之のものです。 自論書」としてあげ、彼自身の書はこれらに対抗できる、もしくはこれらに次ぐという自信を示してします。 文字はもともと伝... -

王羲之の蘭亭序(らんていじょ)について詳しく解説【臨書の書き方・特徴、何がすごい?本物は存在しない?】
書聖が挙げられます。 中国の書道の歴史上、最高傑作として評価され、現代でも大きな影響力を持っています。 しかし、真跡は昭陵へと収められ、その本当の姿は、おびただしい数をつたえる拓本・紙本の向こうに見えかくれするばかりです。 今回は、そんなミ... -

王羲之の十七帖について、内容や書風、特徴、いろいろな種類の拓本を解説
十七帖は草書を習得するため古来より草書の典型とされ、多くの人に尊重されてきました。 今回は、十七帖について、内容や書風、特徴、いろいろな十七帖の拓本を解説していきます。 【十七帖について】 十七帖(じゅうしちじょう)は、王羲之の手紙29通を集... -

王羲之:蘭亭序の内容を全文現代語訳で紹介
書道をされている方なら必ず知っているであろう王羲之の蘭亭序。 漢文で訳も分からず書いているけど、一応意味も知っておきたいと思いませんか? 今回は王羲之の蘭亭序の現代語訳を全文を紹介します。現代風に意訳した部分や、新字体を用い、現代かな使い... -

王羲之の字を集めた集王聖教序:碑文の内容、字の集め方などを解説
今回は、集王聖教序の呼び方で、どういったものなのか、文の内容などを解説していきます。 【集王聖教序の概要】 「集王聖教序の真跡から文字を集めて(集字して)作られた碑の拓本です。 当時の都であった長安という僧侶が24年の歳月をかけて完成させ、67... -

王羲之(おうぎし)について解説/王羲之とはどんな人物だったの?なにがすごいの?
中国で書道が完成の域に達したのは、王羲之時代であると言えます。 中国の書の歴史においてもっとも高い地位を占めている彼の書跡は、学習が盛んに行われて、やがてそれが中国の書の伝統な流れを形成し、永く伝統派の書道として伝えられてきました。 王羲...
1